翌朝・・・。
「うーん・・・。」
私達3人は、昨日キャンプをはった場所で唸っていた。ここから先は、あの薄気味悪い森になるはずだった。だが・・・。
「どう見ても・・・ここと同じだよな・・・。」
「私にもそう見えるな・・・。」
「ちゃんと遠くまで見通せるわよね・・・。」
私達がこの間迷い込んだ森は、木々の間は全て真っ暗で、先などとても見渡せなかった。だが今、目の前に広がっているのはこの場所と同じさわやかな森だ。木々の間から光が差し込み、美しい景色が広がっている。
「とにかく、ここで唸っていても仕方ない。荷物をまとめて、はぐれないように手を繋いでいこう。」
私達はここに来た時と同じように、一列になって森の中を進んでいった。私が結界で作ったはずの道はなかったが、木々の間はそれほど密集しているわけでもなく、歩くのに障害になりそうな物は特にない。そして・・・。
「桟橋だな・・・。」
「船もちゃんとあるね・・・。」
歩き続けて、いつの間にか船を着けた桟橋まで辿り着いていた。
「ああ!?あれを見て!」
ウィローの叫び声に振り返ると、そこに広がっていたのは・・・
「あの森じゃないか・・・。」
「しかもこの道は、最初に見つけた、あの真っ直ぐな道だよね・・・。」
ここで船を下りた時と同じように、船着場からは一本の道が真っ直ぐにのび、辺りは鬱蒼とした薄気味悪い森に変わっていた。
「つまり、これも魔法の産物ってことか・・・。」
「多分100年以上前のサクリフィアの巫女姫達が作り上げた物なんだろうけどね。」
「まったく・・・魔法ってのは俺達の理解を超えてるな。」
「もうここを出るわけだし、あまり深く考えないでおこう。」
「そうだな・・・。」
なんだか狐につままれたような気持ちではあったが、いつまでもここでぽかんとしているわけにも行かない。来た時と同じように、私達は船に乗り込み、サクリフィアの村へと向かった。
「静かなもんだな・・・。」
舵を取りながらカインがぽつりと言った。運河はほぼまっすぐに延びていて、海での操船のように舵を切らなければならないことはほとんどない。さわやかな風が頬をなでて、まるでのんびりと舟遊びをしているような気分だ。
「ついさっきこの近くにドラゴンが現れたって言うのにね。」
「まったくだ。でも昔はこの運河のすぐ近くまで人が住んでいたんだろうなあ。」
「水の近くには人が集まるって言うのが普通だからね。」
「それにこの運河の水、すごくきれいよ。底のほうには魚もいるんじゃないの?」
船にはだいぶ慣れたウィローが水底を覗き込んだ。船の揺れも少ないせいかここに来てから船酔いはしていない。
「この運河の結界も100年以上前にかけられたままらしいから、古代のサクリフィアでは漁もやってたかもしれないな。」
「そうよねぇ。」
カインは『サクリフィアの錫杖』を手に入れてすっかり笑顔だし、ウィローも昨日のように取り乱していない。でも・・・
(気になるなあ・・・。何でカインは何も言わないんだろう。)
それとも、カインは私達が最初の予定通りにエルバール王国に戻ると思ってるのだろうか・・・。でも私は昨夜セントハースの言葉をはっきりと伝えた。『エルバール王国に戻っていたのでは間に合わない』と。つまり私達は、フロリア様を元に戻すより先に飛竜エル・バールに会いに行かなければならないのだ。カインが行こうともだめだとも言わないのはどうにも気にかかる。
「お、見えてきたぞ。」
神話の作者の家が前方左側に見えてきた。ここまでくれば船着場はすぐそこだ。
「2日か3日くらいしか過ぎていないのに、なんだか久しぶりな気がするな。」
カインはのんきそうに笑っている。そしてカインを包む『気』も、特に張りつめているわけでもない。
(考えすぎなのかな・・・。)
だとすればもう気にするのはやめるべきなのだろうけど・・・。神殿の前で突然感じたあの奇妙な感覚は、未だに私の頭の中に居座っている。
サクリフィアの村に着いたのは、もう夕方だった。村に入るなり、メイアラが走ってきた。
「あ・・・あなた達無事だったの!?」
メイアラは真っ青だ。
「無事だよ・・・どうしたんだい?」
カインが尋ねた。
「昨日、神殿のほうから東に向かって、ものすごい大きな何かが空を飛んでいったの。まるでドラゴンみたいな・・・。」
「セントハースかな。」
「ああ、そうだろうな。他にドラゴンなんていなかったし。」
「え・・・・?」
ぎょっとして固まっているメイアラに、とにかく事情を説明するから村長の家に一緒に行こうと提案した。
「・・・わかったわ・・・。村長も心配しているのよ。行きましょう。」
「おお、メイアラ、様子は・・・なんと!あんた方が戻ったのか!無事だったんだな!」
村長の家では、村長とランスおじいさん、そしてリーネが青い顔で待っていた。私達が今このタイミングで戻ってくることは知らなかったらしい。もっともそれが普通なのだが・・・。
「神殿の方角から、とんでもない大きなものが空を飛んで去っていったと聞いたものでな。メイアラに様子を見てきてもらおうと思ったのだが・・・。あんた方が戻ってきてくれたのはうれしいことだ。」
「でも様子って・・・どうやって見てくるんですか?」
「この村は高台にあるから、村の入口の辺りまで行けば、神殿の方角を多少窺うことは出来るのよ。私の力でもね。でもその前にあなた達と会ったから、戻ってきたわけ。あなた達から様子を聞けるならありがたいけど・・・さっきの話は本当なの?」
メイアラの顔色はよくない。『セントハース』などと聞けば、それも無理からぬことか・・・。サクリフィアの国を滅ぼすべく攻めてきたモンスター達を率いていたのは、ほかならぬ聖戦竜と呼ばれた3匹の竜だ。
「メイアラよ、まずは座ってもらおうではないか。みんな疲れておるじゃろうて。それからリーネ、気は進まんが、グィドー老達を呼んできてくれぬか。我々だけで話を聞いてしまうと、大事な話を隠したのではないかなどと言われかねんからな。」
「はあい。みなさん、お帰りなさい。ゆっくりしていて。私も気が進まないけど、グィドーじいさん達を呼んでくるわ。」
リーネは言いながら肩をすくめて見せて、部屋を出て行った。私達は荷物を下ろしてソファに座り、お茶をご馳走になった。しばらくしてリーネがグィドー老人達を連れてきた。なんとその後ろから、あの武器屋の主人、バルディスさんまでもが顔を出した。
「・・・なんであなたまで来たの?」
メイアラが戸惑った様子で言った。
「リーネから、ファルシオンの使い手達が戻ってきたと聞いたからな。さっき空を飛んでいった黒い影と、何か関連があるかも知れん。そう考えて話を聞かせてもらいに来たというわけだ。」
その言葉を聞いたグィドー老人が忌々しげにバルディスさんを睨んだ。
「ふん、仕方あるまい。話の内容によっては、バルディスの鍛治の腕が今後ますます必要になってくるかも知れぬのだからな。」
「まあまあグィドー老、みんなも座ってくれ。せっかく剣士殿が無事で戻ってこられたのだ。話を聞かせてもらおうではないか。」
みんなが席に着き、リーネがお茶を入れてくれた。カインは荷物の中から、大事にしまっていた『サクリフィアの錫杖』を取り出した。
「まず最初に、村長さんにこれをお返しします。」
「それと神殿の鍵です。ありがとうございました。」
カインはそう言って、テーブルの上に『サクリフィアの錫杖』をおき、私も神殿の鍵を取りだし、隣に置いた。
「うむ、確かに返してもらったぞ。」
村長はまず神殿の鍵を取り上げ、懐にしまった。そして『サクリフィアの錫杖』を見て・・・
「これが・・・『サクリフィアの錫杖』なのか・・・。」
心なしか顔が少しこわばっている。
「これがどこにあったのか、どうやって手に入れたのか、そして神殿の中がどうなっているのか、それについて説明する前に、これが本物だってことを確認してほしいんです。」
「う・・・うむ・・・。」
村長が少し震える手で『サクリフィアの錫杖』を持ち上げた。
「む・・・・こ、これは確かに・・・。」
村長は、杖の形状やはめ込まれている宝石などの『見た目』には目もくれず、杖を持ち上げたり、軽く振ったりしている。魔法に縁がない私達にはただの杖にしか見えないが、村長は見た目ではなく本当に力を秘めているのかどうかで判断しようとしているようだ。この村で使われている『神術』という名の魔法を使う人々には、杖に触ればこれが本物か偽物かわかるのだろうか。
「どれ村長、見せてみよ。」
グィドー老人が進み出て、『サクリフィアの錫杖』を手に取った。
「む・・・!」
グィドー老人は驚いたように手を離した。
「・・・確かに、魔法の力を霧散させるようだ・・・。」
「私がやってみるわ。」
メイアラが言って、杖に向かって何か唱えた。奇妙な気の流れがメイアラから放たれたが、杖の手前でその流れはぱっと砕け、消えてしまった。
「見るのは初めてだけど・・・これが偽物ではありえないってわかるわ・・・。こんなものを作っていたなんてね・・・。」
メイアラの顔はさっきより青ざめている。
「しかも力はいささかも衰えておらぬようではないか。メイアラとて巫女姫として選ばれるだけの力を備えておるというのに、この小さな杖はその力をいとも簡単に霧散させてしまった・・・。」
「と言うことは、間違いなくこれが本物だと認める、こういうことでいいのかの、村長よ。」
ランスおじいさんが言った。
「ああ、認めよう。グィドー老よ、どうだね、あんたもこれを偽物だとは言わんだろう。その辺の枝切れにガラス玉をはめ込んだ偽物などを持ってきたわけではないと、認めてくれるかね。」
グィドー老人はだいぶ渋い顔をしていたが・・・
「ふん、認めるしかないだろう。」
そう言ってフンと鼻を鳴らした。
「よし、では剣士殿、改めて話を聞かせてくれ。出来れば、あんた方が神殿に向かったところから、神殿のある北側がどんな状態なのかを教えてくれると実に助かる。」
「その前に村長さん、聞いていいですか?」
カインが言った。
「ん?私に答えられることなら何でも答えるが?」
「村長さんなのかどうかはわからないけど、神殿のある北側の陸地に、行ったことがある人はいるはずですよね。」
一瞬、部屋の空気がピリッと震えた気がした。だが村長は穏やかな微笑を崩さず
「ああ、いるとも。」
そう答えた。
「そうですか。それじゃ、船着場から延びる道の先までは?」
「行ったことがあるのはそこまでだ。だいぶ前の話だがな。そうだなあ・・・デール卿がこの村を訪ねてきた、そのあとのことか。デール卿が訪ねて来たことで、何か神殿に変化があるかもしれないということでな。当時の巫女姫と、神官の末裔、それに巫女姫の侍女達と、その巫女姫達を守る我らのように腕っ節にはいささか自信のある男達が何人か、北の台地に向かって船を出した。」
「神殿まで行ったんですか?」
「行こうとはしていた。巫女姫の制御を失ったというガーディアン達を恐れていたのがばかばかしいと思えるくらい、楽な道のりだったが、残念ながら我らは神殿まで辿り着くことが出来なかった。」
不意に村長の顔が険しくなった。
「出来なかった?あのさわやかな森を抜ければ、それほどかからず辿り着けると思うんですけど。」
カインが不思議そうに尋ねた。
「うむ・・・。その時まで北の大地がどういう状況なのか、それについて知らなかったことは確かだ。だがあんた方も見たと思うが、船着場のすぐ目の前に迫る薄気味悪い森も、その成り立ちは知っていたから、一気に抜けてしまえばどうということはない。あんたの言うように野営地となるあの森は遠い古代の力で護られておる。だが問題はその後だ。森を出るとガーディアンが待ち構えていた。時の巫女姫はそれなりに力のあるお方だったし、神官の末裔もついておったが、とにかく手ごわいモンスターばかりだった・・・。」
そのときのことを思い出したのか、村長は大きくため息をついた。
「何匹かのガーディアンを撃退した後、巫女姫が動けなくなり、神官の末裔も歩けなくなった。結局森へ引き返し、野営地で休んだ後あきらめて村へと戻ってきた。」
「あの時は大変だったのお。巫女姫はしばらく寝込んじまうし、それが村によそ者を入れたせいだと騒ぎ立てる者はおるし、ずいぶんと長いこと村の中が騒がしかったもんだわい。」
ランスおじいさんがため息をついて言った。
「ガーディアンが森の外で・・・?」
「そうだ。あんたらは出会わなかったのかね。」
「いや、俺達は・・・船着場の近くでちょっとしたのに出会ったけど、あの森を出てからはまったく・・・。」
「ほぉ、ガーディアンにも剣の波動がわかったのかのぉ。」
波動に気づいてくれるなら、あの薄気味悪い森の中で気づいてほしかったものだが。
「出会わずにすんだのなら何よりだ。我らがあんた方に頼んだことが、どれほど危険を伴うものだったか、それを知らせなかったことについては実に申し訳なく思う。この通りだ。」
村長が頭を下げた。
「村長、顔を上げてください。私達は無事戻ってきたんですから。」
「村長、俺達はこのとおりぴんぴんしてます。俺達は実際に神殿まで行ってみて、少なくともあの野営地の森までなら苦労しないで行けることがわかったから、実はみんなあの森までは行ったことがあったんじゃないのかなあって、それを知りたかっただけなんです。」
本当は腹が立ったのだが、こうして謝られてしまっては、さらに文句を言うことなど出来ない。
「うむ・・・そう言ってくれて感謝する。剣士殿、私はあんた方が無事に戻ってきたら、今度こそ本当にファルシオンの由来について話すと約束した。その約束を果たさなければならん。」
「その前に、私達の話を先に聞いていただけませんか。」
「それは構わんが・・・いいのかね。それでなくても散々はぐらかしてしまったというのに。」
「今確実に話していただけるなら、多少の時間差については気にしません。それより、私達が神殿で見たこと、聞いたことを皆さんにも知ってほしいんです。カイン、ウィロー、いいよね?」
「お前がそういうなら俺は構わないよ。」
「私もよ。剣のことは気になるけど、話していただけるなら、そんなに焦らないわ。」
「クロービス、お前から話したほうがいいだろう。全部知っているのはお前だけだからな。又聞きのうろ覚えで話して、つじつまが合わなくなったりしたら大変だしな・・・。」
「そうか。それじゃ私から話すよ。」
「どういうこと?」
メイアラが怪訝そうに聞き返した。
「まずは聞いてください。」
森で迷ったことは話さないでおくことにした。あの魔法の本が私の手元にあることを、グィドー老人が知っているかどうかはわからないが、何もわざわざ険悪な雰囲気を作ることはない。そこで、村長の助言どおりに一晩船で休み、翌朝出発してあのさわやかな森で少しのんびりしたことにして、神殿に入ったところからじっくりと説明しようとしたのだが・・・・
いくらも話さないうちに、グィドー老人の『ちょっと待て!』という声にさえぎられた。あの『導師』に出会ったときのことを話しているときだった。
「本当にその・・・『導師』に会ったのか!?」
「本当に会いましたよ。ただ、本物かどうかと聞かれても、あの時会ったのが最初でしたからわかりませんが、『導師』と名乗っていましたよ。」
その『導師』が身に着けていると思われる光り輝く鎧の説明をすると、グィドー老人だけでなく、村長もランスおじいさんも一様に『うーむ』と唸って腕を組んだ。
「あ、いや、すまんな。まずは続けてくれ。グィドー老よ。気持ちはわかるが、今は彼らの話に耳を傾けるときだ。そうではないかね。」
村長の言葉にグィドー老人は小さくため息をつき、『そうだな』とうなずいた。私は『導師』に出会った後、彼の言葉通りガーディアン達は動かなくなり、おかげで神殿内の探索がかなり楽になったこと、そして・・・・
「サクリフィアでもナイト輝石の採掘は行われていたんですね。」
ここは私が話を止めて、村長に尋ねた。
「うむ・・・遠い昔の話らしいがな。200年前から、サクリフィアでは採掘しておらぬ。あんた方が神殿の中で見たとおり、ナイト輝石は聖戦の原因になったとも言われている。」
「それじゃ・・・どうしてそのことをエルバール王国の人は誰も知らないんですか?」
ウィローが呆然とした顔で尋ねた。
「それはわしらにもわからんのだが・・・あえて推測するならば、200年は長いと言うことかも知れぬなあ・・・。」
少し思案げにランスおじいさんが言った。
「200年前、英雄ベルロッドが体を張ってエル・バールと約束したのは、二度と大地を汚さない、そのことだったと聞いておる。当然当時のサクリフィアの民はそのことを知っていた。だから彼らはエルバール王国を建国した後も、鉱山には近寄らずに生きてきたはずだ。だが、英雄と言えども常命だ。サクリフィアの悲劇を心に刻み、新しい土地で明るい未来を拓こうと汗を流した人々もいずれは死を迎える。その後少しずつ代替わりしていく中で、教訓は忘れ去られて行ったのではないかね。エルバール暦175年に鉱山は再び発見されてしまった。175年前の悲劇など何も知らぬ人々が見つけてしまったのだ。」
やはりそういうことか・・・。
「でも、私の父にはその説明は・・・。」
ウィローが尋ねた。
「無論してある。ただし、当時はまだナイト輝石など影も形もなかったころのことだ。遠い昔、死彩と呼ばれた黒い鉱石が原因となって、聖戦が起きた、デール殿に語られたのはその程度のことだ。かなり詳しく聞きたがっていたのは確かだが、この村でも言い伝え以上のことはわからない。どうしても詳しく知りたいなら、かえってあんたの国にある書物を見たほうがいいのではないかと、当時の村長が言ったのだが・・・なかなかそれは難しいと言う話だったな。」
「そうですか・・・。」
デール卿が死彩の存在を認識していたのは間違いなさそうだ。
「・・・それじゃ・・・これはあくまでも私の単なる疑問なんですが、今はサクリフィアにもナイト輝石は流通していますよね。バルディスさんのところで、ナイト輝石の武器防具を拝見しました。サクリフィアにナイト輝石が流通し始めた時、誰も疑問に思わなかったのでしょうか。サクリフィアの人々ならば、その鉱石がどういうものなのかはわかったはずです。」
「つまり、わかっていたのなら採掘を止めることも出来たのではないかと、そういうことかね。」
実に不機嫌そうな声で答えたのはグィドー老人だ。
「お気に障ったのならすみません。でも私には皆さんを責めるとか言う意図はないんです。ただ、サクリフィアの人々にとって、聖戦の元凶がまた掘り出されたなんて話は、とんでもない話だったんじゃないのかなと思ったんです。エルバール王国に、何らかの形で警告したりと言うことはなかったのかなと。」
「それは難しい話だろうなあ。」
ランスおじいさんが首をかしげながらつぶやいた。
「確かにわしらはナイト輝石が遠い昔の聖戦の引き金になったと言うことを知っておる。だがな、わしらとてその時代に生きていたわけではない、言い伝えの一つとして知っているだけに過ぎんのだ。エルバール王国では、ナイト輝石のおかげで強い武器防具を作れるようになり、そのおかげでたくさんの人々がモンスターから救われた。当時のエルバール王国の人々にとって、それは間違いなく福音であったというのに、それをサクリフィアが横からしゃしゃり出て、200年前の聖戦の原因だという言い伝えがあるから元の通り封印しろと言えるかね。わしなら言えんのぉ。それに、仮に言ったところで信用されまいよ。」
「なるほど・・・。それは確かに・・・。」
「第一、当時この村には厳しい掟があったもの。外の世界で何が起きていようと、サクリフィアは行動を起こそうなんて思わなかったでしょうね。」
メイアラの声にはいささか刺々しさがこもっている。
「これこれメイアラよ、そういう言い方をせんでくれ。わしらだって心配はしておったのだぞ。だが、その後も特に何事もなくナイト輝石は流通しておったから、エルバールの人々はうまくやっとるのだろうなと、そう思っていたからのぉ。だいたいこの村にはナイト輝石の精錬の方法など伝わっておらん。ハース鉱山がどんな形でナイト輝石を扱っているのかさえ、わしらは知らんのだ。」
「それについては私からも説明しよう。」
バルディスさんが口を開いた。
「ランスじいさんの言うとおり、この村には精錬の方法は伝わっておらぬ。ただ、精錬された後の鉱石を使って武器防具を作る手法は伝わっている。だから私も、エルバール王国から入ってくるナイト輝石をあてにしているのだ。いかに結界で守られているとはいえ、それはこの大陸のわずかな範囲でのこと。エルバール王国との交易では外海に出なければならぬ。あなた方もここまで来られる間に、海のモンスター達に出会っただろう。あのような恐ろしいモンスターを相手にせねばならぬがゆえに、交易船にはたくさんの戦士や魔術師が乗り込むが、中には命を落とした者もいる。だがナイト輝石で武器防具を作れるようになってからは、だいぶ被害が減った。サクリフィアにとっても、ナイト輝石は福音であったのだ。」
そう言えば、カフィールの恋人も交易船で命を落としたと聞いたのは、ついこの間のことだ。
「わかりました。へんなことを聞いてすみませんでした。では続きを話します。」
随分と失礼なことを聞いたものだと自分でも思う。疑問に思うとどうしても確認しなければ気がすまない、わが身の好奇心の強さが恨めしい。気を取り直して、私は続きを話した。そしていよいよ『サクリフィアの錫杖』を見つけたときのことを話し、その部屋の奇妙さを説明すると、村長も、ランスおじいさんも、グィドー老人達までも暗い表情になった。そんな中で、壁のレリーフの説明を聞いたリーネだけがうれしそうだ。
「まあ、そのレリーフはそんなところにあったのね。私も見てみたいなあ。」
「建物全体がすばらしい文化遺産だよ。あんなに美しいものを誰も見られないなんて、もったいないよ。」
「いつか、誰でも気軽に見に行けるようにしたいものだがなあ・・・。さて、剣士殿、その部屋の話だが、もう少し詳しく話してくれんかね。」
村長に促され、私はその部屋の中の奇妙さと、私達なりにその正体を探った考察も含めて話した。
「・・・この杖があるのに・・・?」
メイアラは驚いた顔で聞き返した。
「そうです。部屋の中の家具調度、窓、カーテン、何一つ時の流れにさらされたものはありませんでしたよ。」
「なるほど・・・。やはり言い伝えは真実だと言うことか・・・。」
村長が神妙な面持ちで言った。
「神殿の内部について、何か言い伝えがあるんですか?」
「言い伝えと言うより、この村には当時のことを記録した本とかもあるんじゃないんですか?」
カインが尋ねた。
「確かにそういう記録は存在するのだが、残念ながらここにはない。そういった記録は全て、エルバール王国へと持ち出されておる。おそらく文書館と言うところに保管されておるだろう。」
「文書館へ・・・。それではその言い伝えを記録したものはここには何もないんですか?」
「ああ、ろくな本はない。ただ、写本は幾冊か残っておるのだが、それも持ち出された本全部の話ではないし、長い間のうちに破れたり燃えたりしてなくなってしまったものも多数だ。そういった内容の書物については、かえってあの神話の作者の家のほうが、充実しておると思う。」
「そうじゃのぉ。家にある写本だってその元になった本もまた写本だったからのぉ。情けない話だが、この村には、自分達の歴史を一望できるような記録は何も残されておらんのじゃ。」
「だがそれも仕方ないことなのかもしれん。サクリフィアの城下町は広大で美しかったと聞く。ところが聖戦でそれらが跡形もなく破壊され、燃えてしまった。誰もが絶望し、生きる気力を失っておったのだ。記録などあったところで誰も顧みることなどしなかっただろう。ここに置いておいては貴重な書物が失われることを懸念した、おそらくはディード卿あたりが、新天地へ書物を持ち出すことを提案したのかもしれんなあ。」
ディード卿とは確か、文書館の初代管理官だ。ベルロッド様の仲間の冒険者で魔法に精通していた人物で、文書館は彼の提案で設立されたと聞く。
「まあそういうわけで、神殿の中の様子についてはわしらも言い伝えと言う形でしか知らん。あやふやな知識で先入観を持たせてしまうのはよくないということで、内部の情報については特にあんた方に話さなかったのだ。そこは理解してくれんかね。」
「では今なら、その言い伝えについて話していただけるんですか?」
「うむ。それはきちんと話しておくべきだろう。だが、あくまでも言い伝えだ。真実かどうかとなると、わしらにもはっきりとしたことはわからぬのだ。」
「それは構いません。お願いします。」
村長が話してくれたところによると、神殿の中には『時のない部屋』があると言われていたそうだ。その部屋に、サクリフィアの民は入ってはならぬと言い伝えられてきた。そして、そこに宝物を収めたと言う話も聞いたそうなのだが、その宝物が何をさすのかはわからなかったと言う。そして『導師』についても、『ファルシオンに選ばれし者を導く、類い希なる賢者』という者が神殿に存在すると言う話は伝わっているが、サクリフィア建国の時から剣は失われたままだったので、その存在を知る者はほとんどいないだろうと言うことだった。
「つまり、その『宝物』が、この杖と言うことになるんですね。」
「おそらくはそうだろう。確かに宝物は宝物だが、サクリフィアの民にとっては大きな罪の証でもある・・・。この話は、ファルシオンの使い手に関わる話でもあるのだ。だからどうせ話すなら最初からきちんと話したいと考えておるのだが、どうかね。」
「村長よ、その前に、さっきのでかい生き物の話も聞いたほうがいいんじゃないかのぉ。この話の先にあれが出てくるんじゃないのかね?」
ランスおじいさんが言った。私達としてもセントハースの言葉は早く伝えたい。
「はい、そちらを先に話させてください。」
「なんと・・・。」
「そ・・・そんなことが・・・。」
『時のない部屋』に置かれていた『サクリフィアの錫杖』を手に入れた後、私達が神殿の屋上で出会ったセントハースの話を聞いて、誰もが言葉を失い、青ざめた。
「つまり・・・、もう一度聖戦が起きるかどうか、その鍵を握っているのは飛竜エル・バールで、そしてその説得が出来るのはあんた方だけだと、こういうことなのかね。」
村長が震える声で尋ねた。
「・・・そういうことになるんだと思います。」
「うーん・・・・。」
村長は大きくため息をついて、椅子に寄りかかった。そしてしばらく思案した後・・・
「よし、では約束どおり、わしらが知っているファルシオンについて話そう。今の話を聞く限り、エル・バールは今日明日にも目覚めて行動を起こすと言うことではないようだ。ならばここは浮き足立たず、剣士殿にわれらが知っていることをきちんと話して、エル・バールと対等に渡り合えるだけの知識を身に着けていただこうではないかと思うのだが、みんな、異存はないかね?」
「それがいいだろう。今ここでわしらが騒いだところで事態が変わるわけでもなさそうだ。明日も明後日もうまい飯が食えるよう、ファルシオンの使い手殿達にがんばってもらわねばならん。グィドーよ、あんたはどうだ?それに他の2人も。いいかげんその、眉間の皺を伸ばしてもいいんじゃないかのぉ?」
ランスおじいさんがグィドー老人達に向かって言った。
「・・・眉間の皺は今さら伸びんわ。だが、お前さんの言うことももっともだ。いかに老い先短いこの身とて、ドラゴンに踏み潰されたくはないからな。」
「決まりだな。ではファルシオンの使い手殿よ。まずは、これを読んでくれんかね。」
村長は古ぼけたノートのようなものを私の前に差し出した。ノートと言ってもとても薄く、どちらかというとノートから破った紙を何枚か重ねた、そんなふうに見える。
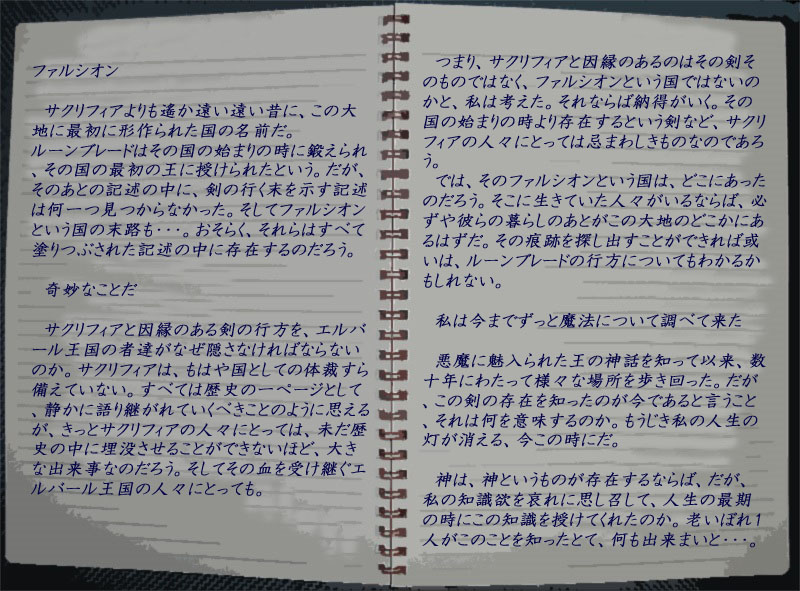
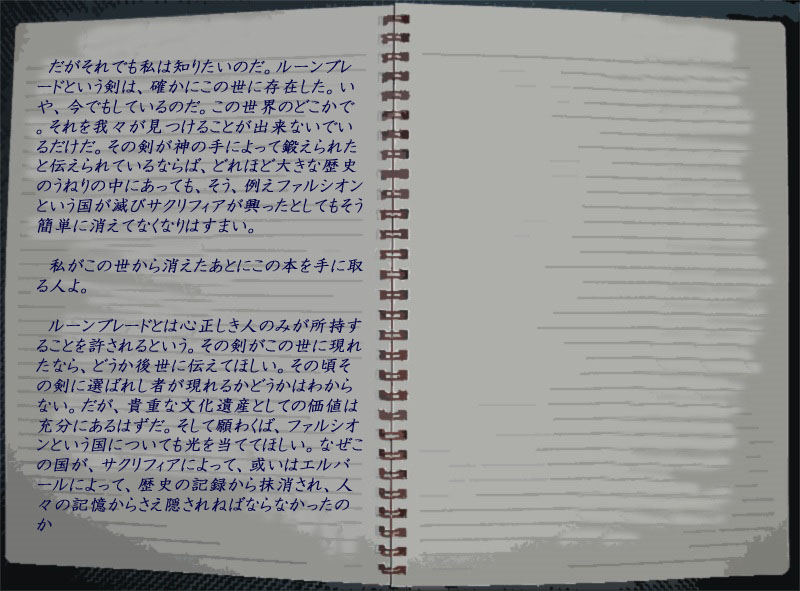
「・・・これはもしかして、私達があの神話の作者の家で見つけた、ノートの続きですか・・・。」
「そうだ。もう少し正確に言うならば、ノートの続きを写したものだがね。読みにくくてすまんが勘弁してくれ。本物はあの家の本棚に置かれている。もっともあれだけの量だ。すぐに探し出すのはきわめて困難だろうが。」
村長の声は冷静だが、それは何もかも流れに任せるしかないと、肚を括った者の強さのような気がする。
「しかし・・・なんて言うかピンと来ない話だなあ。この大地に最初に国が出来た時に作られたのがお前の剣だなんて・・・。」
カインは首をかしげている。
「そんなに古いものには見えないんだけどなあ・・・。」
私は腰の剣を外してテーブルに置いた。サクリフィアでさえ千年王国だと言われているのに、その前に、しかもこの大地に最初に出来た国の王様が持っていたなんて・・・。
「さて、そのノートを読んでもらったところで、次はこの村に伝わっている剣についての話だが・・・うーん・・・どこから話したらいいものか。」
村長が腕を組んで考え込んだ。
「始めから話して終わりまできたらやめればいいわい。」
「こらランスじい!まぜっかえすな。まったくもう・・・。」
2人の掛け合いがなんだかおかしかった。こんなやりとりは聞き慣れているのか、メイアラとリーネはくすくすと笑っている。渋い顔でいるのはグィドー老人達。バルディスさんは笑いをこらえているのか下を向いている。
「まず、そのノートに書かれているように、その剣はこの大地に最初に造られた国の最初の王に授けられた、この世に1本しかないものだ。その剣には何かの文字が記されているだろう?」
モルダナさんから預かっている指輪に書かれている文字と同じような文字なので、多分ルーン文字だろうという程度しかわからないと、正直に答えた。村長達はその指輪にも興味を示し、おそらくそれはそれで、伝説の秘宝とも言うべきものかも知れないと言っていた。そんな大事なものを、『フロリア様のためだから』と新人剣士の試験のために提供してくれているのだ。少なくともライザーさんまで、あの試験を受けた王国剣士はちゃんと指輪をモルダナさんに返すことが出来たのだから、私も無事に戻って必ず返さなければならない。でないと、あの試験自体が続いていかないことになる。
「これは我らも言い伝えでしか聞いたことのない話だが、その剣に記されているルーン文字は、『この剣を制する者、大地を統べる者なり』と読むのだそうだ。」
「・・・へ?」
最初に声をあげたのはカインだった。私はと言えば、あまりに突拍子もない話で、脳の理解が追いつかない。
「大地を統べるって・・・どういうことですか?」
やっとのことで声を絞り出した。
『大地を統べる』
言葉としては理解出来るのに、なぜこの場に、私の剣についての話に、そんな言葉が出てくるのか・・・。多分私は呆けたような顔をしていたのだろう。村長が私に、いたわるような視線を向けた。
「この大地に最初に興った国の名は、この柄に彫り込まれているファルシオンと言う銘から取ったのだと言われている。これは我々がいつも使っている文字と同じものだから、問題なく読めただろう。」
「はい・・・それは読めましたけど・・・え?もしかして、今私達が使っている文字や言葉は、その最初に造られた国で使われ始めてからずっと変わっていないということですか。」
村長がうなずいた。
「そういうことになるな。だが、その日常使われている言葉や文字とは別に、神聖文字とも言うべき文字が存在したそうなのだ。それがルーン文字と言って、ファルシオンという国の神殿にはその文字で書かれた祝福の言葉や祈りの言葉がレリーフに彫られていた・・・。あんた方が見た時には、おそらく今使われている文字で贖罪の言葉などが彫られていたのではないかね。」
「あ、あのレリーフが・・・」
ウィローが声をあげた。
「あのレリーフには元々そのルーン文字で何か彫られていたんですか・・・。」
「そう聞いておる。だが、サクリフィアは神々に見放され、都は無残に破壊された。絶望した人々は唯一無傷で残った宮殿に向かい、壁のレリーフを全て取り外した。そして、せめて少しでも自分達の罪が赦されるようにと、我らの言葉で反省と贖罪の言葉を彫ったレリーフを掲げたのだ。さて、ここまではいわばおさらいのようなものだ。では、この国に伝わる、その剣にまつわる話をしてあげよう。」
そう言って、村長が語り出した話は驚くべきものだった・・・。