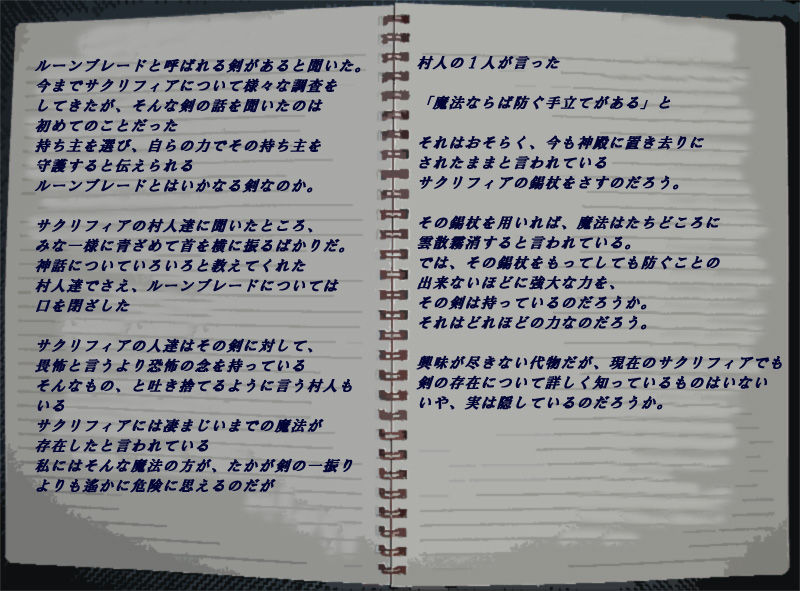
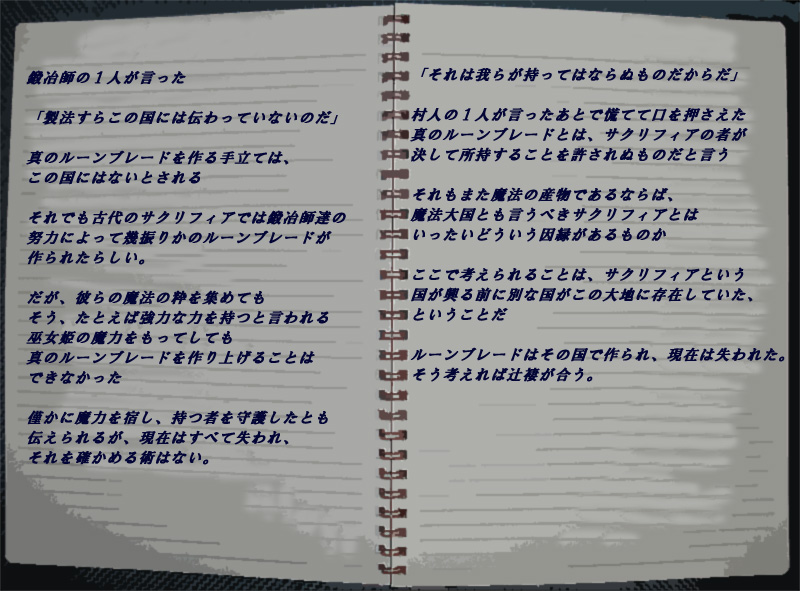
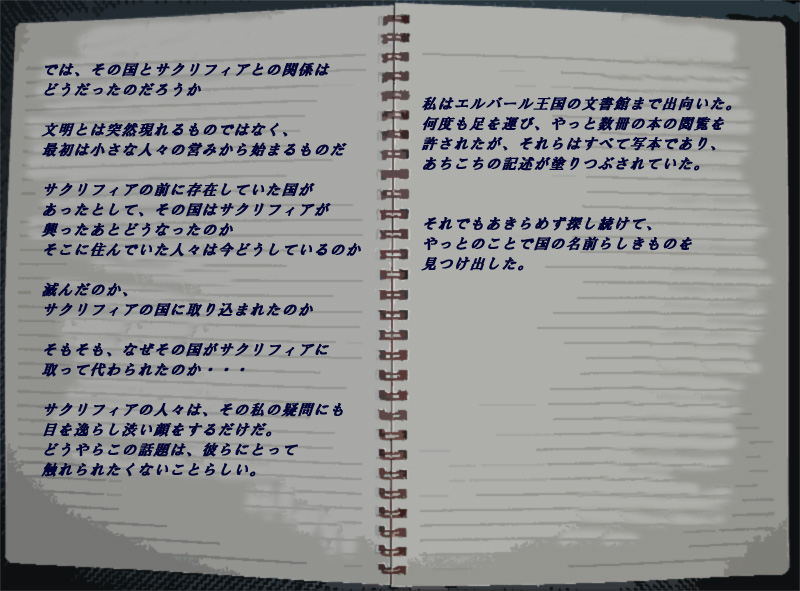
「ずいぶんと思わせぶりな切れ方だな。」
カインがうーんと唸りながら言った。
「ウィロー、これだけか?他に続きが書いてあるようなものはないのか?」
ウィローがうなずいた。
「本の間に挟んであったのよ。挟んであった本は、普通の歴史の本だったわ。サクリフィアからエルバール王国に変わるまでのお話ね。」
「どれどれ、見せて。」
リーネが覗き込んで、「ああ」と言う顔をした。
「これは、私もずいぶん前に見つけたことがある紙よ。その時はカフィール姉様と一緒だったから、その紙に書かれている続きを教えてもらったことがあると思うわ。ただ、よく覚えていないのよね。」
「つまり、君はこの剣についてよく知ってるって言うわけだね。」
「少なくとも、持ち主のあなたよりはね。おかしな話だけど。」
「でもどう言うことなのかって聞いても、答えてはくれないんだね。」
リーネは困ったように笑ってうなずいた。
「そうね。それに、その話を聞いたのはずっと昔のことよ。カフィール姉様が、『あなたはこの村の人間なんだから、知らなければならないわね』って言って、教えてくれたの。だからそんなに詳しいことを知っているわけではないわ。村長だってメイアラ姉様だって、どこまで知っているかはわからないわ。もしも確実に知っている人がいるとすれば、きっと神様ね。」
リーネはクラトと似たようなことを言った。だが実際にそうなのかもしれない。この剣を神が鍛えた云々は別にして、エルバール王国の前に栄えていたサクリフィアの、さらに前に存在したはずの国のことなんて、この大地の創世からずっと見守ってくれている神様以外に確実に知っている人なんていないんじゃないだろうか。
「でもわかったことが一つだけあるな。この剣の存在は、エルバール王国でも掴んでいるってことさ。」
カインが言った。
「それもそうか・・・。と言うことは、フロリア様やレイナック殿も知ってるってことだね。」
「だと思うなあ。文書館に入れるのは、基本的に国王陛下と文書管理官だ。この剣がエルバール王国にとってどういう存在なのかはわからないけど、そんなのがあった、くらいのことは、歴史の勉強でレイナック殿あたりが教えてそうな気がするぞ。」
「そうだね。レイナック殿なら、そう言う国の成り立ちとか、歴史の授業に力を入れそうだね。」
「ウィローさん、その紙は元の場所に戻しておいてほしいの。ただ、内容を写すのは問題ないと思うわよ。」
「そうね・・・。それじゃ私はこれを書き写しておくわ。」
ウィローは部屋の真ん中に置かれているテーブルを使って、自分の持っているノートにメモの中身を写し始めた。カインと私はまた部屋の中をいろいろと探し始めた。
「しかし妙な話だな・・・。」
カインがぽつりと呟いた。
「なにが?」
「フロリア様を元に戻したくて、必死に手がかりを求めてあちこち歩いたのに、なぜかお前の剣の謎にどんどん近づいていく気がするからさ。」
「カイン・・・。」
カインは振り向いてくすりと笑った。
「別にお前に文句を言いたいわけじゃないよ。案外、お前の剣が俺の行く先に導いてくれてるのかもしれないしな。」
確かに妙な話だ。魔法のことを知りたくてあちこち歩き回っていくたびに、私の剣の謎が立ちはだかる。この剣は、さっきのメモに書かれているように、本当に『魔法の産物』なのだろうか。そりゃ・・・持ち主を守るとか、力量を見定めるとか、とても説明の付かない力を秘めているのは確かだ。あの島での稲妻だって、とても考えられないような強大な力を、この剣が持っていることの証だ。だが・・・
(なんで・・・こんな剣を父さんが・・・)
疑問はいつでもそこに戻る。なぜ父がこんな不思議な、いや、不思議と言うより奇妙としか言いようのない剣を持っていたのか。
「ふぁ〜〜〜、そろそろ限界だな・・・。」
最初に根を上げたのはカインだった。元々本を読むのは苦手なのに、こんなに大量の本を前にして、片っ端から調べるなんて長続きするわけがない。クロンファンラの王立図書館での時だって、ほんの数冊見るのにも、脂汗を流しながら必死だったのだから。
「それじゃ戻りましょうか?ここの本を1日で全部読破するなんてとてもとても無理だもの。本気でそうしたいなら、うちの村にしばらく滞在しないと無理よ。」
リーネが笑った。
「そうだね・・・。魔法の本も手に入れたし、村に戻ろうか。そろそろ会議の結果も出ただろうし。ウィロー、そっちはどう?写し終わった?」
「ええ、今ちょうど終わったところ。あとは、戻って村長さん達の話を聞いたほうが良さそうね。」
私達は腰を上げ、船に戻った。村に戻って村長の家を訪ねると、村長とメイアラ、それにランスおじいさんの他に、数人の村人が待っていた。顔ぶれを見ると、そんなに若者がいない。おそらくこの人達が村の運営に携わる人達なのだろう。
「どうだったかね。何か興味のあるものは見つかったのかな?」
村長は笑顔で迎えてくれたが、今初めて会う他の人達は、そうとう私達を警戒しているのが、手に取るようにわかる。
「村長、あの魔法の本だけど、クロービスさんに渡したわ。別にいいわよね?」
「おお、あれか。うむ、構わんだろう。」
2人の会話から察するに、私が持ち出してきた呪文の本は、村長もその存在を認識している。そして、おそらくは私が見つけるだろうと言うことも、どうやらある程度は推測していたらしい。
「さて座ってくれんかね。お客人方に、会議の結果を伝えねばならん。」
「村長、わしがさっき言うたことを忘れるでないぞ。」
ランスおじいさんより少し年配かなと思われる、老人が鋭い目で私を見ながら言った。この老人が私に対してよい感情を持っていないのは明らかだ。
「そう急くものではないぞ。あんたの言い分はこれから伝える。客人を立たせたまま話をするわけにはいかん。」
「ふん、これだけ若けりゃ立ちっぱなしでも疲れんじゃろうて。さっきの話はわしだけが言うておるわけではない。他の者も同じ考えだと言うことを忘れんでもらおうか。」
「わかっておると言うに。まずは話し合いの席についてもらわなければならんのだ。サクリフィアの運営会議の委員は礼儀知らずだなどと、エルバール王国で評判になるのは困るのでな。」
少し強い口調の村長に、老人はグッと言葉に詰まって黙り込んだ。だが、老人とその周りにいる2人ほどの別な老人達は、先ほどからずっと私を睨みつけている。
「グィドー老、あんたは相変わらずだのぉ。歳をとって少しは丸くなったと思うていたが、ちっとも変わっておらん。」
いささか呆れた口調でそう言ったのはランスおじいさんだ。隣でリーネが肩をすくめているところを見ると、この老人の態度は特に私にだけ向けられているものではないらしい。
「悪かったな、ランス。わしの性格は昔から同じだ。」
その後もグィドー老人はブツブツと口の中で何か言いながらムスッとしている。この人を囲む老人達もサクリフィアの人間ならば、人の心の中をある程度感じ取ることは出来るはずだ。ということは、私もカインもウィローも、この村に対して邪な思いを何一つ抱いてないことだってすぐにわかっただろう。にもかかわらずここまであからさまに嫌悪感を表すのには、何か理由があるはずだ。その時
−−−くそ!ちっとも読めん!!−−−
不意に頭の中に響いた言葉に、危うく振り返るところだった。この声は、おそらく今のグィドー老人だ。私の心を読もうとしているのか?
(なるほど・・・わかってきたぞ・・・。)
彼らは、多分私の心の中を探りたいのだ。もちろん、近づいただけである程度は感じ取ることが出来るのだろうが、おそらくこの老人は私の心の中を読もうとしている。だが私の心の中には、今ではすっかり作ることに慣れた『防壁』が張り巡らされている。その壁を破ることは出来ない。だから彼らは私を怒らせようとしているのではないか。怒って感情を爆発させればその時だけは防壁が揺らぐ。私の心の中を覗く絶好のチャンスだ。だがちっとも怒った気配がないものだから、イライラしているのだ。
(知らない振りをするしかないかなあ・・・。)
今の心の叫びまで聞かせるつもりだったかどうかはともかく、ここで私が彼らの企みに気づいたと宣言したところで話し合いの場が険悪になるだけだ。
(いまのところは、黙っておくしかないか・・・。)
「三つ子の魂百までか。なるほど、確かにお前さんの性格は昔っから変わらんな。村長、とにかく話を進めようじゃないか。そっちの赤毛の剣士殿がしびれを切らしているようだからな。」
カインのイライラは先ほどから私も感じていた。この家に入ったときから、すぐにでも村長に許可をもらった神殿に行くつもりでいたのに、妙な方向に話が逸れてしまって、そうとう我慢していたらしい。
「え、い、いや、俺は別に・・・。」
「カイン、ここの人達には、少しの気の揺らぎもわかるんだよ。」
「あ、そ、そうだったな・・・。」
カインは少し焦り気味にうなずいて黙ったが、本当に焦ったのは先ほどのグィドー老人達だろう。ビリッと気が震え、私の背中に刺すような視線が降り注がれているのが手に取るようにわかる。自分達が考えていることを私に悟られてしまったと、彼らには今の私の言葉でわかったと思う。
「困ったもんだな・・・。お客人、村の者の非礼は私が詫びよう。とにかくあんた方にはさっきの会議の結果を伝えねばならん。座ってくれんか。」
私達は部屋の中央に置かれたソファに座った。私達が座ったのを確認して、村長も座った。村長は一つ小さなため息をついて、グィドー老人達をぐるっと見渡した。
「この通りだ。もちろんこれはあんたのせいではないが、あんたがその剣の主である限り、この村の者にとってはあんたは招かれざる客なのだ。その理由なんだが、あんたはこの剣について何も知らないという。だがさっきのグィドー老の話は、それが信じられないという話なんだよ。」
「でも私は本当に知らないんです。」
「うむ、あんたが嘘をついておらんことは私にはわかる。もちろんグィドー老達にもわかるはずなのだが、なんと言ってもあんたは剣の主だ。我々が感じ取ることの出来ない部分に、知識を隠しているのではないかと、まあグィドー達の言い分はそう言うことなのさ。」
「でもそう言われても・・・。」
「・・・でまあ、その・・・ここからがさっきの会議で決まったことなのだが・・・。」
村長はかなり言いにくそうだ。まさか、私の剣のことが原因で、神殿に入る許可をもらえないのだろうか・・・。
「まったくばかばかしい。村長や私の言葉を信じられないなら、いっそ王家の血筋も巫女姫も、こんなしきたりやめてしまえばいいのよ!」
メイアラは明らかに怒っている。国王の末裔である村長も、昔ながらのしきたりに則って選ばれる巫女姫も、もはや無条件でその言葉を受け入れてもらえるわけではないと言うことか・・・。
「そうはいかん。これは伝統だ。だが、お前がやめたければ別な誰かを選ぶだけのことだ。昔のようにそう簡単に還俗できなかった頃よりは、ずいぶんと緩やかになったものだと思うがな。」
グィドー老が言った。確かに、昔のような強力な力を巫女姫が操っていた時代からすれば、今の時代は掟もなくのんびりとしたものなのだろう。だからそのかわり自分達の言い分も聞けと、こう言うことらしい。
「まあ、やめてしまえば確かにそれまでだが、村を率いていく誰かしらは必要だ。それより話の続きをしたいのだが、グィドー老よ、いいかね?」
「ああ、早いところ結論を言ってやればいいのではないか。この、自称剣の持ち主にな。」
グィドー老人は、まだ私を怒らせようという試みを続けているらしい。村長がわざとらしく咳払いをして、小さくため息をついた。
「グィドー老、頼むからそう言う挑発的な物言いはやめてくれ。」
「ふん!仕方あるまい。わしはこの若者の持っている剣がルーンブレードの、いや、ここでは正式名称で呼ぼうではないか。ファルシオンかどうかなど知らんのだからな。そもそも見たことすらないのだ。」
「ふむ・・・まあそれも一理ある。見たのは今のところ私とメイアラだけだからな。ではグィドー老、この若者に剣を抜いて見せてもらえばいいのではないか?」
「そして全員ばっさりか?わしはこんな年寄りだが、まだ死にたくはないからそれは遠慮するわい。」
「グィドーじいさん!いい加減にして!今のは剣の持ち主だけじゃない、剣を実際に見たと言っている私達に対する侮辱でもあるわ!」
メイアラが怒り心頭で怒鳴ったので、さすがのグィドー老人も言いすぎたと思ったらしい。腹は立つが、ここで私が怒ってしまってはますます話がこじれてしまう。私は腹の底にグッと力を入れてこらえ、腰の剣をここでも剣帯ごと外してテーブルの上に置いた。
「どうぞ。ご覧になるならご自由に抜いてください。」
メイアラの剣幕におされながらも、今度こそ私を怒らせることに成功したかと期待したグィドー老人は、私の顔を見て少しぎょっとしたように目を見開いた。
「これでもまだ不安なら、私は離れていますから、どうぞ。」
私はテーブルから離れて、部屋の隅に移動した。おそらくこの老人は、誰が何をどう言っても私に対する態度を変えることはない。この剣を見たところでそれは変わらないと思う。だが、とにかく存分に見てもらうのがいい。そもそも隠すことなど何もない。カインとウィローは不安そうではあったが、2人とも黙ったままテーブルから離れて私の隣に立った。
「すまんな、お客人。グィドー老よ、これで文句はあるまい。好きなように剣を鞘から抜くといい。剣の持ち主もお仲間の剣士殿も、それに、デール卿のご息女も剣のまわりにはおらぬぞ。」
村長は、『デール卿のご息女』の部分を少しだけ強調したようだ。その言葉にグィドー老人は小さく舌打ちをしながら、恐る恐るテーブルに近づいて剣の鞘に手をかけた。
(ウィローのお父さんのことは、この老人も認めてるってことか・・・。)
単身サクリフィアにやって来て、威嚇の攻撃をすべて退け、ついに村長に会って話を聞き出すなど、何とも大胆な人だったのだろう。
グィドー老人は剣を鞘から抜こうとしたようだが、手が震えている。サクリフィアの者が決して持つことを許されぬと、あの神話の作者の家から見つかったメモには書かれていた。それを手にとって見ようというのだから、確かにそれは勇気のいることかも知れない。ましてや、これが本当に千年の昔に姿を消したと言い伝えられる伝説の剣かもしれないとなればなおさらか・・・。
剣のまわりに、グィドー老人の後ろにいた老人達が集まって囲んだ。1人が鞘を持ち、グィドー老人に抜けと促している。剣は鞘からするりと抜けて、パッと光り輝いた。
「おお!」
剣の周りにいた老人達は一斉に驚きの声をあげて後ずさった。
「こ・・・これは・・・。」
呆然としていた老人達だが、いきなりグィドー老人が眉をつり上げてきょろきょろと辺りを見回した。村長を見、メイアラを見、私達を睨みすえたが・・・
「誰も魔法なんて使っていないわよ。グィドーじいさん達がそんな子供だましの手に引っかかるなんて、いくら私達だって思っていないわ。」
メイアラの言葉にグィドー老人は舌打ちをし、忌々しそうな一瞥を私達にくれて剣を鞘に戻した。
「ふん!もうよい!村長、さっきの続きだ。この連中に説明してやるといい!」
吐き捨てるようにそう言って、自分達の座っていた椅子に座り直した。この老人は、先ほどの剣の光が誰かの魔法によって操られた光ではないかと疑ったらしい。だから村長とメイアラを見て、最後に私達を睨みつけたのだろう。もちろん村長もメイアラも魔法なんて何も使っていないはずだし、私達に至っては誰1人魔法など使えない。
−−−ふん!本当に本物のようではないか・・・!まさか今になってこんなものが現れるなど・・・くそっ!−−−
グィドー老人の心の中の悪態まで聞こえてくる。こんなことまで聞かなくてもいいのだが、聞こえてくるものはなんとも仕方がない。私が聞いていると知っているのかいないのか、口をへの字に曲げて椅子に座ったグィドー老人の顔からは読み取れない。
「ふぅ・・・やっと話が進められるな。だが、助かったよ。あんたの話のおかげで、私もお客人に話す覚悟が出来た。感謝せんといかんな。」
村長の言葉に、グィドー老人はフンと鼻を鳴らし、そっぽを向いた。彼を取り囲む老人達は少しそわそわしている。なんとなくだが、他の2人はもう私を疑ってはいないように見えた。剣の輝きを自分の目で見て納得したのかもしれない。だがグィドー老人の手前、それを言い出せないでいる、そんな風に見える。私達は席に戻り、座り直した。剣はそのままテーブルの上に置いておいた。ここにいる分には使う必要がない。
「さて、だいぶ話が逸れてしまったが、お客人、昨日私はあんた方に約束した。今日の会議のあと、サクリフィアの錫杖のことと、その剣の由来について、話すとな。」
「そう伺ってます。今日の会議の結果はどうなったんでしょう?」
「それでその・・・さっき私が言い渋っていたのには、わけがある。今のグィドー老の態度から見て、一部の村の者達があんたを歓迎していないのはわかってくれたと思うのだが、グィドー老達は、あんたが本当に伝説の剣の主であると言うことにも疑っておる。」
「つまり、私が剣に認められたと言うことが信用出来ないと、そう言うことなんですね。」
「ああ、まあその、うむ、そういうことだ。」
村長は言いにくそうだ。もしこれがすべて嘘だったならばどんなにいいか。私がそんなことを考えていることまでは、この人達にはわからないのだろう。
「だが、もしも本物ならば、剣の由来を話すのはある意味我らの義務でもあるわけだ。いかに因縁がある剣とは言っても、せっかくこの村を頼ってこられたのだし、今朝も言ったように、今さらその剣1本で何が変わると言うこともないからな。それでだな、グィドー老が言うには、その話をするために、あんた方に条件を出したいと言うことなのだ。」
「・・・条件?」
「うむ、つまり、そっちの赤毛の剣士殿、あんたはサクリフィアの錫杖を借り受けたいと言っておったな?」
「はい。」
カインは即座にきっぱりと答えた。
「それについては許可すると言うことなのだ。それで、その、錫杖を手に入れたら、それをまずはこの村に持ってきてもらいたい。その時にファルシオンの由来についても話してやろうと、そう言うことなのだよ。神殿は今では危険な場所だ。あんた方を試すことになるのは心苦しいが、会議で決まった以上は、その条件を呑んでもらわないことには私も剣の話が出来ぬのだ。」
どうやら、この村ではサクリフィアの錫杖を借りたいという話よりも、私の剣のことの方をかなり重要視しているようだ。
「それなら、俺達でサクリフィアの錫杖をとってきます。この村に持ってくれば、こいつの剣の話も聞けて、錫杖は俺達に貸していただけるんですね?」
カインはかなり乗り気だ。錫杖が借りられて私の剣のこともわかるとなれば、それはもうカインにとっては願ってもないことだからだ。私はと言えば、ここまでもったいつけられてしまうと、なんだか剣のことを聞くのが怖くなってくる。だがそう言うわけにも行かないらしい。今私がここで逃げ腰になれば、グィドー老達は私が偽物だと断じるだろう。私自身が構わなくとも、そのことでいろいろと親切にしてくれた村長、メイアラ、ランスおじいさんまでも窮地に立たせることになるかもしれない。それだけは避けたい。
「それは約束する。危険を冒して錫杖を取りに行ってもらったのに、いきなりお払い箱ではサクリフィアの民としての信義に悖る。サクリフィアの錫杖とて、この村にとっては宝だ。財宝という意味ではなく、この村が今まで守ってきたものの1つだからと言う意味でだが。その宝をこの村に取り戻してくれたなら、今度こそ村を挙げて、あんたの力を認め、あんた方全員を客人として歓待しよう。」
「わかりました。それなら行ってきます。おいクロービス、ここまで言われたら引き下がれないぞ。俺は行く。」
「私だって行くよ。では村長、明日にでも出発しても構いませんね?」
「うむ、早いほうがいいだろうが、さすがにこれからではすぐに暗くなる。今日はゆっくり休みなさい。今のうちに鍵を渡しておこう。」
村長はあらかじめ準備してあったらしい大きな鍵を渡してくれた。それが神殿の扉に取り付けてある錠前の鍵だと言うことだった。私達は礼を言って村長の家をあとにした。この村ともしばらくの間お別れだ。そんなに長い間いたわけでもないのに、何となく名残惜しく感じる。町の中をしばらく散策したあと、私達はもう一度武器と防具の点検をしようと、前に訪れた武器屋に行ってみた。中に入ろうとしたとき・・・
「・・・やはりあの客人の持つ剣はファルシオンだったのだな。」
武器屋の主人の声だ。
「そうよ。あなたが修理したそうね。」
・・・これは・・・メイアラの声だ。
「まさか生きているうちに伝説の剣に出会えるとは思っていなかったからな。実に光栄なことだ。」
「あなたはあの剣が本物だって信じてるの?」
「お前は信じていないのか?夢にまで見た剣じゃないか。」
「そうね・・・。夢と同じ・・・いいえ、それ以上の輝きだったわ。あれが偽物だなんてあり得ないでしょうね・・・。」
「それならいいじゃないか。何でそんなに暗い顔をしているんだ?まさかあの剣が、本当に伝説通りにこの村に復讐をしにやってきたとでも思っているのか?」
復讐・・・?どういうことだろう・・・。
「そんなんじゃないわよ。ないけど・・・。」
「俺としては歓迎したいね。おかげでお前が巫女姫などやらなくてもよくなるかもしれないからな。」
「よく言うわ。心にもないことを。」
「俺の気持はずっと変わらないさ。お前が信じないだけだ。」
「カフィール姉様のことはどう思っているの?」
「それは昔のことだ。」
私達は顔を見合わせた。どうしてこうも立ち聞きとしか言えないような状況になってしまうんだろう。
(なんかすごくまずいところに来たような気がするぞ・・・。このまま帰るか?)
カインがささやいた。
(でも武器は見てほしいし・・・。)
(こんな時は、声を掛けてしまえばいいのよ・・・。)
言うなりウィローは大きな声で叫んだ。
「こんにちはぁ!いらっしゃるかしら!!」
このまま聞いていては盗み聞きになってしまう。カインも私も心の底からホッとした。が・・・きっと私達が話を聞いていたことは、もう知られてしまっただろう。ウィローが叫んだ瞬間、店の中の空気がビリッと震えたのがはっきりとわかった。
「いらっしゃい。今日は武器の調整かな?」
武器屋の主人は何事もなかったかのように私達に声をかけた。メイアラも黙って一歩後ろに下がった。だが、二人の間に漂う気まずい空気がはっきりと感じられて、どうにも落ち着かない。
「さすがにあなたは大人よね。今の話をこの人達に聞かれたことなんて、何とも思ってないんだわ。」
巫女姫として、いつも凛とした態度を崩さないメイアラだが、今はすねたような口調になっている。先ほどの会話から、この2人の微妙な関係は何となくわかったのだが、こんな時はどうすればいいものか。
「お客が来れば商売をするのが商売人というものだ。話を聞かれているのに気づかなかったのは失態だが、起きたことは仕方あるまい。」
「起きたことは仕方ない。でもだからって止めもしないのはひどいじゃないの!?」
メイアラはだだっ子のように武器屋の主人を責める。止めもしないというのは、もしかしたらカフィールがこの村を出ることを止めなかったといっているのだろうか。武器屋の主人は小さくため息をついた。
「今はその話をしているときではないだろう。この人達は村のお客人でもあるのだ。あとでまた話し合おう。」
「話すことなんてないわ。私は帰る。」
メイアラは武器屋を飛び出すように出ていった。
「・・・すまなかったな。見苦しいところを見せてしまった・・・。」
「いえ、私達もすぐに入ればよかったんですが・・・。」
「いや、あなた方は悪くない。気にしないでくれ。それより、メイアラからあなた達がどこへ向かうのか聞いた。また飛んでもない場所に行くことになったものだが、あなた達ならばそう簡単にやられはすまい。私に出来ることはないが、武器と防具の点検はさせてもらえないか。」
「私達の方こそお願いします。」
武器屋の主人は店先で仕事を始めた。私達は置かれている椅子に座って、その様子を眺めていた。
「あなた達はカフィールの紹介で来られたのだな。」
手元から目を離さないまま、主人が誰にともなく話しかけてきた。
「ええ、サクリフィアから来たという吟遊詩人の噂を聞いて、会いに行ったんです。」
「カフィールとメイアラとクラトは、とても仲のいい姉弟だった。・・・あんなことさえなければ、今でもカフィールはここにいたかもしれないのに・・・。」
「あんなこと?」
主人がぎくりとして手を止めた。うっかり言い過ぎたと思ったらしい。
「いや、失礼した。こちらの話だ。」
「あんなことって何よ。」
いきなり入口から聞こえた声に振り向くと、そこには何とメイアラが立っていた。
「今のは私に聞かせるためよね?何なのあんなことって!」
「お前に聞かせるためなんかじゃない。今は仕事中だ。お前がそこにいたのも気づかなかったんだ。」
この2人の会話が芝居でないとすれば、この村の人々が持つ力というものがおぼろげながら見えてきた。人の心を感じ取ることについてはどうやら誰でも出来るらしいが、力の強さについてはかなりばらつきがあるようだ。たとえば今のように、何か他のことに集中している場合、他の人の思念は感じ取れなくなるらしい。ましてや私の心に張り巡らされている『防壁』を打ち破ってまでその中を感じ取ることは、今のところ誰にも出来ない・・・。巫女姫の座についているメイアラでさえこうなのだということは、呪文の力とこの力とは関係がないのだろうか・・・。
「ええ、あなたにとって私はその程度よね。ずっとここに立っていても気配にすら気づかない程度のね。」
私達がここにいるというのに、メイアラは引こうとしない。よほど腹に据えかねているのか、わざと私達に聞かせて武器屋の主人を追い込むつもりなのか・・・。
(つまりそれほどこの人を好きなんだってことだろうけど・・・困ったなあ・・・。)
下手に口を挟むわけにも行かないし、黙っているしかない。
「・・・仕方ないな・・・。メイアラ、お前はどうしたいんだ?お前にいくら責められたところで、返せる答は同じだ。だから、どうすればお前が満足するのか、それを聞かせてくれ。ここには客人もいるが、お前はこの人達にも話を聞かせるつもりでここにいるのだろう。」
武器屋の主人はあきらめたようにそう言ってため息をついた。
「お客人方、すまんな。おかしな話を聞かせてしまうことになるが、少しつきあってやってくれないか。私もこのままでは集中して仕事が出来ん。」
「それは構いませんけど・・・そもそも俺達は何があったのかも全然わからないんですよ。それでいいんですか?」
カインもすっかり困った顔になっている。
「簡単なことよ。この人はね、カフィール姉様の恋人だったのよ。でも姉様が巫女姫になりたくなくてこの村を出るって言ったとき、黙っていたの。結婚すればよかったんだわ。そうすれば姉様はこの村にいたって巫女姫になんてならなくてよかったのに。」
「仕方あるまい。カフィールだって好きでもない男と結婚したくはないだろう。」
「まだ嘘をつくの!?それでごまかしたつもり!?」
「ごまかしてなんかないさ。もちろん嘘だってついていない。」
武器屋の主人はどこまでも冷静だ。苛立っているのはメイアラのほう・・・。何となく見えてきた気がする。メイアラはこの武器屋の主人を好きだが、相手はカフィールの恋人だ。カフィールが村を出ることになった時、2人が結婚してくれれば自分もあきらめきれたのに、そう言う展開にはならず、大好きな姉は村を出てしまい、好きな人をあきらめるチャンスも失ってしまった。だからメイアラはイライラしているんだろう。でもさっきからの話を聞く限りでは、この武器屋の主人はメイアラを好きなような気がするんだけど・・・
(私の勘じゃあてにならないからなあ・・・)
迂闊なことを言って話をこじらせるわけにも行かない。
「私が怒っているのはね、カフィール姉様が村を出ることになった時のことを、自分のせいじゃないみたいな言い方をするからよ。」
「あの時俺が出来ることなどなかったさ。カフィールは俺のことなど何とも思っちゃいなかった。・・・なあメイアラ、お前、アガレスを覚えているか?」
「どうしてはぐらかすの!?何でそこにアガレスの話が出てくるのよ!」
「関係あるから話を出したんだ。お前は覚えているのか?」
メイアラはグッと唇を噛み締め、うなずいた。
「忘れるわけないわ。あれほど悔しい思いをしたことはなかったもの・・・。」
武器屋の主人はぽかんとしている私達に向かってすまなそうに微笑んだ。
「アガレスというのは、この村の・・・そうだな、エルバール王国で言うなら風水術師と言うところか。特にものすごい術を使うわけではない。この村では神術師と呼んでいるが、風水術と似たような、火を呼んだり風を起こしたり、そんな術を使う。その男が6年ほど前、交易船に乗っていて命を落としたのだ。」
「交易船で?」
「うむ、この大陸の運河に入れば、あとは村の者達が使っている船着場まではずっと結界が張ってある。村の交易船はエルバール王国へ村の特産品などを積んでいき、向こうから必要な生活物資やゴールドを手に入れて戻ってくるのだが、運河を出てからの海のモンスターは手強い。そのために船には何人もの神術師や戦士が乗り込むのだ。アガレスはその中の1人として、何度もエルバール王国とこの村とを往復していた、ベテランの神術師だった。だが、6年前のあの日、海から躍り上がってきたモンスターの足が、運悪くアガレスの目に命中したそうだ。船の手すり近くにいたアガレスは視界を奪われてそのまま海に落ち、モンスター達をやっとのことで撃退して引き揚げたときには・・・見るも無残な姿になっていた・・・。」
「サクリフィアにはかつて魔法王国だったというプライドがあるわ。そのサクリフィアの交易船が万に一つもモンスターによって沈没させられることなどないようにと、戦士も神術師も、みんな必死で訓練しているのよ。でも、本当に・・・本当に運が悪いとしか言いようがなかった。そんなことで命を落とす羽目になったアガレスが気の毒で・・・。」
メイアラの瞳から涙が一筋こぼれ落ちた。
「でもどうしてここでアガレスの話が出てくるの?まだはぐらかすつもりなの?」
メイアラがまた武器屋の主人を睨んだ。
「そうではない。カフィールが村を出たのは、アガレスがいなくなったからだと言いたかっただけだ。」
「・・・どういうこと・・・?」
「お前は気づかなかったのか?カフィールとアガレスは、ずっと前から恋人同士だったんだ。もはや俺など、入り込む隙もないほどにな。」
「・・・う、嘘!アガレスがもういないと思って、そんな嘘を!?」
武器屋の主人は少しだけ悲しげな瞳でメイアラを見た。
「俺は死人を盾にして嘘をつくような男だと、お前は本気でそう思ってるのか?」
「だ、だって・・・そんな、そんな話、私は知らない!」
「お前に言えるはずがないだろう。お前の気持をカフィールが知らなかったとでも思うのか?お前は俺とカフィールさえ結びついてくれれば、自分の気持にけりをつけてしまえる、それしか考えていなかっただろう。カフィールと俺の仲は、もうずっと昔に壊れていたんだ。その後カフィールはアガレスと愛し合っていた。だがそのアガレスが死んで、カフィールの力の強さに目をつけた村の長老達が巫女姫として立たないかと持ちかけてきたんだ。カフィールにとって、今さら村に留まって巫女姫になどなりたくなかっただろう。以前から興味を持っていた吟遊詩人として身を立てようと思っても無理はないし、それを俺が止められるはずがない。しかもその時、俺が愛していたのはカフィールではなくてお前だったんだからな。」
メイアラは唇を噛み締め、店を飛び出した。今度は本当に通りを駆けていった。
「ふう・・・まったく、お客人に妙な話を聞かせることになってしまってすまなかった。だが、おかげでやっと正面から話をすることが出来たよ。」
「うーん、2人ともお互いを好きだったなら、そんなに考えなくてもまとまりそうだけど、難しいんだなあ・・・。」
カインが首をかしげた。カインの愛する人はとてもとても手の届かない場所にいる。でも武器屋の主人もメイアラも、同じ村に住んでいて実は何一つ障害がない。なのにどうしてうまく行かないものか。
「私は何となくわかる気がするわ。」
店の入口から、メイアラの駆け去った方向を見ていたウィローが独り言のように言った。
「メイアラさんは、好きな人がずっと自分のお姉さんの恋人だと思いこんでいたのよ。お姉さんがいなくなった隙に横取りするみたいな気がして、いやだったんじゃない?だから自分の気持をあきらめるチャンスを探していたのに、ちっともうまく行かなくて悩んでいたんだと思うわよ。それにカフィールさんだって、『自分はこの人ともう何でもないからさあどうぞ』なんて、妹さんに言うわけに行かないでしょ?」
「でもそんなところで意地はってたら、一生後悔しそうだけどな。」
「一生後悔するかどうかはわからないけど、素直になったらいいのになって私も思うわ。ね?クロービス。」
ウィローは私に向かって『あなたもそう思うわよね?』と言いたそうな顔で微笑んだ。お互い意地を張って素直になれなかったあの10日間を思い出す。私は2度とあんな思いはしたくない。それはウィローも同じだ。
「なるほど、やはりこう言うことは、若いお嬢さんのほうが洞察力があるな。私としても、メイアラが素直になってくれるとありがたいんだがね。さてと、話も終わったことだし、本格的に武器と防具の点検をさせてもらおう。」
武器屋の主人は、前にもまして丁寧に私達の武器と防具を点検してくれた。とても複雑な気持でいることはわかったが、私達に出来ることは何もない。礼を言って武器屋をあとにした。
「はぁ・・・思いもかけない展開になっちゃったなあ。」
カインがため息をついた。
「でも私達に出来ることなんてないよ。とにかく今は、明日からの旅に向かって準備することだけを考えよう。サクリフィアの錫杖は、ここまで持って帰って来なきゃ借りられないんだから。」
「そうだな。まずはそっちだ。フロリア様さえもとに戻ってくれれば、みんな解決するんだからな。」
明るく言ってはいるが、カインの心は不安に包まれている。そしてウィローも、例え今すぐにフロリア様が元に戻ったとしても、私達の旅がまだまだ終われないのではないかと、何となくだが思っているらしい。確かに、フロリア様が元に戻っても私の剣の謎は解けるわけではない。サクリフィアの錫杖をここに持って来ることで聞き出せる情報がどんなものか、それもまったく見当がつかないのだから。
「よし、次は宿酒場だな。」
先ほどの話では、この村にも武装して戦うことを生業とする戦士はいるらしい。ある程度モンスターとの戦闘経験がある戦士がいれば話を聞きたいんだけど・・・。
私達は昨日入った宿酒場に足を向けた。昼時を少し過ぎていたせいか、今日はそれほど混んではいない。そしてぐるっと見渡すと、やはり何人かの武装した戦士が食事をしている。
「はぁ・・・やっと落ち着いたよ。」
さっきからカインは溜息ばかりついている。
「会ったばかりの赤の他人である私達に聞かせてまで話をしようとしていたんだから、きっとメイアラさんはよほどつらかったのね・・・。」
ウィローはメイアラに少し同情しているらしい。
「あの武器屋の主人もかなりいい人みたいだよね。お互いが相手を思いやろうとしているのに、うまくかみ合わないんだからつらいんじゃないかなあ。」
ウィローと私の諍いも、結局はそう言うことだ。あの時私達にたりなかったのは言葉。そしてメイアラも武器屋の主人も、やはり思ったことを素直に言葉に出せずに苦しんでいる。
「でもさっきはちゃんと話が出来たって言ってたし、俺達にはこれ以上どうしようもないよ。それより、今日も戦士らしい人達がいるみたいだから、何か聞いてみないか?」
「そうだなあ・・・。でもなんて聞けばいいかなあ。」
「ねえ、雑貨屋さんで聞いたレジェンドストーンていう石のことでも聞いてみる?」
「そうだなあ・・・。相手がどんな奴かわからないのにウィローに聞きに行かせるわけに行かないから、クロービス、お前聞いてきてくれよ。」
「うーん、私でうまく行くかなあ・・・。」
「ここの人達が人の心に敏感だって言うなら、大丈夫だよ。」
「それならカインだっていいじゃないか。」
「俺だと近づいただけで警戒されそうだしな。」
体格のいいカインよりも、細身に見える私のほうが警戒されにくいと言う考えは理解出来るのだが・・・そんな心配は必要なかったらしい。戦士達の一団からひとりが立ち上がり、私達に近づいて来た。
「よお、あんたら昨日も来てたよな。この村じゃ見かけない顔だが、どこから来たんだい?」
特に嫌みな感じはしない。言葉通り、見かけない顔に興味を持った、と言うだけらしい。
「エルバール王国からです。」
ここは嘘をつかない方がいい気がした。
「エルバール!?ずいぶんとまた遠くから来たもんだな。まさか陸路を来たんじゃないよな?」
「まさか。教えてくれる人がいたので、船で来たんです。」
「教えてくれる人?へえ、そんな親切な奴がいるのか。」
「元船乗りの人ですから。」
「なるほどな。交易船にでも乗ってたのか。しかしエルバール王国では、この国はとっくに滅びたことになってるんじゃないのか?よくこんなところまで来たもんだな。あんたら冒険家かい?」
「そう言うわけでもないんですが・・・。」
どこまで正直に言ったものかと考えあぐねて、私はさっきウィローが言っていたハース聖石のことを聞いてみた。かなり腕の立つ者しか取りに行けないと言われているが、本当のところはどうなんだと。
「なんだ、あんたらトレジャーハンターか。ま、エルバール王国からこんなところまで来る奴らなんてその程度か・・・。レジェンドストーンは、そうだなあ・・・。神殿の北側に広がる山脈の麓でたまに拾えるな。」
「掘り出すわけではないんですね。」
「その辺に落ちてるぜ。ただし、そのあたりには獰猛なモンスターがわんさかいるから、拾うのが先か死ぬのが先か、なんてこともあるがな。」
物騒な話だが、戦士はそのわりにけろりとしている。かなり腕は立つのだろう。身のこなしも隙がない。
「そんなに獰猛なのがいるんですか。」
「ああ、神殿まわりはすごいぜ。獰猛と言っても、薄気味悪い奴らも多いんだがな。」
「薄気味悪い・・・?おばけみたいなのとか?」
「うーん・・・おばけなら正体がわかる分まだいいがなあ・・・。ま、行くなら気をつけるこった。」
戦士はそのモンスターを思い出したのか、少し身震いして自分の席に戻っていった。
「・・・薄気味悪いモンスターか・・・。」
獰猛で攻撃力が高いというなら、それなりに対処出来る自信はある。だが薄気味悪いとはいったい・・・。
「あの人も、どう表現していいのかわからないような顔だったわよね。」
ウィローが首をかしげながら言った。
「そうだな・・・。ま、あとで村長にでも聞いて見るか。」
そこに食事が運ばれてきた。