「出せそうかな。」
「うーん・・・どうかなあ・・・。このまわりのぼろ船が邪魔してるんだよな・・・。」
カインがため息をついた。舳先は北に向けてある。つまり、この船が私達のあと誰も乗って動かしてはいないと言うことだ。だが、まわりにびっしりと置かれている古い船のおかげで、中途半端に引っかかったような状態になっていた。これは確実に、この船を港から出さないための、王国軍の・・・あるいはフロリア様の仕業・・・。
「難しいが・・・よし、とにかく乗り込んで、甲板から確かめよう。ここからでは船の状態がよくわからないからな。」
私達は船に乗り込んだ。渡し板なんてもちろんないので、まわりの船を足場にしてやっとのことで甲板によじ登った。
「まったく・・・意地の悪い置き方をするなあ・・・。」
甲板から見渡した限りでは、船そのものに損傷はなさそうだ。まずは出航の準備をしようと、3人で帆を張り、舫綱を外した。問題はここからだ。まわりの船が邪魔をしているので、このままでは港を出ることが出来ない。
「さてどうするかな・・・。無理をすれば出せないことはないんだが、船体に傷がついたりしたら航海に支障が出るしなあ・・・。」
カインが腕を組んだままうーんと唸って、ウィローも私もつられて黙り込んでしまった。さてこの船を無事に港から出すためにはどうすればいいのか・・・。
(あれ・・・?)
3人とも黙り込んだせいなのか、どこかで微かに、弓弦を引き絞る音がしたのを私の耳が捉えた。
「みんな伏せて!」
とっさに3人で甲板に身を伏せた。私達がたった今いた場所を矢が数本飛んでいき、マストに突き刺さった。
「待ち伏せか!?」
カインが身を伏せたまま叫んだ。と同時に、『ばか野郎!外しやがって!』『けっ!さっさと乗り込んだ方が早かったんだ!』などの声が聞こえてきた。この状態では確認できないが、おそらくは王国軍の兵士達だろう。
「くそ!・・まずいな。ここで捕まったりしたら今までの苦労が水の泡だ!」
「とにかく乗り込まれる前に船を出そう!」
「出すってどうするんだよ!?」
そんな話をしている間に、焦げ臭い匂いが立ちこめてきた。まさか!?
「あ、あいつら・・・火矢を打ち込む気か!?」
「そんな!帆を燃やされたりしたらもう出航できないわ!」
「カイン!とにかく舵を取って!ウィロー、君はその辺に掴まっていて!私が帆に風が当たるように『慈雨』を唱えるから、少しでも動き出したら港をなんとしても出よう!」
「わかった!」
カインは身を伏せたまま舵の場所まで素早く移動した。舵のある場所は船の後方なので、立ち上がってのこのこ歩いたりすればそれこそ火矢の格好の的になる。私達を足止めするためにそんなものを用意すると言うことは、もはやフロリア様は『不殺』など何とも思ってないと考えていいのだろうから、出来る限り危険を冒さずにすむようにしなければならない。ウィローも同じように身を伏せたまま、掴まれそうな場所に移動している。この船の甲板はそれほど広くない。掴まれる場所はすぐ見つかるだろう。あとは私の仕事だ。
(立ち上がって矢を射かけてから呪文を唱えるか・・・。)
一瞬でいい、敵をひるませられれば、そこに必ず勝機が生まれる。
(おいクロービス!こっちは準備が出来だぞ!)
押し殺したカインの声を合図に、私は立ち上がり、威嚇の矢を1本、船のまわりに集まった兵士達の真ん中に射た。思った通り、兵士達が驚いて飛び退き、注意が私達から一瞬だけそれた。
(今だ!)
私はあらん限りの『気』を集め、『慈雨』を唱えた。『天地共鳴』に勝るとも劣らない凄まじい雨風が吹きはじめ、王国軍の兵士達は突然の嵐に驚いている。『熱いじゃねぇか!』『ばか野郎気をつけろ!』そんな怒鳴り声が聞こえてきた。弓兵達が驚いて、つがえていた火矢を取り落としてしまったらしい。火は彼らの足下に燃え広がり、大混乱だ。そして私達を乗せた船の帆は大風を受けてパンパンに膨らみ、まわりに係留されているぼろ船の間をぎしぎしと音をたてながら、海に向かって動き出した。
「今だ!船を出すぞ!」
カインが立ち上がり、思いきり港の外に向けて舵を切った。船体が隣のぼろ船に当たってバリバリと音を立てる。ぼろ船の船体には大きな亀裂が入って、ぐらりと傾き沈みはじめた。そのおかげで、船の進路がさっきよりは広くなった。
「よし、これなら行ける!」
私はもう一度『慈雨』を唱えた。再び起きた雨風は私達の乗った船をさらに沖合に押し出し、王国軍の兵士達をさらに浮き足立たせた。『ひるむな!風水術になど惑わされるな!』将校らしい声だけがむなしく響き、もう火矢も普通の矢も、飛んでは来ない。私達の船は、無事港から出ることに成功した。
「ふう・・・なんとかなったか・・・。」
カインが額の汗を拭った。
「あの人達やけどしたりしてないかしら・・・。」
ウィローは王国軍の兵士達を心配している。
「大丈夫だよ。あれだけ雨が降れば、いまごろみんなびしょ濡れなんじゃないかな。」
「それもそうね。」
ウィローが笑った。『慈雨』と言う風水術は、風と共に雨を呼び込む。おかげで私達も全員びしょ濡れだった。
「ま、寄せ集めの兵士じゃあれが限界だろうな。将校らしい奴は威勢がよかったみたいだが、他の連中はもう戦闘どころか逃げ出す寸前だったみたいだし。」
カインが港を指さした。ぼろ船の船体に遮られてよくは見えないが、誰一人、こちらに向かって弓を構えたりしている者はいないようだ。船を出して追いかけてくる可能性はあるが、港があの状態では使える船を探し出して、出帆出来る状態にまでするほうが大変だろう。
「船らしい船もなかったみたいだしね。多分海からの出入りを制限するために、ハース城との行き来をするための船以外にろくな船を置いてないんじゃないかなあ。」
「元々王室が持っている船ってそんなに数はないからな。ま、そのおかげで助かったわけだけどな。」
「でもこの船が壊されていなくてよかったわ。」
「多分私達をおびき寄せるためのエサにするつもりだったんじゃないかな。この船があればいずれ私達はここに来て、船を出そうとする。でもまわりにあれだけのぼろ船が押し込められていれば、そう簡単に出せないから、もたついているところを一網打尽!・・・という筋書きだったのかも知れないよ。」
「ははは、ということは、敵はお前の風水術のことまでは計算に入れてなかったと言うことになるな。」
「風を起こすために風水術を使うって事くらいは考えたと思うけど、元々『慈雨』ってのは雨と風を一緒に起こして、水滴の鋭さで敵を痛めつけるって言う呪文なんだよ。だから、あんなにすごい風が吹くとまでは思っていなかったのかも知れないよ。」
この時ウィローが大きなくしゃみをしたので、とにかく着替えをしようと順番を決めて船室を使った。そして先ほど隣の船に体当たりをしたことで、こちらの船に損傷がないかどうかも見てみたが、甲板から見る限りではたいした損傷はないようだ。もう後戻りは出来ない。とにかく前に進む以外に、道は残されていないのだ。
「まずはこのあたりにあるはずの島か。そこに着いたら、改めて船の点検をしてみよう。」
カインが地図を広げながら言った。
「・・・うーん・・・・。これはちょっと厄介だな・・・。俺達が今いるのは、だいたいこのあたりだ。」
「ここ!?」
カインが地図上で指さした場所を見て、驚いてしまった。私の唱えた『慈雨』は、思ったよりもかなり強力だったらしい。いつの間にか、目指す島よりも遙か沖合まで来てしまっていたのだ。
「こんなところまで・・・。」
ウィローがため息をついた。
「ここから戻るしかないけど、うっかり東の港に近づくとまた騒ぎになりそうだからなあ。この島の、東側に船を着けられそうな場所があるかどうか、行ってみるしかないだろうな・・・。東がだめなら北側か。南や西の方に桟橋がないことを祈るよ。東の港からでは丸見えの位置だからな。」
幸い、まだ昼にはなっていない。これから戻れば、島にたどり着くことは可能だと思えた。
「それなら準備をしないとね。」
「そうだな。とにかく行って、話を聞いてみないことには、お前の剣のことも・・・あれ?」
カインが首をかしげた。
「なに?」
「おいクロービス、クロンファンラを出る前に、お前、シャーリーの手紙を受け取ってたよな?」
「あ・・・そういえば・・・。」
すっかり忘れていたその手紙は、私の荷物の中に押し込めてあった。小さくたたんであったせいか、濡れてはいない。
「でも私達が灯台守の詰所にいるって、よくわかったわね。」
ウィローが少し薄気味悪そうに言った。確かに、私達が訪ねてくるかも知れないとか言うことなら、ある程度予測することが出来るとしても、宿ではなく詰所にいることまでわかると言うのは、あんまり気分のいいものではない。
「そうだなあ・・・。あの子供も、宿に行ってからじゃなくて直接詰所に来たみたいだったしなあ・・・。」
いくら小さな時から一座の下働きをしているとは言っても、あの小さな子供にそこまでの機転が利くとは思えない。詰所に行けと言うのは、間違いなくシャーリーの指示だと思っていいだろう。
「ま、考えても仕方ない。もしかしたら、何か巫女姫の力みたいなのを持っているのかもしれないけど、シャーリーは俺達にそういうことは何一つ話してくれなかったんだ。それより、今のうちにその手紙を見てみないか?シャーリーがお前の剣のことで何か考えがあるらしいのはわかったけど、その手紙に何か手がかりが書かれているのかどうか、それを確かめてから島に行ったほうがいいような気がするんだが・・・。」
「そうだね。先に確認しておこう。」
カインの言うとおりだ。シャーリーは自分の持っている情報を隠すことで、私達を試そうとしたようなものだ。そして私達はその手に乗らなかった。もう彼女のことを考えるのはやめよう。ウィローが不安げに見ている。私は荷物から取りだしたあの手紙を開けた。
「なんて書いてあるんだ?」
カインとウィローが私の右と左から覗き込んだ。
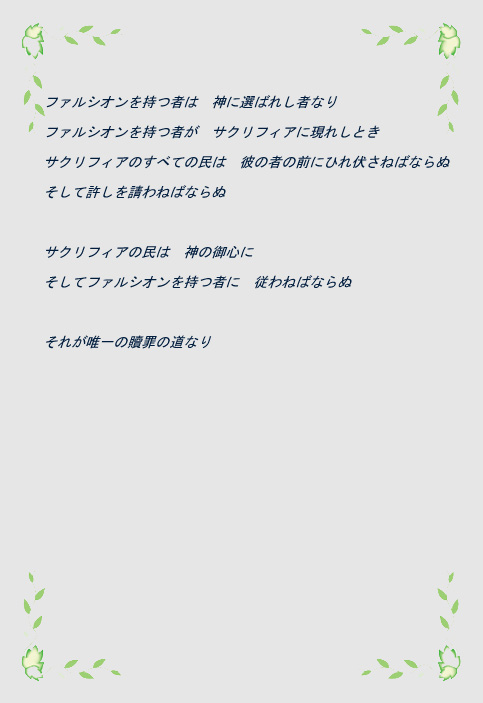
「・・・なんだこりゃ?」
カインが首をかしげた。ウィローが不安げに眉根を寄せた。便せんの中に書かれているのはまったく妙な言葉だ。ファルシオンを持つ者が神に選ばれし者?駆け出しの作家が書くような安直な冒険小説の展開じゃあるまいし、これは一体何の冗談なんだろう。
「うーん・・・。」
またカインが考え込んでしまった。
「なんだか冒険小説の古文書みたいね。」
ウィローが言った。確かにその通りだと思った。こう言うものが発見されると、主人公が何か特別な人物だったことがわかって、いろいろと展開があるとか・・・。
(ばかばかしい。そんな物語みたいな話、そうそう現実に起きるもんか。)
「これ、シャーリーさんが書いたんじゃないの?私達を混乱させるために。」
ウィローがまた怒ったような声で言った。
「うーん・・・。確かにその可能性がないとは言い切れないけど、どうかなあ・・・。この手紙、けっこう古いぞ?」
カインの言うとおり、手紙の書かれている便せんは古く、インクも乾ききっている。試しに水を一滴便せんに落として見たのだが、インクは滲まず、水がガラス玉のように紙の上を滑って転がり、床に落ちた。
「いくら火にかざして乾かしても、ここまで乾燥させるのは無理だろうなあ。この手紙が古いものだって事だけは、間違いなさそうだ。まあ中身の真偽のほどはなんとも言えないがな。」
「つまり、シャーリーが作った物語の一節ってわけではなさそうだってことか・・・。」
もしもこれが、単にこの手紙を読んだと言うだけだったなら、『ばかばかしい』と言って捨ててしまったかも知れない。だが、私はシャーリーの心の声を聞いた。切羽詰まった、怯えたような声を。そして、この手紙はそのシャーリーがわざわざ私宛に届けさせたものだ。だとすれば・・・。
「この手紙が古いってことは、シャーリーがおばあさんから聞いたって言う、巫女姫の話の、何かしら裏付けになるようなものなのかも知れないってことか・・・。ますます、その島に住んでいるって言う語り部に会う必要がありそうだ。とにかく行こう。ここでうんうん唸っていても、何もわからないぞ。」
顔をこわばらせたまま、カインが立ち上がった。言いようのない不安が、私達の間に広がっていくようだった。だが、カインの言うとおりなのだ。私達は前に進まなければならない。そうしなければこの謎は解けそうにない。ウィローと私も腰を上げ、風向きを確認して、船乗り達が使っていた地図の書込を頼りに、進み始めた。
「・・・あれかなあ。」
陽が高く昇り、もう少し過ぎれば少しずつ西側に傾き始めるだろうと思われる頃、行く手に島影が見えた。大陸ほど大きくはない。地図によると、このあたりには他に大きな島もなかった。私達が探している島と見て間違いなさそうだ。
「東側に近づいてみようか。船を着けられそうならそのまま降りてみようよ。そんなに大きな島じゃなさそうだし、王国軍がいるとは考えにくいからね。」
「そうだな。サクリフィアの村を出たって人が住んでいるとしても、1人や2人のために王国軍が出張ってきているとも思えないしな。」
私達は速度を落とし、少しずつ島に近づいていった。
「あれ・・・桟橋じゃない?」
ウィローが眼を細めて指さした。島の東側、ちょうど大陸側にある東の港からは視認できないギリギリのあたりに、桟橋が設えられている。船も何艘か見えた。
「東側に桟橋があるってことは、この島にも漁をする人達とかがいるのかな。」
「うーん・・・漁をして生活しているなら、もう少し船がたくさんあってもいいような気がするなあ。」
桟橋に係留されているのは片手で数えられる程度だ。この船は島の人達が大陸と行き来するためのものだと思う。
「ま、気にしないことにするか。こちら側に桟橋があるのは好都合だ。ただ、島の人達を驚かせないようにだけ、慎重に近づいてみようぜ。」
「騒ぎ立てられたりしても困るからね。」
「そういうこと。少なくとも、今の俺達はエルバール王国に楯突く反逆者だからな。」
少しだけ、カインの声に自嘲的な響きがこもったが、あえて私は黙っていた。そんな言葉を口にしたくないのは私も同じだが、今の私達の立場は間違いなくその通りなのだから・・・。
「よし、このあたりでいいか。」
近づいてみると、桟橋は思ったよりも広かった。ある程度大きな船を着けられるようになっている。私達は出来るだけ東の港から見えないような場所に船を着けて、島に降り立った。浜辺から続く道の両側には、畑が広がっている。島自体はそんなに大きくないが、このあたりの気候は穏やかだ。作物はきっとよく育つだろう。
「のどかだな。」
「そうだね。人もそこそこ住んでいるみたいだ。」
私達は、サクリフィアの末裔達がひっそりと住んでいるものと思いこんでいたが、この島には他にも住人がけっこうな数いるらしい。遠くには家もずいぶん並んでいるし、畑はきれいに手入れされていて、そこかしこに農作業をする人達の姿も見える。なるほど、これが無人島だったりしたら『サクリフィアの末裔が住んでいる』などという噂はすぐに人の口の端に上っただろうが、元々住んでいる人々の中に紛れ込むことが出来れば、穏やかに暮らしていくことが出来る。私達は途中の畑から出てきた農夫に、この島に語り部がいるのかどうかと聞いてみた。思った通り、農夫は胡散臭そうに私達を見て、黙っている。そこで私達は、この島に知識の豊富な語り部がいるという噂を聞いたので、ぜひ話を聞きたいのだと言ってみた。農夫の顔から警戒の表情が少し薄れた。おそらくここに住む人々は、その語り部達とうまくやっているのだ。もしかしたら、彼らがあまり外にその存在を知られたくないと思っていることまで、知っているのかも知れない。農夫は『あまり人に言わないでくれよ』と前置きして、その語り部の家を教えてくれた。
「語り部ってのはたいてい吟遊詩人と一緒に歩いて興行をするもんだが、ここの語り部は1人なのかい?」
カインが農夫に尋ねた。農夫はあまりよく知らない、と言って、足早に立ち去ってしまった。
「・・・つまり何人かいるってことか。全員サクリフィアの末裔なのかな。」
「とにかく行ってみよう。場所を教えてもらえただけでも収穫だよ。」
畑の中の道を歩いて行くと、前方に人影が見える。何と語り部の身につける黒いローブを着ていた。
「私を訪ねてこられたのはあなた方ですかな。」
見た感じは40代前半か、もう少し若いくらいだろうか・・・。だが、その風貌に似合わぬ、落ち着いた口調と物腰に、なんだか奇妙な違和感を覚えた。語り部というのは、あまり若くても信用されないという話は聞いたことがある。だからみんな黒いローブに身を包み、つば広の帽子を目深にかぶって伏し目がちに話す。そうすることで、落ち着いた印象を人に与えようとするのだ。だからこの語り部が、こんな風な話し方をするのは別におかしくも何ともないのだが、では、何に引っかかるのだろう。
「あなたがこの島に住む語り部ですか?」
カインが尋ねた。声が少しうわずっている。「早く話を聞きたくてたまらない」のを必死でこらえているのだ。そんなカインに、語り部はにっこりと笑った。
「いかにも、私がこの島に住む語り部です。先ほど島の人から、わざわざ私を訪ねてこられたと聞きましたので、お待ちしておりました。こんな道ばたでもなんですから、もう少し開けた場所に参りましょう。いつも私が島の人々に物語を聞かせている場所です。なに、ここからはそう遠くはありません。」
とても感じのいい語り部だ。この人ならば、いろいろと話を聞かせてくれるかも知れないとは思うのだが・・・
(島の人に聞いたのはついさっきなのに、なんでこんなに調子よく現れたんだろう・・・。)
語り部だって普通に外は歩くだろうから、たまたま出会って話を聞いて、と言う偶然が起きたと考えたっていい。しかしどうしても、何かが引っかかる。語り部と出会った時から、なにかこう、もやもやしたものが私の心の中に気づかれた『防壁』のまわりを漂っているのだ。さっき感じた違和感も、このもやもやしたもののせいなんだろうと思う。私の気のせいなんだろうか。船を下りる前に見たシャーリーの手紙のせいで、少し警戒しすぎているのか・・・。
≪・・・何者だ・・・。我らがここにいることをかぎつけるとは・・・・≫
「え?」
突然頭の中に響いた声に、思わず声を漏らした。
「ん?何だよクロービス。」
カインが不思議そうに振り向く。
「あ・・・い、いや、何でもないよ。」
どきんと心臓が波打つ。今の声は何だ?どこから聞こえてきた?いや、どう考えても、これはこの語り部の声だ。
「あなたはこの島にずっと暮らしているのですか?」
さりげなく聞いてみた。さっき頭の中に響いた声が、『空耳』ではないのかと思えるほど、語り部の笑顔は穏やかで、殺気は感じられない。
「もう10年ほどになりますでしょうか・・・。我ら語り部は、基本的に定住はせずにあちこちを巡って歩いては様々な物語を詠い、時には奏で、糊口を凌いでおります。ところがこの島に訪れたとき、島の人達が歓迎してくださいましてねぇ。それ以来ここに住んで、時折大陸に出掛けては興行をしております。さて着きました。ここが、いつも私が興行している場所でございますが・・・此度はいかような物語をお聞かせしましょうか。」
その広場は、島のおそらくは中央に位置しているのだろう。それほど広くない島の中にあって、どこを見渡しても畑や家が見えるだけで、海がよく見えない。そして、その畑にも家のまわりにも、人がいない。浜辺からこの語り部に出会うまで、畑には農作業をする人達が何人かいたはずだが、彼らはどこに行ってしまったのだろう・・・。
(おかしいな・・・。この語り部、何か企んでるのか?)
さっきの声といい、この語り部が見た目通りでないことは確かだ。では、この男は何者だ?本物の語り部なのだろうか。カインがガゼルさんから聞いた話では、『サクリフィアから来たらしい語り部』と言うことだった。東の港まで送ってもらうためのキャンプの時も同じ事を聞いたっけ。
『サクリフィアから来た語り部があの島に住んでいるってのは、商業地区の店屋の店主達から聞いた話なんだ。あの島の住人が買物に来てそんな話をしてたって言ってたから、ほとんどの店主達はホラ話だと思ってるようだがな。だが、そこまで堂々と『サクリフィアから来た』と言っているってことは、逆にそう言っていれば誰も信じないだろうという計算があるのかも知れん。』
なるほど、それはうまい考えかも知れないと思ったものだ。この語り部が本当にサクリフィアから来たのなら、それは出来れば隠したいことなんじゃないかと思うが、隠そうとすればするほど人の口の端に上る確率は高くなる。ならば逆に言いふらしてしまえば、みんなホラ話だと思って相手にしなくなる・・・。
(私達みたいに、どうしてもサクリフィアの人に会おうなんて考える人間がいなければ・・・ね・・・。)
「そうだな・・・。それじゃ、サクリフィアについての興味深い物語とか、伝承なんかは知らないかな?」
カインは何も気づいてないらしい。普段ならばおかしいなと思うのかも知れないが、今のカインはとにかく語り部から話を聞き出したくてたまらない。そんなカインの心を知ってか知らずか、語り部の表情は穏やかなままだ。
「サクリフィアでございますか・・・。未だ謎多き神秘の国でございますな・・・。で、あなた方は何を知りたいのでございましょう?サクリフィアの歴史、人々、産業、一口に「興味深い」と申しましても、実に様々な事柄がございます。」
「そうか・・・うーん・・・。」
カインが悩んでいる。この語り部は、別に私達を煙に巻こうという気はないらしい。時折苛立ちが見え隠れするところを見ると、さっさと私達を追い返してしまおうと考えている、そのためには私達が納得しそうな内容の話を聞かせたいと思っているようだ。ということは、この語り部はやはり何かを隠してるのだろうか。だとすれば、『サクリフィアから来た』というのは真実で、それを『ホラ話』ではなく『真実』として世間に知られるのが困るということだろうか。先ほどから島の住人が見当たらない理由も、もしかしたら島の人々は全員この語り部の協力者で、物陰に隠れてこちらを伺っているのかも知れない。そして、私達が語り部に対して不審な動きを見せた場合、一斉に躍り出て私達を押さえつけようとしているのかも知れない。
(・・・・・・・・・・・・・。)
少しだけ、あたりに意識を集中してみた。やはりここから見えない場所に、何人かの気配を感じる。私達に対して敵意は持っていないようだが、なんとなく、語り部に対して不安げな感情がゆらゆらと揺れながら漂っているようだ。きっと心配しているのだろう。
「あなたがこの島に住み始める前は、あちこちを旅して歩いていたのですか?」
思いきって聞いてみた。
「はい、北大陸も南大陸も、小さな町や村まで歩いておりました。」
「語り部は一般的に、吟遊詩人と一緒に興行をするものですが、あなたはこちらにお一人で?」
「おいおい、新聞の取材じゃないんだぜ?この人のことをそんなに根掘り葉掘り聞くのは失礼じゃないか?」
カインが苦笑いしながら言った。自分でもさっき同じ事を疑問に思っていたはずなのに、今のカインはすっかりそんなことを忘れてしまったようだ。
(・・・忘れた?)
島に降りるまで、かなり警戒していたはずのカインだが、そう言えばこの語り部に出会ってから、すっかりその警戒心が薄れている。それはカインがこの語り部から話を聞きたいと思っているからだと・・・・
(いや、それは違う・・・・。)
この語り部と出会ってから感じていた、あのもやもやしたもののせいじゃないんだろうか・・・。
「・・・なぜ効かないのです?」
さっきとはうって変わって、低く苛立たしげな声で語り部が言った。
「・・・・・・・・・・・。」
私は語り部を見た。今までの穏やかな笑みは消え失せ、目には冷たい光が宿っている。
「やはりあなただったのですね。」
さっきのもやもやしたものは、この語り部から発せられていたものだったのか!
「時折城下町に出掛けておりますからね。私の噂を聞きつけて、ここまでやってくる人々はけっこうな数いるのです。私達は出来れば他人に詮索されずにこの島で生きていきたいと考えておりますから、そういう方達には、その方達が一番聞きたい話をして差し上げて、早いところ引き揚げていただくようにしているのです。最初話を聞いたときは、あなた方もそういう観光目的の人々と同じだろうと思っていたのですが・・・」
語り部は一度言葉を切って、大きな溜息をついた。
「なぜかあなた方は私に対して警戒している・・・。それだけで、あなた方が今までこの島にやってきた人々とは決定的に違うことは明らかでしたよ。だがあなた方の目的がわからない以上、下手に事を構えたくはありませんでしたからね。仕方ないので、その警戒心を薄れさせ、あなた方の望む話をして差し上げて、納得していただこうと思ったわけですが・・・あなたには効かなかったようですね。」
「今のはなんです?」
「・・・気功術の一種ですよ。」
「・・・つまり、あんたは俺の心を操ろうとしたって事なのか?」
私と語り部とのやりとりを、しばらくぽかんとして聞いていたカインが言った。苦々しげな言い方をしているが、カインの言葉の裏側にはある期待がこもっている。それをこの語り部に悟られなければいいのだが・・・。
「操るなど人聞きの悪い。あなた方が、私に対してほんのちょっと好意を持ってくださるようにしたかっただけですよ。もっとも・・・」
語り部が私を見た。
「一番私に対して警戒心を持っておられたらしい方には、効かなかったようですが。」
「なるほど・・・。で、そこまでご自分の手の内を見せて、あなたはこれからどうしようというのです?」
この語り部が一番厄介だと考えているのは、どうやら私らしい。この語り部の気功が効かなかったのは、言うまでもなく私の心に張り巡らせた『防壁』の力だ。だが、この語り部はそこまでは気づいていない。おそらくこの語り部の目には、私は得体の知れない人間として薄気味悪く映っているのだろう。
「あなた方の目的をお聞きしたいですな。」
「目的・・・ですか?先ほど島の方に申し上げましたけど、それでは納得していただけませんか?」
「私の話を聞きに来られたと?それは方便でしょう。私がお聞きしたいのは、あなた方の本当の目的です。あなた方は、いったいこの島に、何の目的で来たのですか?」
語り部の目は、真っ直ぐに私を捉えて離さない。思い切って聞いてみるべきか。『あなたはサクリフィアから来たのですか』と。だが、それがもしも、この語り部が『他人に詮索されずに生きていきたい理由』であった場合、このあとに起きることは容易に想像がつく・・・。
「クロービス、せっかくだから聞いてみようぜ。」
カインは私の気持を察したのか、さりげなく剣に手を添え、いつでも抜ける状態にしている。
「そうだね・・・。」
ここで嘘を言ったところで、私達の目的を果たすことは出来ないし、本当のことを聞くタイミングがいつであれ、口に出してしまえば穏便に済ませることは出来そうにない。
「では本当の目的をお話しします。私達が知りたいのは、あなたが本当にサクリフィアからやって来た語り部なのか、ということです。答えていただけるんですか?」
「やはりそれが目的でしたか・・・。」
語り部の瞳がきらりと光ったような気がした。
「城下町でも噂にはなってるんですよ。この島に住んでいる語り部は実はサクリフィアからやって来たってね。」
「ばかばかしい。そんなこと、誰も信じていないでしょう。」
語り部は呆れたように笑って見せたが、その笑顔の向こう側に、何となく焦りが感じられる。
「他の人が信じているかいないかは、この際重要ではありません。私達が知りたいのは真実です。」
「・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・。」
語り部は答えない。私達も黙っていた。どちらもだんまりでは話が進まない。さて次にどうしようかと考えたのだが・・・・
「な・・・なんですかそれは!?」
語り部が青ざめて数歩後ずさった。突然、私の腰に下げた剣が輝きだしたのだ。鞘に入っていようが、燦々と降り注ぐ太陽の下だろうが、この剣の輝きは褪せることがない。
「お、おいクロービス、どうしたんだよ、お前の剣・・・。」
「剣に聞いてよ。私にだってわからないんだから・・・。」
「・・・なるほど、そういうことでしたか・・・。」
語り部の声に、はっきりとした悪意がこもった。
「ふふふ・・・私としたことがこんな簡単なことに気づかないとはね・・・。あなたはファルシオンの使い手だったのですね。」
この語り部はファルシオンのことを知っているのか?
「だったらどうだと言うんです?」
「ふん!さすがにとぼけるのまでお上手なようですね。ですが、私達もはいそうですかとあなたに殺されたくはありませんから、それなりの対処をさせていただきましょうか。」
「殺される・・・?」
何とも物騒な話だが、それを問いただす前に語り部の放った風水術『百雷』が、爆音と共に私達の足下を切り裂いた。