−−カチャリ−−
ドアを開ける音。誰か入ってきたのか・・・?
いや、ちがう。私は夢を見ているのか・・・。
父がブロムおじさんの家に入っていく。
「バ、バカな!?まだ昔のことを引きずっておられるのですか!?あの事は、はるか昔に終わったことではありませんか!!もう考えるのはやめてください!!」
おじさんが青ざめて叫んでいる。
「あれからもう二十年近くになるか・・・。過去を引きずることに、もはや疲れてしまった・・・。私が犯した罪は途方もなく重いものだ。私はもっと早く罪をあがなうべきだったのだ。」
父が沈痛な面持ちで話している。
「そ、そんな・・いまさら関係ない!!過ぎたことではないですか!!」
おじさんの必死な叫び。
「違うんだ・・。私の罪は、今も生きているんだよ・・。」
罪・・・?いったい・・・何のことだ・・・?
「一体何が起きたというのです?王国への旅で一体何があったのですか!!?」
おじさんが今度はすがるように父を見つめる。
「お前には詳細を言うことなど、とても出来ない・・・。知らない方がずっと良いのだ。だが、我々の考えも及ばないようなことが起きていたのだ・・・。まさか、あのような事態が・・考えられない・・。」
父は頭を抱え、つぶやくように言い続ける。
「・・・・!?」
おじさんは、驚いた顔で父を見つめ続けている。
「こんなことならば、行くべきではなかった・・。これを知った以上、私は生きていけるはずもない・・。」
「サミルさん・・・!?」
生きていけない・・・?どういう事だ・・・。
「そうだ・・・私は罪をあがなう・・・!」
突然父が顔をあげて、決心したように叫ぶ。
「つ、罪をあがなうって・・・な、何をなさるつもりなのですか・・!?」
おじさんの表情が驚きから恐怖に変わった。
「今すぐの話ではない・・。クロービスに気づかれないようにしないといかんからな。」
私に・・・?
「ブロム・・クロービスを頼んだ・・。あいつにはこんな辺境の村でなく、王国へ出て自由に幸せに暮らしてほしい・・・。」
私を思ってか、父の顔が悲しみで歪み、その瞳に涙が滲む。
「な、何をおっしゃっているのです!?ど、どうかお考え直しを・・!」
父は答えない・・・。
あがなう・・?
あがなう・・って、何を?
どうやって・・?
夢はそこで終わり、私はまた深い眠りに落ちていった。朝、目覚めると父が私の顔をのぞき込んでいる。
「おはよう、父さん・・・。」
私の頭はぼんやりしている。夢を見た日の朝はいつもこうだ。でも今は父がそばにいてくれる。それがとても心強かった。
「また・・・悪い夢を見たんだな、クロービス。」
「・・・・・・・。」
父は私の顔つきで夢を見ているかどうかわかるのだろう。ぼんやりしているか、恐怖のあまり飛び起きるか、大抵どちらかだからだ。
「・・・お前は、まだ赤ん坊の頃に重い病気にかかったことがあってな・・・。それ以来、毎晩のように奇妙な夢にうなされるようになったんだ・・・。なぜそうなったのかはわからないのだが・・・。」
父はつらそうに下を向いた。医者でありながら、私の夢の原因を突き止めることができない苛立ちがあるのだろう。
その後・・・旅から帰ってからしばらくの間に父は病気になった。寝たきりとなり、苦しげにうめく時が多くなった。病状は一向に回復を見せず・・・むしろ、一定の割合で悪化しているかのようだった・・・。
そして1年後・・・・。その頃には、朝起きて父の寝息を確かめるのが日課になっていた私は、いつものように父の寝顔をのぞき込んだ。父はふと眼を開け、私の顔をじっと見つめている。
「父さん、おはよう。気分はどう?」
「・・・ああ・・クロービスか・・。すまないのだが、ブロムのところに行って、荷物をとってきてくれんか。・・・行けば・・・わかるように言ってあるから・・。」
父はそれだけ言うと、またつらそうに目を閉じた。
「わかったよ。すぐに戻ってくるからね。」
私は外へ出た。道の向こうからやってくる人影がある。グレイとラスティだった。
「ああ、おはようクロービス。見舞いに来たんだけど、親父さんの病気の具合はどうだい?やっぱり去年長旅をしていたのが体に悪かったのかなあ・・。今、大丈夫か?」
グレイが心配そうに家の中を窺う。
「ありがとう。でもちょっと疲れているみたいだから。」
「そうか。それじゃまた来るよ。」
「ごめん。」
グレイ達は帰っていった。この時彼らを家の中にいれていたら、この後訪れる悲しみを回避することができたのだろうか・・・。
私は長老の家に寄り、父の様子を伝えた。これも最近の私の日課になっていた。
「ふむ・・・いくら医者であるサミルでも自分の病気だけは治しようがない・・か。わしらも何かしらの力になりたいんだが、こればかりはどうにもならん・・。」
長老は悔しそうに唇を噛む。長老の家を出ると、道端にデュナンさんがいた。相変わらず酒臭い。
「よぉっ!!クロービス!へっへっへ。一杯やっていかねぇか?・・・なんてそんなことするわけねぇよな、お前は。なあ、クロービス。この島の連中は皆一様に王国を嫌っている。理由は、ただ自分達が王国で落ちぶれたからで、まあ要するに逆恨みなんだがね。そんな情けない連中でもみんなサミル先生のことは心配しているんだ。俺だってそうなんだぜ。もっともいくら心配したって俺なんぞなんの役にも立ちゃしねぇから、こうして酒ばかり飲んでいるがな・・・。」
そう言うと、手に持った酒瓶の口を直接自分の口にあててぐいと飲み干した。
「ちぇっ・・・もうねえのか・・・。」
一人でつぶやいている。
デュナンさんの言葉は本心だと思いたい。この島に住む誰もが父の病気の快癒を祈ってくれている。この願いが天に通じれば・・・あるいは、父は元気になるのだろうか・・・。
ブロムおじさんの家に行く途中で、私はふと思いついてイノージェンの家に寄った。昨日イノージェンの母さんが見舞いに来てくれた、お礼を言おうと思ってのことだった。
「おはようございます。昨日はありがとうございました。」
「おはよう、クロービス。そんなこと気にしなくていいのよ。私達はいつもあなたのお父様にお世話になっているんですもの。それよりサミル先生、ここのところずっと寝たきりよね・・・。でも昨日見た感じでは顔色は良さそうなんだけど・・。何かちょっと不思議だわ。一体何のご病気なのかしら・・。」
イノージェンの母さんは心配そうに首を傾げる。
「ありがとう、おばさん。きっと大丈夫だよ。」
自分に言い聞かせるように言うと、私はイノージェンの家を出た。
「待ってぇ。クロービス。」
イノージェンが追いかけてくる。
「おはよう。イノージェン。」
「もう!!待っててくれてもいいじゃないの!どこへ行くの?」
「父に用事を頼まれてブロムおじさんのところへね。」
「ブロムさんのところかぁ。私も行ってもいい?」
「いいけど・・・。別に楽しいことなんて何もないよ。」
「そんなのわかってるわよ。ブロムさんのところじゃね。でもいいわ。今日は特別仕事もないし。」
「クロービス、おはよう。どこへ行くんだ?」
その時声をかけてきたのは、墓守をしているドリスさんだ。
「おはようございます。ブロムおじさんのところへ行こうと思って。」
「ブロムのところへ?ふぅん。それよりサミル先生、具合悪そうで心配だよ。早くよくなるといいけどなぁ・・・。クロービス、お前も大変だろうけど、しっかり看病してやれよ。サミル先生はまだまだ若いんだから、すぐ持ち直すよ。じゃな。」
そう言うと墓地のほうへ歩いて行ってしまった。
「みんな心配してるのよね。あなたのお父さんのこと。」
遠ざかるドリスさんの後ろ姿を見送ってイノージェンがつぶやく。
「そうだね・・・。」
世捨て人の島と呼ばれたこの地に来る人達は皆似たり寄ったりだが、みんな心は優しい人達ばかりだ。そのうちにブロムおじさんの家に着いた。
「おはよう。ブロムおじさん。」
ブロムおじさんはぼんやりと虚空を見つめたまま返事をしない。
「おじさん?」
私が顔をのぞき込むと、びくっとして私達の方を振り返った。
「あ、ああ、クロービス、何か用か?」
「父さんから荷物をとってきてくれって頼まれてきたんだけど。おじさんに言えばわかるって。」
「あっ、そうだそうだ。ちょっと待っていろ。」
そういうと、見覚えのない荷物袋に入った荷物を奥から出してきた。
「そら、これだ・・・。」
私は荷物を受け取った。ブロムおじさんはその様子をただじっと見つめている。
「ありがとう。それじゃ、確かに預かったよ。帰るね。」
そう言ってドアを出ようとした時、突然ブロムおじさんが叫んだ。
「ク、クロービス・・・!!」
ただならぬ気配に思わず振り返ると、ブロムおじさんが青ざめた顔で私を見つめていた。
「な、なに?・・・どうしたの?」
「い、いや何でもない・・・。そ、そうか・・い、家に帰るのか・・・。も、もう、ちょっと遊んでいってもいいんだぞ・・。」
なんだか妙だ・・・。
「ん、いや、いいよ。イノージェンもいるし。このまま帰るよ。おじさん、ありがとう。」
「そ、そうか・・・。」
ブロムおじさんの家のドアを閉めるなり、私は駆け出していた。
「クロービス!!どうしたの?待ってよ、ねぇ!」
イノージェンが慌てて追いかけてくる。
「イノージェン!長老を呼んできてくれ。私の家に!」
それだけ言うと、私は家への道を一目散に走った。
「ちょ、ちょっと、どういうこと!?」
イノージェンの声ももうほとんど耳に入っていない。1年前のあの日、父が帰ってきた日の夜の夢。
あがなう・・・。
あがなうって何を・・・?
どうやって・・・!!
寄り道などしなければよかった。まっすぐにブロムおじさんの家まで行き、荷物を受け取ったらすぐに家に戻ればよかった。言いようのない不安に駆られ、私はドアを開けるのももどかしく家に飛び込んだ。
「父さん、ただいま!」
返事がない。
「父さん、ブロムおじさんから荷物を預かってきたよ。父さん!」
ベッドを覗き込んで父の体を揺さぶる。父の体は冷たくなっていた。
「父さん・・・?父さん!!父さんてば!!父さん!!」
父はまるで眠っているかのようなやすらかな表情を浮かべている・・。預かった荷物を取り落とし、私は父の体をもう一度思い切り揺さぶった。
「父さん・・・・!ねぇ、眼を開けてよ・・・父さん!!父さん・・・・!!どうして・・・私をおいて・・・こんなに早く・・・!!父さん!!」
ただ涙が溢れ出る・・・。父とこの島で過ごした日々が次々と脳裏に甦る。母親のいない寂しさを味わうことのないようにと、父は必死で私を育ててくれた。厳しかった、でも優しかった父。私のたった一人の肉親・・・。1年前、家に帰ってきた時は別にどこも悪くないはずだったのに、なぜ!?どうして!?
イノージェンが長老を伴って私の家に着いた時、私は父のベッドの脇でただ涙を流しながら座り込んでいた。
「クロービス!これは・・・どうしたことじゃ!サミル!サミル!!返事をせい!サミル!!」
長老が父のベッドに駆け寄り大声で叫ぶ。
「クロービス!!サミル先生は・・・・!」
イノージェンが声を震わせながら私に駆け寄ってきた。
「私を・・・おいて・・・逝ってしまったんだ・・・。独りで・・・・。」
それだけ言うのがやっとだった。
「そんな・・・そんな・・・サミル先生が・・・。」
イノージェンが私の肩に顔を埋めてわっと泣き出した。私は思わずイノージェンを抱きしめて、そのまま涙が涸れるまでただ泣き続けた。
そのころには、村の中を駆けていく私の姿や、長老が慌てて私の家のほうに向かう様子を見ていた人達が何事かと集まってきていた。皆口々に父の死を悲しみ、涙を流してくれた。父の棺はダンさんとドリスさんが作ってくれた。
「畜生!またこんな仕事が出来ちまうとは・・・・。」
ダンさんは涙と鼻水をぬぐいながら一生懸命金槌をふるっている。
「もうこんな辛い仕事は・・・フローレンス達の時で終わりだと思ってたんだが・・・。」
ドリスさんも涙で赤くなった目でつぶやいている。フローレンスというのがライザーさんの母親の名前だと後でイノージェンから聞いた。グレイとラスティの両親の棺もライザーさんの両親の棺も、みんなこの二人が作ってくれたのだと。こんな風に涙を流しながら・・・。
父の遺体を棺に納めて、みんなが立派な墓を作ってくれた。墓の前で手を合わせる私に、ドリスさんが慰めるように話してくれた。
「クロービス、この集落では葬式を行ったりはしないんだ。大切な人を失った悲しみを癒すには、ただ時が過ぎるのを待つしかないこと、そして、悲しみの中にある人を慰めるにはただ、そっとしておいてやるのが一番だと、みんなが考えているからなんだよ。」
「・・・・。」
私は何も言えなかったが、その心遣いは痛いほど伝わった。埋葬がすんだあと、私は一人重い足を引きずりながら家に戻った。そこには、ブロムおじさんが待っていた。
「生前のサミルさんからいろいろと申しつかっている。お前は、この集落を出てエルバール王国へ行くんだ。」
「王国へ?どうして?」
私が王国へ・・・。この島を出ていくというのか・・・。
「この島とエルバール大陸の極北の地が海底洞窟でつながっているんだ。途中まで私も同行する。出立の準備が出来たら、行くぞ。」
「ちょ、ちょっと待ってよ。まだ決めたわけじゃ・・・。父さんが亡くなったばかりだっていうのに・・・。」
「クロービス、気を落とすのも無理はないが、サミルさんは天寿を全うされたんだ。いつまでも気にしていたらいけないぞ。」
「天寿?」
「ああ、そうだ。」
「本当に?だってまだ57歳だよ。天寿って言うほどの歳もとっていないじゃないか。」
私の言葉にブロムおじさんの顔色がさっと変わった。
「ど、どういう意味だ?」
おじさんは明らかに狼狽している。
「だって、1年前帰ってきた時は元気だったじゃないか。急に・・・。なんだかおかしいよ。」
そう言ったものの、あの不思議な夢のことは言えなかった。言えばまた「意味がない」と逃げられてしまう、そんな気がした。
「な、なにを言っているんだ、クロービス!サミルさんは去年から重病だったじゃないか・・・。あのサミルさんの安らかな死に顔、見ただろう?彼は天寿を全うしたんだ!それ以外に何があるというんだ!?」
ブロムおじさんのその態度に、父の死には何か秘密があると、私は確信した。
「とにかく・・・少し考えさせてよ。いきなり言われても・・・。」
そうは言ってみたが、今は何も考えたくなかった。ただ少しだけ、一息ついて休みたい・・・。
「・・・わかった。お前の気持ちも考えずに悪かったな・・・。でもこれはサミルさんの遺志なんだ。それは忘れないでくれ。決心がついたら私の家に来てくれ。私はいつでも出立できる用意をしておくよ。」
「うん・・・ごめんね。おじさん。」
「気にするな。じゃな。」
そう言うとおじさんは出ていった。
父の遺志・・・。私が王国へ出ていくことが・・・。なぜ私が王国へ出ていかなければならないのだろう。住み慣れたこの島を離れて・・・。エルバール王国・・・。岬から見える遙か彼方の島影。イノージェンが待ち続けるライザーさんがいるところ・・・。
私は頭を思いきり横に振ると、ベッドに身を投げ出した。一休みしようと目をつぶるが、頭の中には父の顔やあの日の不思議な夢が浮かんでは消えていきまた現れる。一休みは出来そうもなかった。仕方なく起きあがると、私は家の中を見回した。父の死以来大勢の人達が出入りした家の中は雑然としている。すこし家の中を片づけなくてはならない。片づけながら考えよう・・・。そう思っても動く気にもなれず、私は何気なくベッドのサイドテーブルの引き出しを開けた。見覚えのない表紙の本がある。開いてみると、それは父の日記だった。震える手でゆっくりとページをめくる。最後の日付は、父が亡くなった日だ。あの日、私が家を出てから書いたのだろうか。私はおそるおそる読み始めた。
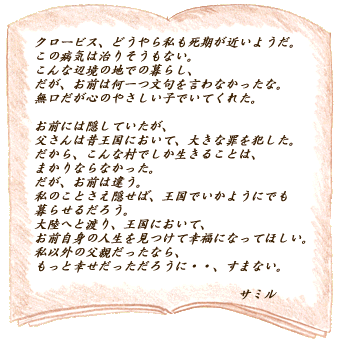
(父さん・・・・!!そんな・・・父さんだからよかったんだ!私の父親は父さんだから・・・。他の人なんかじゃなく・・・・!!)
最期の時にさえ私を思いやってくれる父の深い愛に、私の目にはまた涙が溢れた。
ブロムおじさんから預かった父の荷物の中には、上等な細身の剣と、500Gもの大金が入っていた。剣には「ファルシオン」と銘が入っている。この剣の名前だろうか。それから薬草と、簡単な薬の調合方法を書いた紙、それに風水術と治療術の呪文書。父に教えてもらった風水術・・・。
「いいか?クロービス。呪文を簡単に操れると思ってはいけない。常に精神を高める努力を続けて慢心しないことが重要だ。」
父の言葉が脳裏に甦る。日記を荷物の中にしまい込み、私はもう一度家の中を見回した。何か・・・奇妙な違和感がある・・・。いつもと違う・・・でも何が?どこが?
私は、よりいっそう注意深く、ゆっくりと部屋の端から端までを見渡していった。そして部屋の隅に置いてある、子供の頃から弾きなれたピアノに目をとめた。ピアノの譜面台の上に楽譜が置いてある。
(こんなのあったっけ・・・・?)
練習曲の教則本ならいつも置いてあったが、今はそれがない。そしてこんな楽譜は今までに見たことはない。とすれば父が置いたものだろうか。父が亡くなってから、家の中など見渡す余裕はなかった。ずっとここにあったのだろうか・・・。楽譜の曲名のところには『Lost Memory』とだけ記されている。作曲者の名前も何も書いてない。
(とにかく弾いてみようか・・・。)
呪文とともに小さな頃から父に手ほどきを受けたピアノで、私はこの曲を弾いてみることにした・・。
弾きなれたピアノの音でさえ、何か異なるものに聞こえた。
その一つ一つの旋律が、私の脳裏から、いくつもの断片を拾い上げるのを感じていた。
それは、もう二度とよみがえることはないと思っていた記憶。
流れゆく時とともに、忘れてしまっていた子供の頃のかけがえのない想い出。
いつしか私の心は・・すべての出来事をあるがままに受け入れていた
子供のころの無垢な気持ちに戻っていた。
不思議な感覚だった・・・。
表現出来ない暖かさに包まれて、私は夢中で鍵盤を叩いていた。
同時に私は、幾多のものが変わりつつあることを感じていた。
自分自身も含めて・・。
南の空に広がる曇天と生き物達のざわめき。
微妙にゆれる空気の流れ。
幼いころから夢に出てくる少女のリアルで悲痛な叫び声。
そして父の遺した「Lost Memory」とだけ書かれた楽譜。
込みあげる言いようもない懐かしさを胸中に抑えて、
そのとき、私は故郷を発つことを決意していた・・・。
家の中を片づけ、今は父の形見となった荷物袋に楽譜をしまい込んだ。そして父との薬草摘みの時に使っていた弓と、矢の詰まった矢筒を抱え、服も山歩き用の少し厚手のものに替えた。その時、父が最後の旅に着ていたレザーアーマーが、ふと目にとまった。山に入る時もいつも父が身につけていたこの鎧を、私は着ていこうと壁から降ろした。表面には無数の細かい傷がある。だが作りはとてもしっかりしている。今まで、山歩きの際にも私は鎧を身につけたことはない。父から剣を教えてもらってはいたが、山に入った時に剣を持っていたのは父だけで、私はいつも弓を担いでいた。動物達が近づく前に矢を放てば、大抵はそれですんでいた。今までそれを何とも思わずにいたが、いつも私の前には父がいて、父が私を守ってくれていた・・・。
手に持つレザーアーマーが涙で滲む。私は袖で涙を擦ると、その鎧を着込んで、その上から上着を羽織った。
(父さん・・・。私は父さんの遺志を継いで、エルバール王国に行くよ。何が待っているかわからないけど・・・。でもきっと自分の居場所を見つけるよ。)
心の中で父に別れを告げ、私は家を出た。
庭に咲き乱れる美しい花々とも、しばらくのお別れだ。いや、もしかしたらもうここに戻ることはないかも知れない・・・。私は庭を見渡した。その片隅に咲く小さな草花・・・。確か『シオン』という花だ・・・。イノージェンが教えてくれた花言葉は・・・『あなたを忘れない』。たとえ、もう二度と戻ることがなくても、私はこの場所を忘れない。父と過ごしたこの家を、庭を、そこに咲く花を、そしてこの島のすべてを・・・私は忘れないで生きていこう・・・。
意を決して、今まで過ごした家に背を向け、集落への道を歩き出した。
私はまず長老の家を訪ねた。
「こんにちは、長老。お別れに来ました。私は・・・この島を出ます。」
長老は私の顔をじっと見つめて、何度か小さくうなずいた。
「そうか・・・。そうじゃな・・・。お前のような若い者が、これからもこの集落で過ごす必要はあるまい。あるいは、サミルの死はお前にとってちょうどいい人生の岐路になったのかもしれんな・・・。」
「はい・・・。ところで長老、この楽譜に見覚えはありませんか?」
私は、先ほど家の中で見つけた楽譜を長老に見せた。
「これは・・・?いや、見覚えなどはないが・・・。」
長老は不思議そうに楽譜を見ている。私はこの楽譜を手に入れた経緯を話した。
「なるほど・・・この楽譜をサミルが遺したというのか・・・。死に瀕して、楽譜を置いていくとは・・・ずいぶんと奇妙な話じゃのう・・・。サミルのことじゃ、意味もなくそのようなものを置いていくとは思えないが・・・。もしかしたら一年前の旅で手に入れたものかも知れぬな。お前が王国に行くことで何か手がかりがつかめるかもしれん・・・。」
「はい・・。長老、お世話になりました。お元気で・・・。」
「うむ、お前もな。達者で暮らせよ。」
長老の家を出ると、そこにはグレイとラスティが立っていた。
「クロービス、大変だったな・・・。でも親父さん、とっても安らかな死に顔だったな。何ていったらいいのかわからないけど・・・きっとサミル先生は満足して亡くなったんだと思う。元気を出せよ・・・クロービス・・・。」
グレイはそう言って私の肩を叩いてくれた。
「ありがとう。グレイ、実は私は、これからこの島を出ようと思うんだ。」
「え?お前、行っちまうのか!?」
ラスティが叫ぶ。
「うん・・・。父の・・遺言だそうなんだ・・・。私にこの島を出て、エルバール王国で暮らすようにと・・・。」
「エルバールで・・・そうか・・・。寂しくなるな。」
ラスティは大きくため息をつき肩を落とした。
「・・・クロービス。お前今ちょっといいか?」
突然グレイが真剣な目で私を見た。
「いいよ。なに?」
「ちょっと来てくれ。ラスティ、お前は家に帰ってろ。」
「あ、ああ、いいよ。」
わけがわからずきょとんとしているラスティを残し、私とグレイは岬に来ていた。
「どうしたのさ?急にそんなに怖い顔して。」
グレイは黙っていたが、やがて何かを決心したように話し始めた。
「おまえは・・・イノージェンのことをどう思っている?」
突然の質問に私は戸惑った。
「どうなんだ?言えないのか?」
グレイは真剣だ。そうか・・・。グレイはイノージェンのことを・・・・。
「・・・彼女のことは大事に思っているよ・・・。」
それが今の私に言える精一杯の言葉だった。
「それなのに出ていくのか?彼女と結婚してこの島で生きていくってのは、お前のこれからの選択肢には入っていないのか!?」
グレイが詰め寄る。
「・・・私だってそう出来たらって思うよ・・・。でもイノージェンにとって、私は弟でしかないんだ。彼女が想い続けているのは、昔この島にいたライザーさん一人なんだよ。」
「やっぱりそうなのか・・・。」
以前山歩きをした時に、私がイノージェンからいつもライザーさんのことを聞かされていると、グレイに話したことがあった。彼女の心の中がライザーさんのことで一杯なのだと、あの時から彼も気づいていたのだろう。
「そうだよ。前も言ったけど・・・ここでイノージェンが私に話すことと言えば、全部ライザーさんのことばかりだよ。必ず戻ってきてくれるって。何があっても待ち続けるって。イノージェンの心の中は・・・ライザーさんでいっぱいなんだよ・・・。」
「・・・それを・・・お前はいつも黙って聞いていたのか・・・!?」
「それしかないじゃないか。あんなに楽しそうに話されたら・・・何も言えないよ・・・。」
「俺はずっと彼女が好きだったんだ。でもお前達はいつも一緒だし、彼女が俺を見ていないのはわかってた。だからお前なら許せるかなと思ってたんだ。」
グレイはそう言って唇を噛んだ。
「グレイ・・・。」
グレイの切ない胸の内を思うと、かける言葉が見つからない。
「でも・・・ライザーはもう15年も前にここを出ていったんだぞ。イノージェンがいくら思ってみたところで、あいつの方はこんな島のことなどすっかり忘れてるさ。」
「でもイノージェンは信じているんだよ。いつかライザーさんが自分のところに戻ってくるって。ライザーさんがこの島を出てから15年間、ひたすら信じ続けているんだ・・・。」
グレイは遙か彼方のエルバール大陸に目をやり、ため息をつくとゆっくりと話し始めた。
「なあ、クロービス、俺はこの島に船で流れ着いたんだ。ラスティと一緒にな。俺達の両親はエルバール王国から逃げるように船を出した。でもこの島に向かっていたのかどうかはわからない。途中で差し違えて死んじまったんだ。船の中で、俺達の目の前でな。」
これは私が初めて聞く話だった。
「・・・二人とも泣きながら、俺達を見つめて『さよなら』って。何があったのかはわからないけど・・・。ラスティの奴は憶えてないだろうな。あいつは赤ん坊だった。舟に乗っていた間中、俺はあいつを抱いていたんだ。ここに流れ着いた時、最初に見つけてくれたドリスさんが、俺の手からラスティを抱き上げようとしたけど、腕が固まっちまってなかなかはずれなかったんだ。俺はずっとあいつを抱いたまま、体中に力を入れて震えていたからな・・・。」
グレイは淡々と話す。その冷静な口調が、かえってその時の彼の悲しみの大きさを感じさせた。
「だがとにかく俺達はここに流れ着いた。長老の家に引き取られ、やがてライザーとイノージェンと遊ぶようになったんだ。それは前にも話したよな。イノージェンはライザーのあとばかりついて歩く。ライザーは病気のせいで走ったり出来なかったから、いつも俺達はイノージェン提案のおままごとばかりだった。でもそれでもよかったんだ。両親の死で傷ついていた俺の心を癒してくれたのは・・・彼女の笑顔だったんだ・・・。」
自分の目の前で両親が差し違えて死んでしまう・・・。想像するだに恐ろしい光景を、グレイは実際に体験してきたのだ。どれほどつらかったことだろう・・・。そしてその傷から立ち直らせてくれたイノージェンへの思いは、きっと私の彼女への思いなどより何倍も強い・・・。
「そしてそれから、俺はずっとイノージェンを見てきた。でも彼女は、ライザーが島を出てからは俺よりもお前と仲良くなっていった。正直悔しかったけど、お前が彼女を幸せにしてくれるなら、俺は黙っているつもりだったんだ。でもお前が島を出るのなら話は別だと思って、ここではっきりとお前の意志を聞こうと思ったんだ・・・。でも・・・そうか・・・相手がライザーでは勝ち目はないかもしれないな。イノージェンにとってライザーはいつだって特別なんだ。たとえあいつがずっと帰ってこなくたって、イノージェンはあいつを想い続けるんだろうな・・・。」
グレイの最後の言葉は、まるで自分に言い聞かせるようなつぶやきだった。そしてそこまで話すと、遙か彼方のエルバール王国の島影を見た。切なそうに目を細めて・・・。その時、岬の入口で私を呼ぶ声が聞こえた。
「クロービス!!」
イノージェンの声だった。私は黙って振り向いた。
「ラスティから聞いたわ!!あなた島を出るってほんとなの!!?」
「俺は帰るよ。ちゃんと別れの挨拶はしていけよ。」
グレイが手を挙げて私に背中を向けた。
「グレイ、ありがとう・・・。ごめん。」
「謝るなよ。お前が悪いわけじゃないんだ。」
そして走り去るグレイと入れ違いに、イノージェンが私のところに駆けてきた。息を切らせながら私を見上げる。
「ねぇ、本当にここを出ていってしまうの?」
「本当だよ。だからみんなに別れの挨拶をしてまわっていたんだ。」
「そんな・・・。どうして?寂しくなってしまうわ・・・。」
イノージェンの目に涙が滲んだ。
「きっとライザーさんが君のところに戻って来るよ。島のみんなもいるし、寂しくなんてならないよ。」
「ライザーはライザーよ。あなたはあなただわ。いなくなったらとても寂しいわ。」
涙を拭おうともせずに私を見上げる瞳。風になびく金色の髪。もう会えるのはこれが最後かもしれない・・・。そう思った瞬間、私は両腕をまわしてイノージェンの体をしっかりと抱きしめていた。
「クロービス・・・!」
私の腕の中でイノージェンが戸惑っているのがわかる。このまま離したくない。いっそ一緒にこの島を出ていけたら・・・。でも・・・それは出来ない・・・。
「・・・このまま、君とこの島で生きていけたらと・・・思ったこともあったんだ・・・。でも、君の心の中にはライザーさんがいて、私が入れる余地と言えば弟としてだけだったから・・・。」
「・・・クロービス・・・。」
イノージェンの目からまた涙が溢れ、私の服の肩をぬらした。
「・・・この島を出るのは、父の遺言のこともあるんだけど、私自身、いつまでもここに閉じこもっていてはいけない気がするんだ。だから・・・これでお別れだね・・・。今まで色々ありがとう・・・。」
私はゆっくりとイノージェンの体に回していた腕をほどいた。
「行ってしまうのね・・・。」
「うん・・・。」
「ライザーも行ってしまった・・・。そしてあなたも・・・行ってしまうのね・・・。エルバール王国へ・・・。」
「うん・・・。もしかしたら向こうでライザーさんと会うこともあるかも知れないね・・・。最も私は、その人の顔も知らないし、どこにいるのかも全然わからないけど。」
「・・・知っているわ・・・。」
海を見つめながらイノージェンが小さくつぶやく。
「え・・・?」
思いがけない言葉に、私は思わず聞き返していた。
「ライザーは・・・王国剣士なの。」
「知っているの?どうして・・?」
「5年前手紙が来たわ。王国剣士になれたって。君との約束は忘れてないよって・・・。」
「返事は出したの?」
「出せなかったわ・・・。ここから手紙を出すには、誰かに頼まなくちゃならないもの。ライザーの手紙も、ひと月に一度来る商人に頼んでよこしたのよ。その商人が気を利かせて、うちで頼んでおいた荷物の中にうまく隠してくれたから誰にも見つからなかったけど。私が荷物を整理していて見つけたから・・・このことは母も知らないわ。見せようかとも思ったけど・・・母だって王国でつらい思いをしてきたんだから・・・そう思ったらやっぱり言えなかった・・・。」
この島には店などない。生活物資はすべて自給自足というわけにはいかないので、エルバール王国の商人が、ひと月に一度だけ船で色々な物を売りに来ていた。
「この島の人達にとって、エルバール王国は憎しみの対象なの。私はここで生まれたからそんなことを気にしたことはないわ。でも、みんな王国で傷つき疲れ果ててこの島に逃げ込んで来たの・・・。そんな人達にとって、王国剣士は王国の象徴なのよ。ライザーが王国剣士になったなんて知れたら、みんなが彼を受け入れてくれなくなってしまうわ。それに・・・そのことを聞いただけで傷つく人だってきっといるわ・・・。そう思ったら、返事なんて書けなかった。たくさんたくさん書きたいことはあったけど・・・。」
イノージェンは岬からみえる王国の島影を見つめながらそこまで話すと、ゆっくりと私に振り返った。
「でも・・・こんなことをあなたに話してはいけないわね・・・。今まで色々とごめんなさい・・・クロービス・・・。」
「いいよ、そんなことは気にしないで。今まで君と一緒にいられて、楽しかったよ。」
「私達、お友達よね?」
「うん。」
「ずっと変わらないわよね?」
「変わらないよ。」
「じゃ、約束して。いつか必ずこの島に帰ってくるって。そしたらまた色々お話ししてくれるわよね?」
「そうだね・・・。元気で、イノージェン・・・。」
「あなたもね・・・。」
そのまま私はイノージェンを岬に残し、集落への道を歩きだした。イノージェンが私の背中を見送っているのがわかる。振り返りたい・・・。でも、振り返ればもう、私はここから一歩も歩き出すことが出来ないかも知れない。私は唇を噛みしめて一歩ずつ歩いていった・・・。
途中の道にダンさんがいた。
「こんにちは。ダンさん」
「おう、お前この島を出るんだってな。ラスティから聞いたよ。」
どうやらもうすでに、私のことは島中に知れ渡っているらしい。
「結局・・サミル先生は謎を残したまま逝っちまったな・・。お前の持っているその剣だってかなりの値打ち物だぜ?いったいどこで金を手に入れていたんだろう。そしてこんな島に来た理由は一体何だったんだ?俺は世話になるばかりで、何一つ恩返しが出来なかったよ・・・。」
ダンさんが涙をにじませ、鼻をすすった。
「・・・わからないけど、王国でその答が見つかるような気がするんです。」
「そうか・・・。達者でな。」
「はい、ダンさんも。」
やがて墓地の前にさしかかった。父の墓も、もしかしたら見納めになるかも知れない。墓前に最後の別れを告げようと、私は墓地に入っていった。