カインを行かせたことが、本当に正しい選択だったのか・・・未だに私は答を見つけられないでいる・・・。
私達はサクリフィアの船着場から船を出した。朝日に向かって船は順調に進み、さわやかな風が頬を撫でていた時のこと・・・
≪ファルシオンの使い手よ・・・≫
ふと聞こえた声に顔をあげた。
「その声は、『導師』ですね・・・。」
「え?」
ウィローが振り向いた。
≪あなた達の旅は順調に進むだろう。あなたの仲間の旅も・・・≫
「カインは無事なんですね。」
≪彼の進む道がこの先どうなるのか、それは彼の心にかかっている。あなた達はムーンシェイを目指されるがよい。海の者達はあなた達を襲いはせぬ。無駄に体力を使うことはないだろう。≫
「わかりました。ありがとうございます。」
≪剣が姿を現し、使い手を選んだことで私の力も少しは神殿の外へ及ぶようになったが・・・私があなたに助言出来るのもここまでが限界だ。これより先は、何事も出会う人々の話をよく聞き、助言には耳を傾けて進まれるがよい・・・≫
「はい。いろいろとお世話になりました。」
「カインはきっとあの冒険者の人達と仲良くなったんでしょうね。」
今の『導師』の声は、ウィローにも聞こえたらしい。サクリフィアの神殿では、精霊達の声もカインとウィローに聞こえていた。聖戦竜達の声もみんなに聞こえてくれればいいと思うのだが、聖戦竜達の声と精霊達の声との違いはなんなんだろう。
「そうだね。なんだか王国剣士の斥候みたいに思われちゃったらしいから、みんな同情的なんだと思うよ。」
「でもさっきのはどういう意味かしら。『彼の進む道がこの先どうなるのか、それは彼の心にかかっている』って・・・。」
「フロリア様のことが、あの杖で解決しないってことかも知れない・・・。」
その時、カインが心を強く持てるかどうか・・・そういうことなんだろうか・・・。
「確率は半分だもんね・・・。でも、それならそれで仕方ないわ。何か他の方法を考えなくちゃ。そろそろお昼だし、食事にしましょうか。あの『導師』さんの言ったように、今朝からモンスターに襲われてはいないけど、お腹が空くのは変わらないのよね。」
ウィローが笑った。
「そうだね。あ、そう言えば、今朝村長が持たせてくれた包みがあったから、あれを開けてみよう。」
私の荷物の中に入れてあった包みを取りだした。中に入っていたのは干し肉とパンと、サンドイッチだった。そして・・・
「ねえこれ、メイアラさんの手紙じゃない?」
ウィローが包みの底から取り出した封筒には宛名はなく、裏に小さく『メイアラ』とだけ書かれていた。
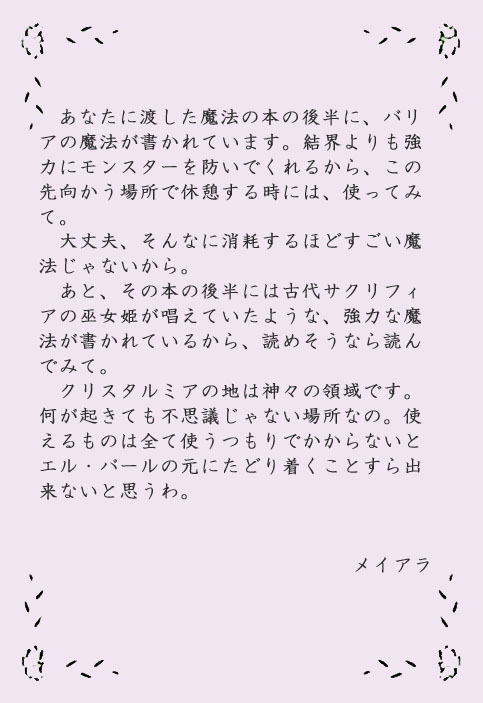
「・・・・・・・・・・・・・・・・。」
ウィローと2人、顔を見合わせた。
「これも助言の一つってことなんだろうね。」
「私達が行こうとしている場所は・・・そういう場所なのね・・・。」
「村長の言葉は大げさでも何でもないってことだね。」
「ええ・・・でも、私達は絶対にエル・バールを説得する。どんな場所でも、必ず一緒よ。」
「うん・・・。」
「食事をしたら、あの魔法の本を読んでみましょうよ。もしかしたら、簡単な呪文なら私でも何とかなるかもしれないわ。」
「・・・・・・・。」
「クロービス!」
ウィローがいきなり私の背中を叩いた。
「出来ることはしておきましょうよ。私達は失敗するわけに行かないのよ。」
セントハースからエル・バールの話を聞いた時、ウィローは取り乱していた。でも今、目の前の現実に戸惑っているのは私のほうだ。この期に及んで、魔法なんて覚えたくないともう1人の自分が叫んでいる。平穏に暮らしたい、何もかも捨てて逃げ出したい。私には・・・伝説の剣などふさわしくないと・・・。
「女の人のほうが土壇場の度胸があるってのは本当だね。腰が引けているのは私のほうだな・・・。」
「私だって怖いもの。でもあなたがいるでしょ?そしてあなたには私がいるの。私はカインの代わりにはなれないけど、ちゃんとあなたの補佐をするわ。カインが戻って来た時に、胸を張って会いたいじゃない?」
「・・・ごめん・・・。」
「それに、魔法って言っても、本の前のほうに書かれているのは簡単な呪文ばかりなんでしょ?読んでみましょうよ。私だって無理はしないわよ。」
夢見る人の塔へと至る『彷徨の迷い路』で聞こえてきた声が、間違いなく自分の心の声なのだと今更ながら気づく。私の中には、ここまで来た今でさえ、こんな情けない考えが残っている。これから先に向かう場所での私の敵は、きっと自分自身の弱さなんだ。どんな時にも心を強く持てなければ、聖戦竜を説得するなんて、出来るはずがない・・・。
この日から、私達は2人で魔法の本を読み始めた。ウィローは、自分にも唱えられる程度の魔法を探して、積極的に本を読み進めていった。私が大きな魔法を扱うようになれたとしたら、それだけ私の負担は増すことになる。だからウィローは、その負担を軽くするような、出来れば回復の呪文がほしいわねと、なんとなく楽しそうに、本をめくっている。
『導師』の言葉通り、海のモンスターはいっこうに現れず、私達は穏やかな海を順調に進んでいた。それなのに・・・私の心に重くのしかかる不安と孤独感は、ムーンシェイに近づくに連れてますます深くなっていった。カインは笑顔で冒険者達の船に乗った。そして遠くない再会を約束して去っていった。カインと離れて行動するのは初めてじゃないはずなのに、そしてカインは順調に旅を進めていると聞いているのに・・・それでも不安はぬぐい去れない・・・。
「ねぇ、クロービス、この分なら本当に早くムーンシェイに着きそうね。」
「そうだね。でもあんまり早く着きすぎてカインが追いついてくる前にエルバールに出会ってしまうのも困るな・・・。待っててくれればよかったのに、なんて文句を言われそうじゃないか。」
「きっと大丈夫よ。カインのことだもの。絶対に無茶な計画たてて、頑張ってそれを実行しているわよ。」
「ははは、それもそうだね。」
笑っているのに、心の中は石でも飲み込んだように重い。
「クロービス。」
ウィローの声に振り向いた。
「不安なのはわかるわ。私だって同じよ。だから、つらい時にはつらいって言って。」
「・・・ごめん・・・。」
ウィローをぎゅっと抱きしめた。それだけで少し心が軽くなった。2人でいるのに1人で頭を抱えてもいいことはない。とにかく今は、ムーンシェイに無事に着くことだけを考えよう。いくら私が剣に守られていると言っても、自分で何一つ努力しないような怠惰な人間では、いずれ剣に見放されてしまうだろう。この剣を手放す日が、もしかしたらいずれは来るのかもしれないが、それは今であってはならないのだ。そして、心の中にずしりと重くのしかかったままのこの不安と孤独も、自分の力で克服しなければならない。私達がこれから説得しようとしているのは『聖戦竜』なのだ。私は一人自分の心の闇と戦いながら、ひたすらにカインが無事に追いついてきてくれることだけを願いつつ、ムーンシェイへ向かって船を進めていった。そしてサクリフィアの船着き場を出てから3日目の夜・・・
「交代するわよ。」
ウィローが船室から出てきた。夕べもその前もウィローはこうして不寝番に立ったが、『導師』の言葉通り、モンスターが海から躍り上がってくることはなかった。それでも気は抜けないし、ウィロー1人を残して船室に下りるのは不安だったが、甲板の上ではゆっくりと眠れない。私は昨日と同じように、後ろ髪ひかれる思いで船室へと降りていった。寝袋を引っ張り出してもぐりこむ。船上のウィローが気になったが、それでも眠気はやってきて、いつのまにか私は眠りに落ちていた・・・
『ふぅ・・・いきなり後ろから来るとはなあ・・・。確かに気が抜けないな。』
カインだ・・・。剣を鞘に収めながらぶつぶつ言っている。
『いやはやあんたの腕はすごいよ。さすが王国剣士だ。』
『まったくだ。なあ、あんたと一緒にいたあの黒髪の兄ちゃんはどうなんだ?こう言っちゃ悪いが、あんたよりは細っこいからひ弱そうに見えたんだよなあ。』
カインが笑い出した。
『あいつの腕は俺が保証しますよ。あいつは剣のほかに弓も風水術も使いこなしますからね。しかも治療術まで使えるときてる。俺より遥かにすごい奴ですよ。』
そんなに持ち上げないでほしいなあ・・・。
『へぇ、人は見かけによらないもんだ。しかしフロリア様も何を考えていなさるのかねぇ。こんなに腕の立つ剣士がそろっている剣士団を解散させて、代わりに出来た王国軍とかいうのは、なんでもならず者の集団みたいなもんだって言うじゃないか。』
『お偉い人の頭の中なんて、下々の俺達に理解出来るはずがないさ。でもまあ、王国剣士が今でもこうして活動してるって思うと、俺達としても心強いよな。』
『カイン、頑張ってくれよ。俺達みんなあんたと、あんたの・・・相方って言うのか、あの細っこい兄ちゃんには期待してるからな。』
『はい。何とか頑張って、一日も早く元のエルバール王国に戻れるよう頑張ります。』
『その意気だな。それじゃそろそろあんたの舵捌きを拝ませてもらうとするか。おーいみんな、船酔いする奴はあんまり飯を食わないでおけよ。』
冒険者達が一斉に笑い出し、『今から間に合うか!ばぁか!』『もうみっちり食っちまったぞ!』と声が上がった。
『ははは・・・皆さんを船酔いさせないように気をつけます。』
カインが頭をかきながら舵を握った・・・・
「・・・・・・・・・・・・・・・。」
朝、ぼんやりと目が覚めた。あれは何日目の話だったのか、日数がわかるような会話は出てこなかった。ただ、彼らの周りの景色はサクリフィアの船着場の周辺とは違っていたから、ある程度南下してからの話かもしれない。カイン達は私達と同じ日に出航したのだから・・・
「もしかしたら昨日辺りの出来事なのかな・・・ははは・・・無事みたいだ・・・。」
涙がにじんだ。夢の中とは言え、カインの無事な姿を見ることが出来たのがうれしかった。カインはいつもと変わらぬ笑顔で冒険者達と話していた。そう、『導師』の言葉通り、カインは順調に旅を進めている。私が心配することなんてないはずなのに・・・。
「・・・クロービス?」
ウィローの声に顔を上げた。
「あ、ごめん。もう日が昇ってるね。」
[何か・・・夢・・・見たの?」
ウィローは不安そうだ。私はカインの夢を見たことを話した。とても元気に旅を続けているところを・・・
「よかった。それじゃあの『導師』さんの言葉通りね。」
ウィローは笑顔になって、天気がいいから甲板で食事をしましょうよと私の腕をひっぱった。
遥か前方に島影が見えてきたのは、それから数日後の午後のことだった。サクリフィアの人達からは、ムーンシェイはそれほど遠くないと聞かされていたが、一週間程度なら、『それほど遠くない』部類に入るのだろうか。
「あれがムーンシェイの大地なのかな・・・。」
「そうみたいね・・・。でも何だか白くない?」
「氷壁みたいだね。進路が少し東寄りになったかな。もう少し南側に向かっていこうか。」
この氷壁の向こうは、おそらく『クリスタルミア』だ。
「海が穏やかだから油断してたかな・・・。南下してるつもりだったのに、いつのまにか東側に流されていたみたいだね。」
つまり、それだけ私は時間をかけすぎてしまったということか・・・。おそらくまっすぐムーンシェイに向かう航路を通れていたら、確かに『それほど遠くない』のだろう。
「仕方ないわ。一人で舵を握ってるんだもの。焦らないで行きましょうよ。」
私は舵を切って舳先を南に向けた。ちょうど風が吹いて、それほど苦労せず船の進路を変えることが出来た。前方に見えていた氷壁が少しずつ遠ざかる。ふと・・・今では遠く離れてしまった故郷からも、北側の無人島の氷壁が見えたことを思い出した。
(みんなどうしているのかな・・・。)
懐かしい人達の面影が浮かぶ。イノージェン、グレイ、ラスティ、ダンさん、ドリスさん、そして・・・ブロムおじさん。もしもこの世界が滅ぼされてしまったら、あの人達とももう永遠に会うことは出来なくなるのだ。そんなことにはさせない。何としても飛竜エル・バールを説得しなければならない。
「あそこがムーンシェイの村の入口かしら・・・。」
進路を南寄りに変えてから数日後、氷壁は徐々に姿を消し、豊かな緑の森が船からも見えるようになってきた。そして前方に桟橋のようなものが見えてきたのは、その翌日のことだった。
「そうみたいだね。人がいるとありがたいんだけど、とりあえず船をつけさせてもらおうか。」
私達は船を桟橋につけて碇を降ろした。辺りに人影は見えない。サクリフィアよりも少し小さな船着場だが、ほかにも船が係留されている。私達の船より大きな船が一艘、もう少し小さな船が2艘。人が住んでいる限り、物資は必要になる。おそらくはサクリフィアあたりから商人達が訪れているのだろう。船着場を降りたところからは森が広がっている。その中に一本、きれいに整備された道が続いていた。
「きれいなところねぇ。」
「サクリフィアの神殿前の森と同じような感じだね。」
「ここもやっぱりあの不思議な力で守られているのかしら。」
「そんな感じはするけど・・・。」
あの森は巫女姫の野営地だったからこそ、あんなふうに守られていたのではないかと思っていた。ではここは何のためにこうして守られているのだろう・・・。
「神様のいる場所へ向かう入口だからなのかな。」
ウィローが言った。
「そういうことになるのかな。でも、今のところ特に違和感は感じないね。」
「そうよね・・・。クラトさんが『得体が知れない』って言うほどの違和感は感じないわね・・・。」
通常なら、初めて足を踏み入れる場所では常に剣の柄に手をかけて、いつでも構えられるようにして慎重に歩を進めたものだ。だがこの森では、なぜか2人とも武器を構える気になれなかった。大きな力に守られていると思えるこの穏やかな場所で、武器に手をかけながら歩くことがとても異様で、また不作法に思えた。
「こんなきれいな場所に住んでいたら、毎日散策するだけでも飽きないかもしれないわ。」
「そうだね。武器を持って歩くのも憚られそうだよ。」
この森の中にいると何となく落ち着く。船の上でのあの重苦しい気持ちが、いつの間にか大分和らいでいた。しばらく歩いていると、女の子が2人でいるのが見えた。まだ若い、と言うより子供のようだ。こんな森の中の道に子供達だけでいるのも不自然に思えたが、この森なら、多分害をなすようなものは出てこないだろう。女の子達が私達に気づいたが、驚く様子も見せず、笑顔で近づいてきた。
「こんにちは。あなた達は・・・何日か前に着いた交易船の人達ではないみたいね。どちらからいらしたの?」
年かさらしい少女が話しかけてきた。にこにこと愛想がいい。交易船が来ると言うことは、ある程度人馴れしているのだろうか。
「こんにちは。私達はここからずっと西の彼方にある、エルバール大陸から来たのよ。ここはムーンシェイの森ね?」
ウィローが笑顔で話しかけた。少女達はエルバールと聞いて少しだけ驚いた顔をしたが、すぐに元の笑顔に戻った。
「遠くからいらしたのね。ええ、ここはムーンシェイの森よ。ここではね、ずっとずっと昔から、人間がありのままで暮らす場所なの。だからこの村には便利なものは何もないわ。でも、とても美しくて素敵なところよ。」
少女は言いながら両手を広げて、風を胸一杯に吸い込み、くるくると踊るようにまわってみせた。もうひとりの少女がくすくすと笑いながらそれを見つめている。
「私達はこの村の長老に会いに来たんだよ。すぐに会えるのかな。」
少女は踊るのをやめ、私達に向き直った。
「あら、長老に会いに来られた方だったのね。そうねぇ・・・長老はね、村の中にはいないの。少し離れたところに住んでいるんだけど、私達もなかなか会えないのよ。」
「そうか・・・。何とか会う方法はないのかな。」
少女達は私の顔をじっと見つめていたが・・・
「それじゃ村に案内するわ。長老はなかなか村に来られないから、長老の代わりにいろいろと相談にのってくれる人がいるの。その人に話してみて。」
「ありがとう。」
私達は森の道で出会った少女達と、村に向かって歩き出した。少女達は人懐っこく、歩きながらいろいろと話しかけてくる。2人は姉妹で、姉の方がアンナ、妹の方がノアと言うのだそうだ。
「君達と同じ年頃の子供達は他にもいるのかい?」
「そんなにいないわ。遊ぶのに困るほどじゃないけどね。」
アンナがそう言って笑い出した。
「この村はね、ずっと昔から、文明を持たないことが最良の生き方であるって言われていたんですって。」
「文明を持たない?」
「ええ、そうよ。遠い昔、人間だけが文明を持って、他の動物達との差別化を図ったの。でもそれは自然に悪い影響を与えたんですって。でも、この森はそんな悪い影響とは無縁だわ。美しい花々、澄みわたる風・・・。私はこの森が好きよ。ここでずっと暮らしていきたいわ。」
「本当にいいところだね。」
「でしょ?」
ノアが私達に向かって得意げに笑ってみせた。
「あら、家の屋根が見えてきたわ。あそこが村の入口?」
ウィローが尋ねた。
「そうよ。」
2人は『早く早く』と私達をせかすように走り出した。そして村の入り口に立って大きく手を振り、
「着いたわよ。ようこそムーンシェイの村へ!」
笑顔で迎えてくれた。が・・・
村に足を踏み入れた瞬間、奇妙な感じがした。何か・・・見えない門を通り抜けたような感覚があったのだ。振り向いてみたが、私の後ろには、たった今まで歩いてきた森からの道が延びている。
[大丈夫よ。悪いものじゃないから。」
「え?」
アンナの言葉にどきりとした。今私が考えたことを、この子は気づいている?
「・・・どうしたの?そんなにびっくりして。」
ノアがきょとんとした顔で私を見ている。
「あ、いや・・・。」
アンナはいたずらっぽい目で私を見て、くすくすと笑った。
「へへへ、お兄さん、今後ろを振り返ったでしょ?この村に最初に入る人はね、みんなそういう反応をするのよ。この村はね、特別な力で守られているんですって。だから村に入った瞬間変な感じがするみたいね。でも、別に村に入ったらあとは出られないなんてことはないのよ。さっきの文明の話だって私達が大人から聞いただけの話だもの。第一、文明と全部縁を切りましょうなんて言ってたら、暮らしていけないって母さんが言ってたわ。」
「まあ確かに、難しいかもしれないね・・・。」
この村の人々はどこから来たのだろう。サクリフィアの人達のようにある程度は人の心を読むことが出来るのだろうか。でも、今はアンナの言葉を信じることにしよう。
『何事も出会う人々の話をよく聞き、助言には耳を傾けて』
『導師』は今までのところ嘘はついていない。彼の言葉を信じて、そしてこの村の人々の善意と真心を信じてみよう・・・。
集落に着くと、この村には思いのほか人がたくさん住んでいることが判った。大きな広場に何人もの村人達が座り込んだりして話をしている。商人達の店も出ている。アンナが言っていた『何日か前に来た交易船の人達』だろうか。いくつか出来ている人々の輪の中に、穏やかそうな老人がいる。周りの人々の話を聞いて、優しげにうなずいている。アンナ達がその老人に近づいていった。
「おじいちゃん、この人達が長老に会いたいんですって。」
振り向いた老人は村人達を見るのと同じ、穏やかな優しい目を私達に向けた。本当にこの人がこの村の長老ではないのだろうかと思うほどだ。
「おお、そうか。よし、ではわしが話を聞こう。ところでアンナ、ノア、お前達母さんの手伝いをしないで森で遊んでいたな?」
アンナとノアは『まずい』と言いたげに肩をすくめた。
「これからでもいいから手伝いに行きなさい。遊んでばかりいるのも、長老はちゃんと見ておられるぞ。」
「はあい、お兄さん達、またね。」
「またね。いろいろとありがとう。」
2人はおしゃべりしながら走っていった。
「さてと・・・。」
老人は私達に向き直り、前に座るように促した。
「よく来なさった。ようこそムーンシェイの村へ。長老に会いたいと言うことだが・・・あの子達から聞いたかも知れんが、長老はこの村の中にはいないのじゃ。わしらとてなかなかお会い出来ぬ。」
「あの、場所を教えていただければ、私達で会いに行きたいのですが・・・。」
「ふぅむ・・・。」
老人は私達をじっと見つめていたが・・・
「うーん、どうしたもんかのぉ。・・・まずは見てもらったほうがいいな。ちょいとあんた方、わしについて来てくれんかね。」
私達は老人について広場から村の外れらしい場所までやってきた。村を囲む森は、かなり鬱蒼としている。
「長老はこの向こう側におられるのだが・・・」
老人は森の向こうを指差した。
「ということは、ここを通り抜けないと行けないわけですね・・・。」
森の木々はびっしりと生えている。これでは人間どころか、動物だってこの森を超えていくことは出来ないだろう。
「うむ。我らも長老に会えるのは年に何回かあるかどうかというところじゃ。この森はな、意思を持っておる。それは長老の意思と繋がっていて、長老が誰かを招き入れる時だけ木々が動いて道が出来るのじゃよ。」
「それじゃ私達が会いたいと思っても・・・。」
「そうなんじゃよ。わしらとて、別にあんた方を長老に会わせたくないなどと考えているわけではない。ただこの通り、長老の元にたどり着くためにはこの森を越えていく以外にないのじゃ。そしてこの森を越えていくためには、長老が道を開いてくださらなければならん。ところで、あんた方が長老に会いにこられた理由は何かね。わしは長老の代わりにこの村でのさまざまなことについて相談役を仰せつかっておる。無論、わしには長老と同じ力はないのだが、話くらいは聞かせてもらえるとありがたいのぉ。」
『長老と同じ力はない』
つまり、長老は何か特別な力を持った人物だということか・・・。確かにそうなんだろう。でなければ森の木々を自分の意思で動かすなんてことが出来るはずがない。
『何事も出会う人々の話をよく聞き、助言には耳を傾けて』
『導師』の言葉がまた浮かぶ。目の前の穏やかな老人からは、私達に対するいたわりの気持ちが伝わってくる。
「わかりました。お話したいのですが、ここでは・・・。」
周りには村人がたくさんいる。
「そうじゃな・・・。わしの家に来なさらんか。そこで少し話を聞かせてくれるかの。」
私達は老人の家に付いていった。
「おーい、お客様じゃ。茶を3人分用意してくれ。」
老人は家に着くと、奥に向かって大声で叫んだ。そして声に応えて『はーい、ただいま』と女性の声が聞こえた。
「さて、座ってくださらんか。」
家の中は簡素で、とても落ち着ける。運ばれてきたお茶を勧められて一口飲んだ。とても優しい味がした。
「おいしい・・・。」
ウィローが言った。
「おいしいし、ホッとする味だね。」
「そうね・・・。」
「そりゃよかった。お、まだ名も名乗っておらんかったな。これは失礼した。わしはグランという。さっきも言ったように、長老の代わりに村の中のいろいろなことを任されておる。こんな小さな村じゃからな。何とか長老の手を煩わせずにすむ程度の役割は果たしておると自負しておる。」
私達は名を名乗り、今までの事情を話した。
「なるほどなあ・・・。」
おじいさんは腕を組み、考え込んでいる。思い切って『聖戦竜』や『サクリフィアの錫杖』の話もしてしまったのだが、そういうことについても、特に驚いている様子がない。
「しかし困ったのぉ・・・。そこまで重大な話となれば、当然長老だって聞き及んでいるはずじゃがなあ。そうだなあ・・・。あんた方、仲間があとから来ると言うておったな。ならば、その仲間が追いついてくるまで、この村に滞在してはどうじゃ?」
「え、でも・・・。」
思わず口ごもった。カインが追い付いてくるまであと何日かかるかはわからないが、その間私達がのんびりこの村で過ごしていたら、カインに会うなり呆れられそうだ・・・。私の戸惑いを見透かしたかのように、おじいさんは微笑んだ。
「まあ事情が事情だ。あんた方が焦る気持ちはよくわかる。だがあまり急いでいると大事なことを見落としかねん。少しのんびりすることが必要な時もあるものだ。ちょうど今交易船も村に来ておるから、商人達がバザールを開いておるのだよ。年寄りはうるさがっておるが、若い者達は喜んでおる。まあこんな小さな村じゃから賑やかな酒場などはないが、宿屋もあるんじゃよ。あとで誰かに案内させよう。ところで、あんた方サクリフィアの船着場から来たそうだが、ここに来る途中、北にある氷壁は見たかね?」
「はい、船からですけど。」
「おお、そうか。この森の北には長老が住んでおられるが、そこから先がクリスタルミアと言うて、あんた方がこれから行こうとしている場所だ。神々が住まうと言われる神話の地じゃよ。そのクリスタルミアの奥に、飛竜エル・バールが眠っておる。」
「ではこの村の長老はクリスタルミアの入口にお住まいなんですね。」
「うむ。このクリスタルミアにはちょっとした伝説があってな。この地に入り込んだ者は、そこに住む精霊によって試練を与えられるそうじゃ。そしてその試練を見事くぐり抜けた者には、伝説の武具を貸し与えると伝えられておる。」
「精霊・・・ですか・・・。」
ここでも精霊か・・・。サクリフィアの神殿で声だけが聞こえてきた、あの精霊達とはまた違うのだろうか・・・。
「ん?なんだか精霊に会ったことがあるような口ぶりじゃな。」
「実は・・・。」
私はさっき話した時に意図的に隠した自分の剣のことについて、話してしまった。だがそれでもおじいさんは驚く様子を見せず、感心したようにうなずいている。
「なるほど。そういうことじゃったのか・・・。長老の意図が読めたぞ。」
「・・・え?」
「試練はもう始まっているという事じゃ。あんた方がこの村に着いたことを、長老はおそらくすでにご存じだろう。あとは、あんた方が長老に招き入れられるよう、この試練をくぐり抜けなければならんのじゃよ。」
「それは・・・でもどうすれば・・・。」
「ま、さすがにわしにもそれはわからん。まあしばらく滞在してみてはどうかね。先ほどの話では随分と大変な旅をしてこられたようだし、この村で少しのんびりして、お仲間の到着を待つというのも一つの手かもしれんぞ。」
確かに、それしかないのかもしれない。長老が私達を招いてくれる条件が何なのか、さっぱりわからないのだ。少し落ち着いて考えてみる必要がありそうだ。それに、カインが追いついてくれば、きっとまたいい知恵も浮かぶ。
(『まったくもう、何のんびりしてるんだよ』なんて言われるくらいは覚悟するか・・・。でもさすがに何もしないでいるってわけにも・・・。)
「ちわー、グランじいさん、いるかい?」
玄関の方から若い男性の声がした。
「おお、いるぞ。こっちじゃ。」
グランおじいさんの声に応えて、私達のいる部屋に男性が顔を出した。
「アンナとノアから聞いたんだが、お客さんが来てるって話じゃないか。」
「耳が早いのぉ。まったくお前は油断がならん。」
「あったり前だよ。商売ってのは速さが大事なんだ。」
「ま、それは客人の決めることじゃ。あんた方、クロービス殿とウィロー殿だったな。この男はリガロと言って、町の宿屋を経営しておる。簡素だが居心地の良さはわしも保証しよう。しばらく滞在するのなら、こいつの宿屋は安全だぞ。」
「そういうわけなんだが、俺の宿に泊まってくれるかい?この通りの小さな村じゃ、客はせいぜい交易船の商人や、あとはクリスタルミアに冒険に行こうなんて言う無謀な冒険者程度しかいないから、客集めは大変なんだよ。泊まってくれるならサービスするぜ!」
「わかりました。お世話になります。」
「よっしゃ!それじゃ宿に案内するよ。」
「そうだな。今日は宿でゆっくりするのもいいのではないか。わしはたいていさっきの広場で日向ぼっこしておるからの。いつでも話しに来てくれていいぞ。」
「ありがとうございます。」