翌朝、フロアで食事をしようと私達は1階に下りてカウンターに座っていた。厨房ではロージーとミーファが食事を作ってくれている。
「おはようございまあす!荷物があるんですが、どこに運びましょうか!」
声とともに扉が開いた。厨房の奥からミーファが出てくる。
「あらご苦労さま。いつも荷物は裏口からってお願いしてるのに、今日はどうしたの?」
顔見知りの運送屋らしい。
「いえ、今日のはこちらの宿屋宛じゃなくて、お客さん宛なんですよ。確認をお願いします。」
運送屋の男性は背負っていた荷物を降ろし、伝票をミーファに見せた。ミーファは宛名を見て頷き、
「それじゃそこに置いておいて。お客様にはあとでお渡ししますから。」
そう言って置く場所を指さした。
「わかりました。それじゃ毎度ありがとうございました。」
「ご苦労様。」
運送屋は笑顔で出て行った。
「さてと、はいお客様、お荷物が届いております。」
ミーファがいたずらっぽく笑いながら、荷物を指し示した。
「私宛かい?」
「ええそうよ。でもちょっと重そうね。運ばせましょうか?」
大きさはそれほどでもないが、少しずしりとした感じに見える。
「いや、このくらいなら持って行くよ。」
私は荷物を持ち上げて、部屋に戻った。確かに重い。送り主はグレイになっているが、私がブロムおじさん宛てに手紙を送ってから数日過ぎる。もしかしたら返事が入っているかも知れない。今すぐに開けて中を確かめたかったが、まずはゆっくりと食事をしよう。そう決めて、もう一度下に降りた。気持ちがはやる時ほど、冷静になれる時間を作らなければならない。
「誰から?」
妻が尋ねた。
「グレイからだったよ。案内書が送り返されてきていないといいけどな。」
「そうねぇ。使わなくなったから返してくれなんてことになってないといいわね。」
妻もきっと、ブロムおじさんからの返事を期待している。でも聞くに聞けない。他に客がいないとは言え、こんな場所で患者の話をするわけには行かないのだ。私達は当たり障りのない会話をしながら、食事を終えてすぐに部屋に戻った。届いた荷物を開けると、中から出てきたのは・・・
「うわあ、これは・・・。」
何冊もの分厚い医学書が入っていて、そのところどころにしおりが挟んである。そして手紙・・・。
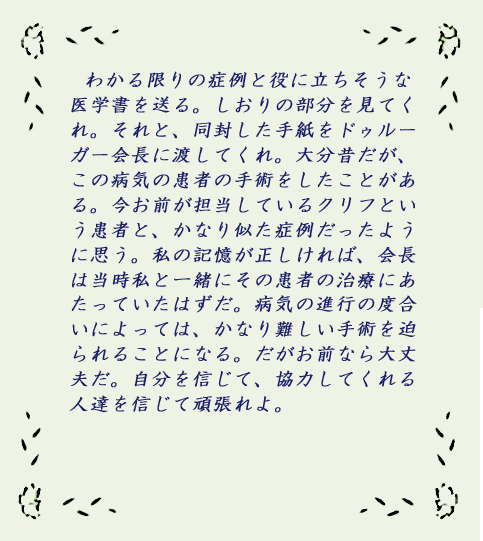
「手紙と言うより、メモだな。おじさんらしいや。」
励ましの言葉が胸にしみる。何としても成功させなければならない。中に書かれているドゥルーガー会長宛の手紙のほうは、きちんと封筒に入れて封をしてある。さすがに会長宛に走り書きのメモとは行かないのだろう。
「こっちはグレイの字ね。・・・こっちもメモだわ。急いで送るのに、長い手紙を書いている時間がなかったのね、きっと。」
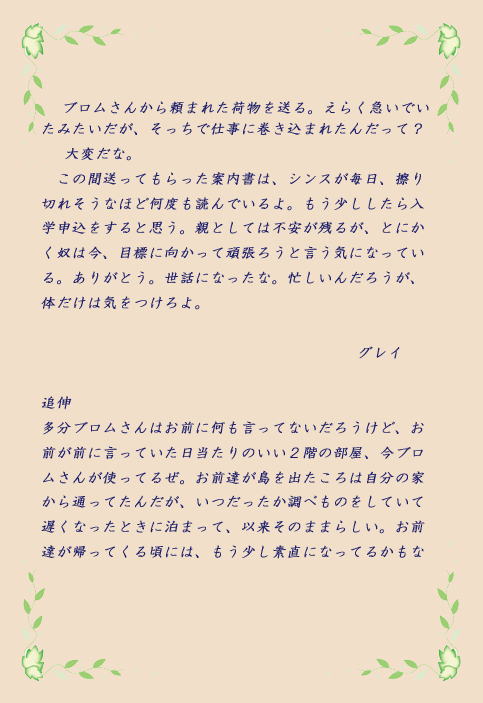
「へぇ・・・使ってくれてるんだ、あの部屋。」
私達は出来ればブロムおじさんと一緒に暮らしたいと思っている。2階にある日当たりのいい部屋をおじさんの部屋として使ってもらえるよう、ずっと前から言っているのだが、どうしてもうんと言ってくれなかった。島を出る前『お試しってことでいいから使ってみて』と言ったのだが、どうやら使ってくれているらしい。私達が帰るころには、やっと一緒に暮らすことができるようになるかもしれない。
「そうなるといいわね。いくらお元気だといっても、暗くなってから帰るのを見送るたびに心配してたのよ。」
診療所の仕事が、毎日決まった時間に終わるとは限らない。夜中まで診療にあたることもある。そんな日でもおじさんはなかなかうちに泊ってくれない。真っ暗な道におじさんを送り出した後は、妻も私も、いつもとても不安だった。
「そうだね。帰ったらさっそく話を進めなきゃね。それにシンスも頑張ってるようだし、一安心かな。」
「そうね。でも大丈夫なのかしら。案内書を熟読するのは悪いことじゃないけど、実際の学校生活は甘くないってちゃんとわかってくれているといいけど。」
確かにノルティから話を聞いた限りでも、かなり厳しい世界だと言うことはわかる。
「それもそうか・・・。もしも本格的に入学ってことになったら、その時本人と話してみたほうがいいかもしれないな。実際の学生さんから聞いた話ってことで。」
「そうね。それじゃ、私達はまずこの荷物を何とかしましょ。そんなに急いで送ってくれたってことは、当てに出来る情報があると思っていいわよね。」
私は箱の中の医学書を全部引っ張り出し、開いて中を確認した。これなら一日もあれば要点をまとめて治療方針が立てられるが、ここで引きこもっているわけには行かない。
「ウィロー、ちょっと重いけど、これを全部持っていくよ。会議室でも借りて、クリフの治療方針を立てよう。」
「わかった。手伝うわ。」
箱ごと担いでいくわけにもいかないので、私達は背負い袋に医学書を手分けして詰め込み、今までに集めたデイランド先生の資料、デンゼル先生のノートなど、クリフの手術方針に役立ちそうなものを全部持って部屋を出た。こんな大荷物を持って王宮に行ったことなどなかったので、なんだかとても場違いな気分になる。王宮の玄関を警備する王国剣士、ロビーの案内係の娘はいつものように笑顔で挨拶してくれたが、みんな一様に『おや?』という顔をするのだった。
「どうなさったんです?そんな荷物を背負って。」
ハインツ先生は驚いて私達を見た。私は事情を話し、手術がいつになるにせよ、まずは治療の方針と手術の手順について確認したいと言った。
「会議室が空いていればそちらをお借りしたいのですが、どうですか?」
「あ、会議室ですか・・・。今日は朝から使用予定があるんですよ。そうですねぇ・・・。」
ハインツ先生はしばらく思案していたが・・・
「では会長にお願いしてみてはいかがですか。そのくらいの融通は利かせてくれると思いますよ。」
「わかりました。では行って来ます。」
妻はもうクリフの状態をゴード先生と打ち合わせ始めている。病室を出たが、さっきのハインツ先生の思案がどうにも気になった。
「言おうかどうしようかって迷ってたみたいだったな・・・。」
場所を借りるのにドゥルーガー会長に頼む、これは別に遠慮するほどのことじゃないと思う。ハインツ先生ならなおさら遠慮なんてしないだろう。
「まあいいか。しかし、やっぱり重いな。」
病室に医学書の山を置いてくるわけにも行かなかったので、妻が持ってきた分まで全部持って出てきた。部屋を借りられたらまっすぐそこに行って、すぐに仕事を始めたい。
会長室についた。ドゥルーガー会長は大荷物を抱えた私を見て目を丸くしたが、笑顔で中に入れてくれた。私はまず事情を説明し、ブロムおじさんから預かった手紙をドゥルーガー会長に渡した。
「うーむ・・・そういえば・・・あまり昔のことなのではっきりと覚えておらぬが、ブロムのほうが記憶は確かだろう。後で記録を届けよう。」
「お願いします。あともう一つお願いがあるのですが・・・。」
私はここに持ち込んだ大量の医学書や、今まで集まった資料を使ってクリフの治療方針、そして手術の進め方についても方針をまとめたいので、どこかの部屋を借りられないかと頼み込んだ。不思議なことに、ドゥルーガー会長もまた、言おうかどうしようかと迷っているような思案をしている。そして・・・。
「・・・うむ、あいわかった。では貴公がクリフの手術に臨む間、自由に使える部屋を用意しよう。ついて来てくれぬか。」
ドゥルーガー会長に促され、私はもう一度荷物を担ぎ上げ、会長の後をついていった。
「ここだ。」
案内されたそこは・・・
「ここは、研究棟ですね?」
医師会の医師達がそれぞれの研究のために持っている部屋が集まっている場所、それが研究棟だ。おそらく昔、父もここにいたはずだ。その最上階にある部屋の扉を開けて、ドゥルーガー会長は私を中に招き入れた。
「うむ、全てではないが、ほとんどの医師はここに部屋を持ち、それぞれの研究を続けている。この部屋を使ってくれぬか。必要なものは全て揃っているだろう。」
「それはありがたいですが、普段ここはどなたかが使っておられるのではありませんか?」
中には机、書架、研究についての書物、助手の机も二つ、そして立派な応接用の椅子とテーブルまである。実験に使いそうなこまごました備品も、ガラス戸がはまった戸棚の中に入っている。研究テーマにもよるかも知れないが、ここに来ればすぐにでも仕事が出来るだろう。そのくらい設備が整っている。
「・・・ふん、ハインツが貴公に私を頼れと言ったのは、おそらくさっさと白状しろと言うことなのだろう。クロービス殿、実はこの部屋は、貴公がこちらに出てきて主席医師として赴任した時のために、用意した部屋なのだ。」
「・・・え・・・?」
思いがけない話に驚いた。
「・・・少し座らんかね。実を言うと、私はもう少し貴公に話さなければならないことがある。」
私は荷物を降ろし、立派な応接用の椅子に、会長と向かい合って座った。
「・・・昔、貴公が故郷に帰ってしばらくした頃、私はブロムからの手紙を受け取った。若い医師を育てたい、そのためにもう一度医師として仕事をしてもいいだろうかと言うその内容に、私は心から嬉しかった。だが・・・。」
ドゥルーガー会長は一度言葉を切ってため息をついた。
「その『若い医師』が、つい先日まで救国の英雄としてフロリア様との婚儀を取りざたされていた王国剣士であると知って、私は・・・落胆したのだ。」
「・・・やはり私が素人だったからでしょうか。」
「いや、そうではない。最初に医師を志した時、私だって素人だった。はっきり言うてしまうが、私が落胆したのは、王国剣士だった貴公に医師としての才があるとは思えなかったからだ。」
「・・・・・・・・。」
「貴公は王国剣士として、類い希なる才能を備えていると、私は思っておった。もしあの時、貴公がフロリア様と結婚して大公の座に座ると聞いたなら、私は貴公の大公としての器に対して疑問を持つことなどなかっただろう。しかし・・・その英雄が剣を置き、しかもまったく畑違いの医師の道に進むなど、そんなことが可能なのか、無謀でしかないのではないかと考えたのだ。無論、父上の後を継ぎたいというその気持ちは理解できたが・・・。」
あのころ・・・もしかしたらみんなそう思っていたかもしれないと、考えたことはある。王国剣士が医者になどなれるのかと、何の知識もないのにと。風邪に効く薬草茶を作るのとはわけが違う。表面では『がんばれよ』と言ってくれていても、誰もが心の中では『無理だろうな』と思っていたのではないかと・・・。
「ブロムは麻酔薬の開発を再開したいという話も手紙に書いておった。私はなおさら落胆した。サミル殿の人となりはそれほど知っていたわけではないが、医師会を辞めさせられたあとも研究を続けていたとブロムの手紙には書いてあった。あの逆境にもへこたれず研究を続けようとした、その不屈の精神は敬服に値する。もしこれが、ブロムがサミル殿の遺志を継ぐという話だったなら、私は心から応援した。今度こそ麻酔薬が完成するかも知れないと期待もしただろう。しかしいかにその子息とは言え、ついこの間まで医師とは何の関係もない職業に就いていた貴公が果たしてどこまでやれるのか、不安ばかりが先に立っていた・・・。」
「それは・・・仕方のないことだと思います。」
王国剣士としてここにいたころ、私は医師の仕事など何も知らなかった。せいぜい父から受け継いだレシピを元に薬草を組み合わせることは出来ていた、その程度だ。そんな人間が医者になる、しかも麻酔薬を完成させる、医師としてそれがどれほどの苦労かを知っていたドゥルーガー会長には、私に期待できる理由など何一つ見つからなかったのではないだろうか。私が逆の立場だったらやはりそう考えただろう。
「ブロムの希望通りの医学書や臨床例などの資料を送る時、実は私はブロムに直接その話を手紙で書いておる。無論ブロムは貴公にそのような話は一切していないであろうがな。その時ブロムから届いた返事には『彼は毎日必死で勉強をし、砂地に水が染みこむがごとくに知識を身につけている。私は彼を信じている。もしも麻酔薬が完成した暁には、彼の名で報告書を送るので、ぜひ今後の治療に役立ててほしい。』と書いてあった。そしてその手紙の通りに麻酔薬は完成し、報告書が送られてきた。あの時の喜び・・・遠い昔、不当な圧力で無念の涙を飲んだ誰もが、あの報告書に歓喜したのだ。私は貴公の力を低く見ていたことを心から恥じた。そして貴公を医師会に迎えたいと、レイナック殿とフロリア様に願い出たのだ。そこでこの部屋を用意し、貴公がこちらに出てこられたらすぐにでも優秀な助手の手配をするつもりでいたが・・・。」
「私のことを・・・そこまで・・・。」
「しかし、その話をブロムに手紙で送ったところ、おそらく彼はその申し出を受けることはないだろうと言う返事が来ていた。だから、まあこの部屋は使うかも知れなかったし、使わないかも知れなかった。だが私はなかなかこの部屋を別な医師に使わせるのがためらわれてなあ・・・。今までそのままになっていたというわけだ。貴公が医師会に入るつもりはないということはわかっておるが、クリフの手術についてはある程度ゆっくりと考えたり、治療方針を組み立てたりする静かな部屋は必要だろう。その間だけでもここを使ってくれぬか。」
「わかりました。ありがたく使わせていただきます。」
ドゥルーガー会長はほっとしたようにため息をついて、微笑んだ。
「ふう・・・肩の荷が一つ降りた思いだ。貴公が麻酔薬の開発を北の果ての島で再開したと言う話をハインツにした時、ハインツは『クロービスさんならきっとやり遂げますよ』と言っていたのだが、私は貴公とハインツが知り合いであることも知っておったから、ハインツの贔屓目ではないかと疑っておったのだ。あやつめ、麻酔薬関係の報告書が届いた時、なんと言ったと思う?『会長、もう少しいいメガネを買われたほうがいいのではありませんか』だ。・・・あやつはおそらくこの医師会の中で、誰よりも貴公の成功を信じていた。見る目がなかったのは私のほうだな・・・。」
「・・・・・・・・。」
「ところが、貴公があの若い剣士を背負ってここに来た時、思いもかけず貴公と会う機会が出来た。そうしたら今度は医師会の長としての意地のようなものが頭をもたげてきてな・・・。今さらここを頼るつもりなら腕を試すくらいのことはしてもいいだろうなどと、つい考えてしまった・・・。」
言い終えて、ドゥルーガー会長はなんとなく満足したような笑みを浮かべて、ソファにもたれかかった。
「ふふふ・・・腹にためておくのはよくないな・・・。しかし、つまらぬ話を聞かせてしまってすまんな。ここは自由に使ってくれていいし、助手が必要なら手配しよう。そのほか必要なものがあったら何なりと言ってくれてかまわぬ。遠慮はしないでくれ。」
「はい、いろいろとありがとうございます。」
私は深く頭を下げた。どんなに感謝してもしたりないくらい、私はこの方に世話になっていたのだ・・・。
「さて、少し部屋の中について説明しよう。出来るだけ必要なものは揃えたつもりだが・・・。」
ドゥルーガー会長は部屋の鍵を渡してくれて、どんな備品が置かれているかについて説明してくれた。私のために用意された部屋なだけあって、おそらくすぐにでも本格的な研究が始められるだろう、そう思わせるくらい、至れり尽くせりのいろいろなものが揃っている。その中で、私は書架に置かれた本に目を留めた。
「・・・薬草学の本がかなり多彩ですね。読んでいるだけでも勉強になりそうです。」
書架の中には医学書がずらりと並んでいる。最新の本と言うわけではないが、若い医師が勉強するための書物は揃っていると思っていい。その中でも薬草学の本は何冊もあり、中にはハインツ先生の著書もあった。実はこの本は私も持っている。基礎知識から応用まで、実にわかりやすく解説してあって、ちょっとした調べものには実に重宝している。
「まあここに用意した本は、貴公が麻酔薬を最初に完成させた時のものだからな。今となっては古くなっておるかも知れぬ。薬草学の本は、時々ハインツが『いい本が手に入った』と持ってきて置いたものだ。ちゃっかり自分の著書まで置いておくとは、ハインツらしいな。」
「ははは、でもとてもわかりやすい本ですよ。薬草学についてこれだけの書物が揃っているなら、オーリスとライロフにここを使って薬の組み立てをしてもらうようにしましょうか。あの2人は今どこで仕事をしているんですか?」
「あの2人なら、薬草庫に行ったりハインツの部屋を借りたりしておるようだな。ふむ・・・ここで仕事が出来るならちょうどいいかもしれん。ここはクリフの手術が終わるまで、貴公の部屋だ。彼らに声をかけてみてくれぬか。」
「わかりました。それではさっそくここを使わせていただきます。」
私はさっき机の上においた、医学書などの荷物を開いた。
「随分とまた大量の荷物だな。これが全部ブロムから送られたものか?」
「それと、デンゼル先生から預かった資料などもありますよ。私が今集められるかぎりの資料を集めました。」
「では私はブロムに頼まれた資料を急ぎ用意しよう。おお、そうだ。オーリス達に届けさせよう。その時にでも話してみてくれぬか。」
「はい、よろしくお願いします。」
さっそく資料のまとめに取り掛かった。今までの治療記録はもう頭に入っている。手術の役に立ちそうな記録を資料の中から探し出してメモする。おじさんがしおりを挟んでくれた箇所は、なるほど役に立つものばかりだ。
・・・どのくらい過ぎただろう、扉をノックする音で我に返った。
「オーリスですが、クロービス先生はいらっしゃいますか。」
「開いてるよ、どうぞ。」
扉が開いて、オーリスが顔を出し、続いてライロフが顔を出した。2人とも中に入ってこようとしない。
「どうしたんだい?」
「い・・・いやあの・・・なんだかこの部屋はすごいなって・・・。」
「ははは、私もさっき初めて来た時は驚いたよ。さあ入って。ドゥルーガー会長から何か資料を預かってきてくれたと思うけど。」
「あ、そうです。これです。」
オーリスが分厚いファイルを差し出した。何ヶ所かにしおりが挟んである。
「ありがとう。君達は今どこで仕事をしているんだい?」
「僕達はハインツ先生の部屋や、会議室を借りたりしています。患者の前で使う薬の議論というわけに行かないので、病室では出来ませんし。」
「そうか。でもハインツ先生の部屋には助手が何人かいるし、会議室も今日のように使用予定が入っていれば使えないだろうね。そこで提案があるんだ。君達、この部屋を仕事場にする気はないかい?」
「ええ!?僕らがですか!?」
2人はほぼ同時に声をあげた。
「私はこの部屋をクリフの手術が終わるまでの間借りているだけだから、ずっとというわけには行かないけどね。どうだろう。薬草学の本はここにはたくさんあるし、クリフの治療方針や手術手順の組立も私はここで作るつもりなんだ。ハインツ先生の書いた本もあるから、環境としては充分だと思うんだけどな。どうだろう?」
「はい、ぜひお願いします。」
「僕もここで仕事が出来るならありがたいです。よろしくお願いします。」
2人はさっそく仕事の資料をここに持ってくると言って部屋を出て行った。私はまた資料をめくり始め、クリフの治療手順を書き出していった。
「失礼します。」
再び声が聞こえ、思考が途切れた。オーリスとライロフが戻ってきたらしい。
「どうぞ、こちらです。」
2人が入口で誰かに声をかけ、『ありがとう』と聞こえた。この声は・・・。
「すごい部屋ねぇ。でも静かに考え事をするのには向いていそうだわ。」
2人に促されて入ってきたのは妻だった。部屋を見渡して感心したようにうなずいている。
「設備は調ってるよ。さすがに医師会だなあって、さっき私も感心していたところなんだ。クリフのほうはどう?」
「さっき少し痛みが出たわよ。ちょうどドゥルーガー会長がいらっしゃった時。それで、午後から手術の日程について話し合いたいから、会長室に来てくれないかって。」
「そうか。それじゃいよいよだね。」
その痛みの正体が気になる。今机の上にある資料の中に、手がかりはあるだろうか。
「ええ、それから、ローランド卿が迎えに来てるわ。ロビーで待っているから支度が出来たら来てくださいって。」
「あ、もうそんな時間なのか。」
部屋の壁にかけられた時計を見上げると、お昼近くになっていた。
「それじゃ行こうか、待たせちゃ悪いし。」
私はオーリスとライロフに出かけてくることを伝え、部屋の中の備品は自由に使ってくれと伝えた。
「ただし、食事もしないで仕事はやめてくれるかい。自分の健康管理が出来ないと、肝心な時に患者の役に立てないなんてことになるからね。」
医者はどうしても自分のことを後回しにしやすい。私も以前大きな手術の前に緊張しすぎて、食事もろくに摂らずに手順の組み立てや薬の準備をしていたら、ブロムおじさんに怒られた。
『お前が今無理して倒れたら、或いは執刀に影響が出そうなほど疲れていたら、それは患者の命を危険にさらすことになるんだぞ。寝不足で青い顔をしていたら、患者の家族だって不安になる。食事を摂って今日はゆっくり眠れ。』
そのあと、我が意を得たりとばかりに妻が私を煽り立て、食事をしてひと眠りしたおかげで、万全の体制で手術に臨むことが出来た。それ以来どんなに忙しい時でもきちんと食事をして睡眠をとることにしている。この2人も手術の薬の管理で相当緊張しているが、肝心の手術当日に倒れられたのでは今までの準備が無駄になってしまう。
「わかりました。」
さてどこまでわかってくれたか。2人を取り巻く『気』は相変わらずピンと張りつめている。
部屋を出てロビーに向かって歩き出した。
「研究棟は初めて入ったわ。やっぱりちょっと独特の雰囲気ね。」
「そうだね。ハインツ先生もマレック先生もここには部屋を持っていないから、来る機会もなかったしなあ。」
ハインツ先生の部屋は薬草庫の隣だし、マレック先生の部屋は医師会の厨房の近くにある。研究の内容に一番則した場所にあるのは確かなのだが、あの2人の性格からして、研究棟が窮屈に感じているのではないか、そんなことを考えた。
「クロービス先生、お待ちしておりました。」
ロビーにはローランド卿が一人でいた。待たせてあった馬車に乗り込み、私達はカルディナ家の屋敷へと向かった。遠い昔、怒りに任せて走った道を、今ゆっくりと馬車で行く。不思議な気分だ。
「今日は昨日のような大げさな出迎えはありませんのでご安心を。」
ローランド卿が笑いながら言った。
「ははは、それはありがたいですね。」
やがて馬車はカルディナ家の屋敷の前に着いた。前日のような大きな声での開門はなく、私達は馬車を降り、ローランド卿に案内されて門の中に入った。前に来た時には屋敷を見あげる余裕などなかったが、こうして見ると落ち着いたいい雰囲気の建物だ。
「さあどうぞ。お入りください。」
ローランド卿に促され、中に入った。なんだろう・・・。以前来た時にはとても暗く感じたのだが、今日はとても明るい。気のせいだろうか・・・。
「簡単な食事会ですが、我が家の家督を相続した養子夫婦も同席させていただきます。」
「ローランド卿の弟さんご夫婦になるわけですね。」
「ええ、真面目で穏やかな夫婦ですよ。父の従弟の子供ですので、血縁としては大分遠いんですけどね。」
その跡取り夫婦は食事会の会場で出迎えてくれた。2人ともなるほど穏やかで優しい雰囲気の人達で、真面目そうだ。そしてその隣にいたのは・・・
「ようこそ我が家へ。ご無沙汰しておりました。」
トーマス卿・・・確かにそうなのだが、以前会った時と雰囲気が全然違う。柔和な笑みを浮かべた、優しい老人だ。以前のような油断のならない笑みはないし、纏っている『気』はとても穏やかだ・・・。
「本日はお招きありがとうございます。」
「いや、本来ならばこちらから出向くべきところを、ここまでご足労くださり、ありがとうございます。たいしたおもてなしは出来ませんが、どうぞ、お寛ぎください。」
以前会った時のような威圧的な態度もまったく感じられない。同じ人物とは思えないくらいだ。
「さあ、それではどうぞお召し上がりください。」
テーブルについて、料理が並べられた。食事もとてもおいしかった。
「おいしい。前と同じ味よ。シェフは変わっていないのね。」
昨日のベルスタイン家の晩餐とはまた違った味の組み合わせだ。どちらがどうと言うことではなく、これだけのおいしいものを毎日作っているということは、そのシェフにとってこの家がやりがいのある職場であると言うことなんじゃないだろうか。家の中の雰囲気も穏やかだし、これならカルディナ家は今後も末永く続いていくのではないか、そんなふうに感じた。
食事が終わり、お茶とデザートが出された。かわいらしいケーキだ。食事の間はとても和やかで、跡取り夫婦もローランド卿も、そしてトーマス卿も終始笑顔だった。もちろん私達も楽しかった。
「さて、クロービス殿、ウィロー殿、いかがでしたかな。さすがにベルスタイン家のシェフには及ばないかも知れぬが、我が家のシェフはなかなかの腕でしてな、よろしければぜひご感想をお聞かせ願いたいのだが。」
トーマス卿に尋ねられ、私達は思ったとおりのことを話した。とてもおいしかったと。
「そうですか。ありがとうございます。ではここで少々お2人にお時間をいただきたいのですが、よろしいですかな。」
「はい、まだ時間はありますから。」
トーマス卿は笑顔でうなずき、立ち上がって私達の前に進み出た。
「随分と間があいてしまったが、私はお二人に謝らなければならん。ウィロー殿、クロービス殿、大変申し訳なかった。この通り、今さらではありますが、謝らせてください。」
トーマス卿はそう言って深く頭を下げた。妻は穏やかな笑みでその姿を見ていたが、やがて立ち上がり、トーマス卿の肩にそっと手をかけた。
「トーマス卿のお気持ち、確かに受け取りました。さあ、お顔をあげてください。」
トーマス卿はうなずいて席に戻り、背筋を伸ばして私達を見た。
「さて、それではお二人とも、私に言いたいことは山ほどおありでしょう。せっかくおいでいただいたのだ、どんな恨み言でもお聞きしますぞ。さあ、何なりと。」
表情は穏やかなままだが、トーマス卿を包む『気』がピンと張りつめた。どんな非難の言葉も受け止める、トーマス卿の固い決意を感じる。
「トーマス卿、私は今日、恨み言を申し上げるためにわざわざ伺ったのではありません。もうこのことは今日で全て終わりにしてしまおう、そう思ったからです。そして今、トーマス卿のお気持ちを受け取りました。私にはもうトーマス卿を責めたり、恨むような気持ちはありません。もちろん・・・当時は腹が立ちましたし、城下町に出てくるまではトーマス卿にもローランド卿にもお会いしたくはないと思っていましたけど・・・」
妻は言葉を切って微笑んだ。
「そんな子供じみたことを考えていた自分が、本当に情けないです。でも一つだけ、トーマス卿にお伺いしたいことがあります。」
「どんなことでもお答えしますぞ。いまさら隠し立てはせぬ。」
「私はあの時、ここでお食事をいただいているうちにものすごく眠くなってしまって、そのあとクロービスと顔を合わせるまで自分に何が起きたのかがまったくわからないのです。ですから、あの時なぜあんなことになったのか、何がどうなったのか、それを聞かせていただくことは出来ませんか?」
トーマス卿がうなずいた。
「もちろんです。包み隠さずお話しさせていただこう。だが・・・そうですな・・・ではいささか遠回りになるかもしれぬが、あの頃の政治情勢から聞いていただこう。」
トーマス卿は宙を見つめ、遠い目をしながら話し出した。
「あの当時・・・王宮に戻ってきた剣士団が、非合法の立場のまま国の治安回復の為に奔走していたころ、御前会議では剣士団を復活させるか否かという議題で激論が交わされていたものだが・・・その議論の裏側で、また違った争い事が起きていたのです・・・。」
フロリア様は一時期人が変わったように苛烈な政治を行われたが、王国剣士団の王宮奪還の後、以前と同じお優しいフロリア様に戻られた。しかし、元に戻ったからまた元のように国王としてこの国を任せていいものか、不安に思っていたのは私だけではないだろう。だがそれを表だって口にすることはさすがに憚られる。そこである大臣がこんな『提案』をした。
『いったんフロリア様には退位していただき、エリスティ公に中継ぎとして即位していただいてはどうか』
もちろん『中継ぎ』なので、フロリア様に然るべき夫を迎えて子供が生まれたら、今度はエリスティ公に退位していただき、フロリア様が再び王位に就く、そしてその子を王太子として、成長したら王位を譲る、その大臣達にとってはかなり『いい考え』だったようだ。フロリア様を擁するレイナック殿は当然これに猛反対したが、勢いづいたのはエリスティ公の一派だった。ここに至って、またしても王位をめぐる争奪戦が始まったのだ・・・。フロリア様にこのまま在位していただくか、エリスティ公に新しい国王になっていただくか、大臣達のみならず王国中の貴族達はどちらかにつかなければならなかった。もちろん強制されるわけではないが、あの時、日和見を決め込んでどっちつかずの立場になどいられる状況ではなかった。誰もが『より有利な側に』つこうと様子を伺いながら、どちらについても喜ばれる『手土産』を用意しようと策謀をめぐらしていたのだが・・・。その時『救国の英雄をフロリア様の夫に迎えてはどうか』と言い出した者がいた。それが以前からエリスティ公の一派だったアルテナ卿だったのだ・・・。
トーマス卿はいったん言葉を切り、小さくため息をついて言葉をつづけた。
「『してやられた!』、あの時私はそう考えた。だが、アルテナ卿はその『救国の英雄』の同意を取り付けたわけではなく、彼ならば申し分ないだろうから考えてみてはいかがですかと、フロリア様とレイナック殿に進言しただけだったらしい。となれば私にも勝機はある。そこでほかの大臣に出し抜かれてなるものかと、アルテナ卿の真意を探るべく密偵を放ったのだが、その密偵の報告によると、エリスティ公からアルテナ卿に、こんな指示が出ていたらしい。」
『フロリアに男をあてがってやれ。あの小娘を骨抜きにするような飛び切りの男をな。』
「エリスティ公にとって、今回の話は願ってもない話。中継ぎなどと言われていても、国王になってしまえばどうとでもなる。とは言え、あまり表だって約束を違えたのではまた批判も起きるだろう。そこで公も、多少は考えたというわけですな。」
「・・・それでアルテナ卿が私の名前を出したというわけなんですね・・・。」
トーマス卿がうなずいた。
「アルテナ卿はその命を受け、それならば救国の英雄はふさわしかろうと提案したのだ。エリスティ公はさすがに王族なだけあって、あなたの剣のこともよくご存じだ。その剣の本来の役割を公にすれば、誰も文句は言わないだろうと。しかもあなたは見目もよく、さらに王国剣士として獅子奮迅の活躍をしてこられた。それでまあ、その・・・。」
トーマス卿は言いにくそうに何度か咳ばらいをした。
「その・・・それほどの男性ならば、夜の生活でもフロリア様を十分満足させられるだろうと。そうなればフロリア様とて一人の女性、男に溺れて、政務などどうでもよくなるだろう、国王になど戻りたくないと、フロリア様の口から言わせてしまおうと考えたようですな。」
フロリア様のほうから王位を放棄させる、それならばフロリア様に子が生まれても、その子が成長するまでエリスティ公が王位に就いていられる。一人息子は自ら廃嫡を願い出、公には跡取りがいない。自分が死ぬまで王位に就けるならと、考えたのだろうか・・・。
「しかし、御前会議でアルテナ卿があなたの名前を出したことで、意外な方がこの話に乗り気になったのだ。それがフロリア様にこのまま在位いただきたいと考えるレイナック殿だ。」
「・・・・・・・・・。」
「レイナック殿はフロリア様を娘のように思っておられる。エリスティ公一派のようにフロリア様を骨抜きにするためではなく、フロリア様の政治基盤を強化するための策として、あなたをフロリア様の夫に迎えてはどうかと考えたのだろう。」
私はどうやら、エリスティ公一派にとってもレイナック殿の一派にとっても、都合のいい存在であったらしい。
「その後の話は、お二人ともご存じのとおり。この話が公になった時、『救国の英雄は婚約者と別れ、フロリア様と結婚して大公になる』と誰もが考えた。お二人が婚約しているとはいえ、まだ神の御前で誓いを立てたわけでもない、お相手がフロリア様なら、その英雄は当然そちらに乗り換えるのだろうと。ところが、さっぱり話が進まない。そこでお二人を引き離すべく貴族達が動き出したのだ。ある家ではエリスティ公の目に留まる為に、またある家ではレイナック殿の目に留まる為に。」
「・・・それで、その話が出たころから急に貴族の家からの招待状が増えたのね・・・。」
妻はあきれたように言った。そしてそのころから、私を娘の婿にという招待状は激減した。私はほっとしていたものだが、その裏でそんなことが起きていたとは・・・。トーマス卿は変わらぬ穏やかな笑みで妻を見た。
「ウィロー殿、あなたを息子の嫁にと考えた貴族達には、もう一つ目的があった。それが私と同じように、デール卿の看板を手に入れることだ。エリスティ公に、あるいはレイナック殿に恩を売り、なおかつデール卿のご息女を嫁として家に迎えられれば、貴族社会の中で優位に立つことが出来る・・・。今思うと情けない話だが、あの当時、私も含めて多くの大臣や貴族がそう考えていたのだ・・・。」
「そういうことだったんですね・・・。最初に招待状をいただいていたころは中身をきちんと読んでいたんですけど、どの招待状にも必ず『デール卿のご令嬢』という肩書がついていて・・・その後あまりにも多くなってからはもういただいたその場でお断りしていたものでしたけど・・・。」
「実を言うと、私はその話も聞いていたのだ。あなたがほかの貴族の招待を断り続けていると。ということは、単にあなたをご招待申し上げたいというだけではおそらくおいでいただけないだろうと考えた。それでまあ・・・あなたの父上とは面識がありましたからな。亡きお父上の思い出を語り合いたいと、そう書いたわけです。」
「・・・その話については私からも謝らせてください。」
ずっと黙って聞いていたローランド卿が口を開いた。
「父からウィローさんをご招待するという話を聞いた時、私はてっきりクロービス先生もご一緒なんだと思っていたのです。私としてもぜひお2人にお会いして、いろいろとお話を聞かせていただきたいと考えていたので、ご招待の話には賛成したのですよ。ところがご招待するのはウィローさんお1人、しかもウィローさんを私の妻にと考えていると聞いて驚きまして、そんな事をしては行けないと何度も言ったのですが、結局私の力が及ばず、父の考えを変えることは出来なかったのです・・・。本当に申し訳ありませんでした・・・。」