昨日のフロリア様とのお茶会で、フロリア様が自分の過去に決着をつけるべく動き出したことを確信した。そして今日、久しぶりに再会したイノージェンの話を聞く限り、ライザーさんも自分の過去と向き合い、前に踏み出そうとしている。では、私はどうなのだろう・・・。
宿に戻って食事をした後、ラドがいいワインが入ったからどうだと勧めてくれたので、食後に一本頼んでおいた。今日は一日資料とにらめっこをしていたので、少し頭をほぐしておこう。あまり色々考えすぎると、いつの間にか考えが偏ってしまうことがある。
「はぁ・・・今日はびっくりしたわぁ。」
風呂上がりの髪を乾かしながら、妻が独り言のように呟いた。
「でも会えてよかったよ。色々話も聞けたしね。」
「・・・・・・・・・。」
妻が考え込んでいる。
「どうしたの?」
「・・・イノージェンは、全部知っていたんだなと思って・・・。」
「うん・・・。」
ライザーさんがなぜ島に戻ってきたのか、イノージェンは知っていたのだ。そしておそらくは、ライザーさんが祭りを見に行こうと言い出した理由も・・・。
「イノージェンも、私と同じようなことで悩んでいたんだなあって、さっき話を聞いていて思ったの。」
「そうだね・・・。オシニスさんからの手紙が届くたびに、その手紙の主が城下町でずっと待っているって、気にしていたんだろうね・・・。」
「そうよね。私も気になっていたし・・・。だからライザーさんがこの町に出てきた理由が、良くないことじゃなかったのが何よりうれしいわ。オシニスさんもきっと、待っていた甲斐があったわよね。」
「そうだね。私もホッとしているよ。」
「でも心配は心配ね。ちゃんと無事な姿を見せてくれないと・・・。」
「ライザーさんが後れを取るほどの凄腕はめったにいないよ。オシニスさんと会った時だって、気配を消したまま盗賊を追い払ったそうだからね。ダンさんの仕事の護衛が、思わぬところで役に立ったかな。」
もしかしたら、オシニスさんは不審に思ったかも知れない。『薬草園の旦那』に、そんな技術はいらないだろうと。だが、ライザーさんの仕事は薬草園の管理だけではない。ダンさんの仕事の護衛も、重要な仕事の一つだ。材木の切り出しで島の最深部に入る場合、ライザーさんは斥候として先行する。そして伐採の予定地に動物達がいれば、脅かして追い払う。でないと思わぬ事故で動物達を死なせてしまうことになる可能性があるからだ。動物達は気配に敏感なので、ライザーさんは仕事のために『気配を消す』訓練をすることになったのだ。
『まさか今になってこんな訓練をすることになるとはね・・・。』
そう言って笑っていた。いつだっただろう、ダンさんが
『いやあ、ライザーの気配の消し方は見事だなあ。おかげで島の奥まで入るのがずいぶんと楽になったよ』
と言っていたことがある。暗い場所で相手が人間なら、まったく気づかれずにすぐ隣に忍び寄るくらいのことは訳ないんじゃないだろうか。
「あの頃はまだ、あなたとライザーさんが立合をよくしていた頃よね。」
「うん・・・。あの後子供達に剣を教えるようになってからはなかなか2人で手合わせは出来なくなったけど、あれからもずっと、ライザーさんは剣のほうも訓練していたんだな・・・。」
「オシニスさんは何も言わなかったけど、おかしいとは思ったでしょうね。」
「オシニスさんのことだから、その場で聞いたと思うよ。もっとも事情を説明出来るだけの時間があったかどうかはなんとも言えないけどね。」
「それもそうか・・・。早く来てほしいわね・・・。」
「そうだね・・・。どうやらライザーさんも、前に踏み出すための行動を開始しているようだしね。」
私はイノージェンから渡された手紙をとりだした。
「まずは読んでみるよ。」
「私が読んでもよさそうなら読ませてね。」
「一緒に見てもいいよ。少なくともライザーさんは、私が自分に届いた手紙を君に隠すとは考えないと思うけどな。」
妻が笑い出した。
「それじゃ一緒に読ませて。」
私達はベッドの端に並んで腰掛け、ライザーさんからの手紙を開いた。
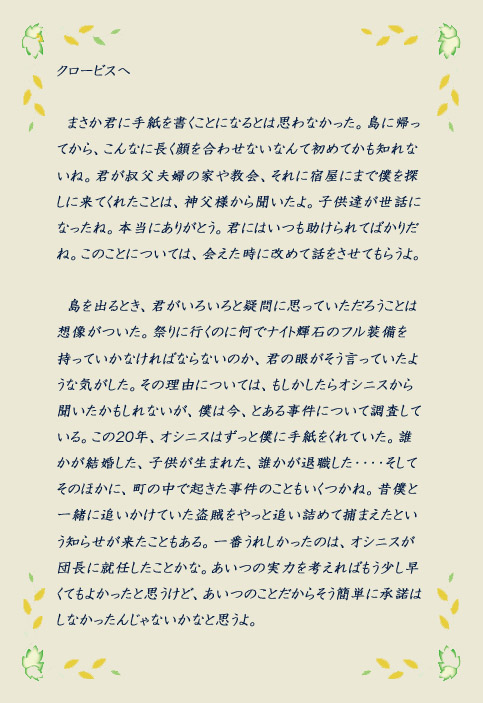

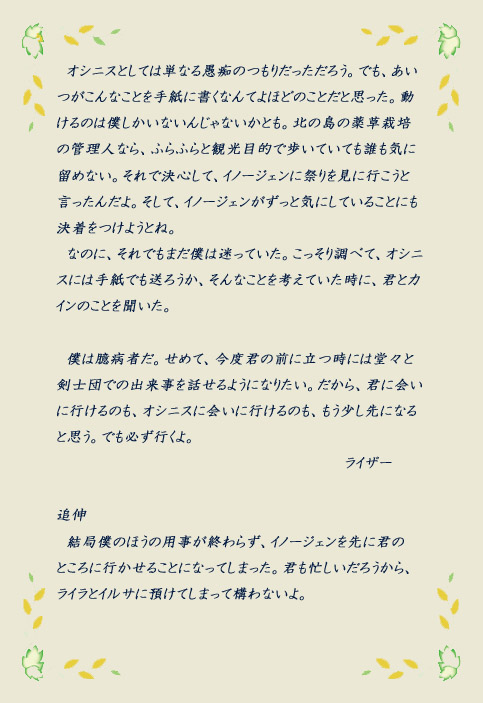
「・・・イノージェンは私より強いわね・・・。」
妻がため息をついた。
「どうして?」
「だって、私はあなたが島に戻ってこないかも知れないって不安に思っていたのに、口に出せなかったわ。だけどイノージェンは、ライザーさんに思い切って話したって言ってたじゃない?だからライザーさんも、もう一度王国に行こうって決心が着いたのかも知れないわよ。」
「私達だけじゃない、みんなが動き出しているんだね。過去に決着をつけようと。」
「そうね・・・。フロリア様もね。」
「うん・・・。私も動かないといけないな・・・。」
動く?いや、動くまでもなく、もう答えは出ている。なのに私自身がその答えと向き合うことが出来ないだけだ。
「あなただって動いているじゃない?」
「私は・・・」
忘れたふりをして、今まで生きてきた。故郷に帰り、結婚して子供が生まれ、父の仕事を引き継いで完成させ・・・何も考えずに毎日を忙しく生きて・・・でも、目を背けていた分だけ、思い出してしまった記憶をどうしていいかわからずに、取り乱してしまった・・・。
いつもいつもいつも、あの時カインを助けられたらと、その思いがただ後悔の念となって私を苦しめてきた。あの時の私にはそれだけの力がなかったのだと、わかっているはずなのに認めることが出来なかった。だが、今はどうだろうか・・・。
「・・・動いてはいるけど、どうなのかな・・・。」
胸を張って言えるほどの自信が持てない。一番強くならなければならないのは私なのに・・・。
「前向きになろうと思って行動しているつもりだけど、なかなか難しいね。」
あの頃のことを、一度全て吐き出してしまわなければ、私はこれ以上進むことが出来ないのかも知れない。
「こっちに来る前、ライザーさんにカインのことを話したって言ってたわよね。」
「うん・・・。」
「あの時のあなたは、見ているほうがつらくなるくらい憔悴していたわ。でもこれからオシニスさんにその話をしようとしているのに、今のあなたはとても落ち着いている。だから大丈夫、きっと前に進めるわ。そしてあなたが進んだ分だけ、私も進むわよ。私は必ずあなたの隣にいるから。」
「ありがとう・・・。」
ウィローと結婚して良かったなあと、いつも思う。これから先も一緒に歩いて行くためにも、私はこのつらい記憶を乗り越えなければならない。
「あとはライザーさんに会えればいいんだけど・・・やっぱり気になるわ。どうしてイノージェンが先に来たのかしら・・・。」
「この追伸部分はあとから書き足したみたいだね。」
その部分だけ他とインクの色が違う。
「ということは、それまではイノージェンが先に来る予定はなかったと言うことなのかしら。」
「そうかもしれない。何かあったんだろうとは思うんだけど・・・。ただライザーさんが追いかけている話というのが、何なのかわからないからなあ・・・。イノージェンが言ったとおり、そちらの調査が手間取っているってことなのかも知れないけど・・・」
「明日にでも聞いてみましょうよ。オシニスさんに剣士団での調査について聞くわけには行かないかもしれないけど、イノージェンになら、少しくらい聞いてもいいと思うわ。心配なのは同じなんだから。」
妻が少し口を尖らせながら言った。
「少なくとも、オシニスさんがライザーさんに会った時の様子だと、イノージェンのことは何も言っていなかったみたいだよね。聞き漏らしてはいないと思うんだけど・・・。」
「私も聞いてないと思う。」
「と言うことは、何か起きたとしたら、余程急なことだったのかな。」
「たとえば、昨日の夜から今朝にかけてとか?」
「うん。それもよほどのことが起きたのかもしれないね。ライザーさん達が泊まっていた宿はまともな宿屋だったよ。あのマスターは誰が泊まっているかを尋ねられて、ぺらぺらしゃべるような人じゃない。にもかかわらず宿を引き払ったと言うことは、泊まり続けられないほど大変なことが起きたと考えるのが妥当だと思うんだよ。」
「うーん・・・おかしな人達が訪ねてきたとか、歩いていて襲われたとか、そういうことなのかなあ。でもイノージェンは何も言わなかったわ。」
「ライザーさんが口止めしているのか、イノージェンが気を使っているのかのどちらかだろうね。」
「そっか・・・。もしもライザーさんの身に危険が迫っているなんて知ったら、オシニスさんは何が何でもライザーさんを探し出して、止めさせようとするわよね。」
「うん。そして剣士団長が仕事を放り出して友人を捜し回る事態になったりすれば、仕事がおろそかになるかも知れない。そんなことになったら剣士団の士気が下がる可能性もある。敵の狙いはそこかも知れないな。」
「でもオシニスさんへのダメージを与えるためだけに、わざわざライザーさんを狙うってのも不自然な気がするわ。ライザーさんとオシニスさんの接点なんて、昔から剣士団にいる人以外わからないんじゃない?世間に与える衝撃はそれほどないんじゃないのかと思うんだけど。」
「うーん・・・だとすると、他に理由があるってことか・・・。でもその理由が何なのか・・・」
2人揃って思わず大きなため息をついた。
「だめだ。私達のわかっていることだけではこれ以上のことは推測も出来ないね。とにかくせっかくワインを頼んだんだから、少しゆっくりと飲んで、あとは今日のお互いの仕事について情報交換にしないか?」
「そうね・・・。この話は明日イノージェンに聞いてみないとなんとも言えないわ。」
そこにワインが届いた。2人でワインを飲み始めたが、イノージェンの来訪、ライザーさんの手紙など思いがけないことがありすぎて、のんびり楽しむどころではなくなってしまった。それに今日はそれぞれが別な場所で仕事をしていたので、お互いがわかった情報の交換をすることにした。島にいる時、私達は離れて仕事をするということがほとんどないので、情報の共有という点では気にしたことはなかったが、今回はそうも行かない。
「へえ・・・イノージェンはずいぶん色々提案してくれたんだね。」
「そうよ。イノージェンのお母さんは城下町から島に渡った人だから、このあたりの食材から島の食材まで幅広くいろんな料理を作っていたみたいね。私が島に行ってからもお元気だったなら色々教えてもらえたのに、残念だわ。」
「その料理の腕はイノージェンに受け継がれているよ。それに君だって、カナの母さんからずいぶん色々教わってきたんじゃないか。栄養価って言うのは確かに大事だけど、まずは食べる楽しみを考えてあげないとね。患者にとっては食事が一番の楽しみなんだから。家族と離れて入院しているなら、なおさらだと思うよ。」
「そうよねぇ。おいしい食事で気持ちが上向きになれば、治癒力も上がるものね。」
「そういうこと。『病は気から』って言葉も、間違ってはいないと思うよ。今回の場合、まずクリフの体の痛みを出来るだけ取り除いて睡眠時間を確保出来れば、体だけでなく精神的負担も少なくなると思うんだよ。そこに栄養たっぷりのおいしい食事で元気をつけてくれれば、手術の成功率だって上がるさ。」
クリフは自分の命が長くないと知っている。おそらくは覚悟を決めているのだろうけれど、それでも出来ることなら生きたいと思っているはずだ。クリフには家族がいて、友人もいて、みんなが彼の快復を祈っている。
(生きたいと思わないなんてことはないはずだよな・・・。)
ふと、カインの顔が浮かんで、胸の奥がまた痛む。でも以前のように冷や汗が流れたりしない。私も少しは、以前より強くなれているのだろうか・・・。
「そう言えばさっきマレック先生が気にしてたんだけど・・・。」
「何を?」
脳裏に浮かんだ懐かしい面影を、慌てて記憶の隅に追いやった。今は感傷に浸る時ではない。
「チェリルにクリフの食事作りを依頼したいらしいんだけど、この間のことがあるでしょ?どうしたものかなあって。」
継続的に患者に食事を提供する場合、マレック先生はいつもチェリルの手を借りていた。だが、先日の一件以来チェリルには監視が付いているので、勝手な依頼をしていいものかどうか、迷っているらしい。
「うーん、さっき本人に話を聞きに行ったけど、仕事については特に何も言われていないそうなんだ。あの2人の雇用については行政局の管轄だそうだから、明日にでもレイナック殿に聞きに行ってみようか。」
「そうね。ねえ、オシニスさんに続きを話すのは先になりそうね。」
「明日にでももう一度聞いてみるよ。ハインツ先生達が今週一週間の記録をつけてくれているうちしか、私の時間が空きそうにないしね。」
「そうねぇ・・・。一週間後にすぐってわけにもいかないし、手術をしたとしてもその後経過を見ないで昔話ってわけにもいかないし・・・。そう考えると、後顧の憂いなくここを離れられるのは、しばらく先になりそうね・・・。」
「カナの母さんに手紙を出しておいたら?島を出る前に出した手紙には一ヶ月くらい先って書いたんだったよね?」
「・・・そうなんだけど・・・。」
妻が里帰りのことを気にしているのはわかる。目の前に治療すべき患者がいる状況で、そんなことを考えるのが申し訳ないと思っていることも。私もこんなことになるとは思っていなかったが、娘の帰りを楽しみに待っているカナの義母さんのことを、後回しにすることは出来ない。でも今動けないことも確かだ。とにかくまずはある程度の状況を知らせておく必要があると思う。
「楽しみにしてるだろうし、私も早く行きたいと思ってるよ。でも予定よりは延びそうだからね。」
「ごめんね、今は大変な時なのに・・・。」
「確かに患者は大事だけど、義母さんのことも大事だよ。ハース城経由で届けてもらえれば2〜3日で着くんじゃないかな。その手紙が母さんに届く頃には、こっちでもある程度の目処が付いていると思うよ。まあ手紙がそのくらいで着くのなら君が行った方が話は早いんだけど・・・。」
「そうも行かないわ。それに2人で帰らなかったら大騒ぎになるかも知れないわよ。」
「それもそうなんだよね・・・。」
初めての里帰りに、私が同行しないわけには行かない。
「仕方ないわよ。まずは手紙でこちらの状況を知らせておくわ。」
いつの間にかワインのボトルは空になっていた。つまみも相変わらずおいしかったのだが、仕事の打ち合わせをしていたせいか、2人とも酔ったという感覚がなかった。頭がはっきりしているのならと、妻はカナに手紙を書き始め、私は風呂に入ることにした。さすがに風呂までクリフの治療記録を持って行くことは出来ない。今日は一日、久しぶりに仕事のことばかり考えていたので、頭の中を整理してすっきりさせるのもいい。
『わたくしの護衛のために、必ず武装してくるように』
仕事のことが頭の中から出ていけば、やはり気になるのはフロリア様のあの言葉だ。フロリア様がオシニスさんときちんと向かい合って話をしようと考えた、これは間違いない。その前に私からカインのことを全て話してほしいと考えているのも理解出来る。出来るのだが・・・
「武装なんていつもしてるはずだよな・・・。」
王国剣士は執政館の護衛につく時全員が武装している。それはもちろん、護衛剣士のリーザも、剣士団長たるオシニスさんだって同じだ。リーザがいなくても、オシニスさんが武装していれば別に賊になど襲われたところで・・・いや、そもそも乙夜の塔に賊が入り込む隙なんてあるのか?もちろん皆無とは言い切れない。でもフロリア様は言わば王国剣士団の最高責任者だ。立場上誰よりも剣士団を信じていなければならないはずなのに・・・あの言葉は、まるで剣士団が任務に失敗するかも知れないからと言っているようなものだ。そんなことを迂闊におっしゃるような方ではないのだが・・・。
「はぁ・・・わからないな・・・。」
妻が言ったように、20年前のあの日、私達がオシニスさんにフロリア様を託して部屋を出た後、2人の間に交わされた会話についてはわからない。昨日フロリア様が聞かされた、あの部分だけならわかる、と言う程度だ。
「パズルのピースは隠されたままってことか・・・。いや・・・」
それならば、そのピースが出てくるかどうか、探ってみるのもいい。オシニスさんに、昔話の続きを話してみよう。この間オシニスさんには、サクリフィアの村を出たところまで話した。その後の話を、今日も話してみようかと思っていたのだが、どうもオシニスさんのほうが乗り気でないらしい。
「聞くのが怖い・・・ってところかな・・・。」
オシニスさんは、ずっとカインのことを気にしている。私達が海鳴りの祠を出る前、自分が言った言葉がカインを死に追い立てたのではないかと疑っているようだ。そして、フロリア様がカインのことをずっと気にしていたことも知っている。
(・・・ま、好きな女性に別な男の影が見え隠れしていれば、気になるのはわかるけどね・・・。)
たとえそれが、もうこの世にいない人であっても。ましてや自分が追い詰めたかも知れないとなればなおさらか・・・。
だとしたらオシニスさんにも、もう少し前向きになってもらおう。いつまでも話が出来なければ、海鳴りの祠でオシニスさんがカインに何を言ったのか、それも教えてもらうことが出来ない。時には待つことも必要だが、それは今ではないはずだ。
翌日、私達は早めに宿を出た。昨夜書いた妻の手紙は朝のうちにラドに頼んできた。毎朝荷物を届けてくれる配達人に頼めば、すぐに東の港の船に乗せてくれると言うことだった。
「仕事とは言っても、母さんを待たせちゃうのは心苦しいな・・・。向こうに行ったら謝らなくちゃならないな。」
「母さんはわかってくれるわよ。逆に、私達が仕事を放り出してカナに来ましたなんて言ったらすぐにでも追い出されちゃうわ。」
「ははは、それじゃ胸を張って会いに行けるよう、今日も頑張ろう。」
「そうね。」
王宮に着いて、まずは医師会に向かおうとした時、呼び止められた。
「失礼ですが・・・クロービス先生でございますかな?」
立派な身なりの年配の男性だ。私よりは大分年上だろうか。その顔に見覚えはない。自分を狙う何者かがいないとは限らないと、先日のラエルの一件でわかってはいるつもりだが、この男性からは殺気も邪気も感じられない。
「そうですが・・・。」
相手の動きを見ながら、慎重に返事をした。邪なものが感じられないとしても、気を抜けないことに変わりはない。男性は私の返事を聞くと安堵したように笑顔になった。
「おお、やはりそうでしたか。お初にお目にかかります。私はレンディールと申します。先生には、現ベルスタイン公爵の義理の兄と申し上げればご理解いただきやすいかと思いますが・・・。」
ということは、この男性はレンディール伯爵、つまりスサーナの父親だ。スサーナの父親が会ったこともない私に声をかけてくる理由は、おそらく一つだろう。
「レンディール伯爵ですね。お初にお目にかかります。私は・・・」
私も改めて名を名乗った。
「先生が医師会のお手伝いをされているという話は聞いております。お忙しいとは思うのですが、よろしければ少しお時間をいただけるとありがたいのですが・・・。」
「かまいませんよ。どちらでお話を伺えばよろしいですか?」
「ありがとうございます。それでは、執政館の上の階にあります我が伯爵家の部屋へおいでいただけますでしょうか。」
私達はレンディール伯爵について、執政館の奥の階段から、上へと上がっていった。レンディール伯爵家は、確かベルスタイン家と時を同じくして創設されたハーシアー公爵家の、初代公爵の孫娘によって創設されたと聞く。その後ハーシアー家は断絶し、その流れを汲むレンディール家は今に至るまで続いている。よく考えると、この家だって血筋としては申し分ないのじゃないか。王家の養子候補として考えてもおかしくないほどだ。確か子供は何人かいたはずだ。スサーナは末っ子で、しかも見た目も美しい女の子だと言うことで、伯爵が大分甘やかしてしまったらしい。それでスサーナはずいぶんとわがままに育ってしまったと、前にセルーネさんと会った時に聞いた記憶がある。
「どうぞお入りください。」
伯爵は中に入り、私達を応接室に案内してくれた。すでに部屋の中には使用人がいて、すぐにお茶が運ばれてきた。
「お忙しいところをご足労いただきまして、ありがとうございます。」
レンディール伯爵は丁寧に頭を下げた。
「先生とお会いしたこともない私が、わざわざここまでおいでいただく理由については、ある程度お気づきかと思いますが・・・。」
「お嬢さんのことですか?」
「はい。それとその・・・申し上げにくいのですが、剣士団長殿の・・・」
言いにくそうに伯爵はしばらく唸っていたが、やがて決心したように顔を上げた。
「いや失礼。これでは話が進みませんな。お話と言いますのは、おっしゃるとおり娘のスサーナのことです。我が家の末娘スサーナは王国剣士をしております。小さな頃から叔母の姿を見て、王国剣士にあこがれておりました。何事にも負けず嫌いな性格のおかげか精進を重ね、無事に王国剣士として採用されて、今ではそれなりの評価を得ているようです。その娘が、なんと剣士団長殿を好きになったという話を聞いた時には驚きました。あの方は娘より20も年上です。最初は飛んでもないと反対していましたが、剣士団長殿のお人柄も今までの実績も、知れば知るほど素晴らしい男性だということで、我が家からスサーナを嫁がせたいと使者を出したのですが・・・残念ながら団長殿が我が家においでくだされて、お断りされました。その時に『どなたか特別なお相手がいらっしゃるのか』と尋ねたのですが、特にそういう相手はいないけれど、あまりにも年の離れた結婚は娘の将来のために良くないのではないかと、どうやらきちんとお考えいただいた末のご返事と言うことで、私としてもあきらめざるを得ないと納得したわけなんですが・・・。娘のほうが納得出来ないようで、ずいぶんと悩んでおりましてな・・・。それでまあ、その・・・先日は先生にも大分ご迷惑をおかけしたとのこと、大変申し訳ございませんでした。」
レンディール伯爵はもう一度、頭を下げた。誠実な人柄が伝わってくる。
「飛んでもない。私のことはお気になさらずに。それで、もしかしたら伯爵がお聞きになりたいことと言うのは、昨日から広まっている噂のことでしょうか。」
「はい・・・実は一昨日、気分転換になればと思い、娘を連れて芝居見物に出掛けたのです。その時に娘が剣士団長殿を見かけたようなのですが、その・・・女性と一緒だったと、真っ青な顔で・・・。あの日の朝は娘の相方のシェリンが我が家に来て、休暇を繰り上げてもらって明日から仕事に戻ると言っておりましたので、私も安心していたのですが・・・。」
「ところが昨日の朝、シェリンと約束していたにもかかわらず、お嬢さんは1人で王宮へと出掛けてしまったということですね。」
「は、はい・・・先生はどうしてそのことを・・・。」
「剣士団長室でお会いしたんですよ。昨日の朝はオシニスさんと一緒に医師会にいくことになっていたものですから。」
「なんと、先生が・・・。では、うちの娘が団長殿に言ったことなども・・・ご存じなんですね・・・。」
「はい・・・。私が行った時にはちょうどシェリンが団長室に入った直後でした。お嬢さんはもう中にいて、前日一緒にいた女性について、オシニスさんが嘘をついていると言って、剣士団を辞めると言ってましたよ。」
「そうなんですよ・・・。なんともバカなことを言うものだと怒りましたが・・・。」
伯爵はため息をついて頭を抱えた。いささか暴走ぎみの娘を、どうしたものかと思案しているようだ。
「その後シェリンが休暇届を出していたようですが、今はご自宅にいらっしゃるのですか?」
「はい・・・。昨日からシェリンが泊まりに来て、説得してくれています。身内がいると甘えてしまうかも知れないと、妻も私も娘の部屋には入らず、シェリンに任せておりますが・・・あの娘はまだ王国剣士としてやっていきたいと言ってましたから、いつまでも世話をかけるわけにも行きません。それで、もしも説得の一助になればと、私がこうして先生にお話を伺いに参ったわけです。それで、その・・・娘のことで団長殿は何か言っておられましたか?」
昨日のオシニスさんの予感は当たっていたようだ。私はまずオシニスさんが言っていた祭りでの話は全部本当のことだと言うことをしっかりと説明した。そしてオシニスさんが言っていたように、スサーナの発した言葉がたとえ本気でなかったとしても、無責任な言葉だと受け取られていると言うことも、話すことにした。
「やはり・・・そうでしょうなあ・・・。」
先ほどから自分の娘を擁護するようなことを何も言わないところをみると、このレンディール伯爵という人物はなるほど噂に違わぬ公正な人物なのだろう。自分の娘が言った言葉の重さを、おそらくは本人よりも遥かに理解している。
「休暇を一週間ほど延長するようだとランドさんからお聞きしました。少し猶予は出来たようですし、ご両親もお嬢さんとよく話し合われてはいかがですか。」
「そうします・・・。先生、お時間を取らせて申し訳ありませんでした。」
レンディール家の部屋を出て、ロビーに戻った。
「お父さんも大変ね。スサーナが冷静に考えてくれればいいんだけど・・・。」
「冷静になってもらわないと困るよ。でもあのままでは、王国剣士としてこれ以上仕事をしていくのは無理かも知れないな。」
「そうねぇ・・・。」
スサーナがどんなに望んでも、オシニスさんは手に入らない。そのことを理解して気持ちを切り替えることが出来るのなら、まだ望みはある。だが、スサーナは退職というカードをちらつかせてオシニスさんの気を引こうとした。少し考えればそんなことでオシニスさんが考えを変えることはないとわかるはずなのに。あとは・・・考えたくはないが、スサーナが自分の命を捨てようとするのではないか・・・。たとえば本当に死ぬつもりなんてなくても、ただ、オシニスさんを振り向かせるために・・・。
(今の状態ではそこまでやりかねない・・・。でもまさかあなたの娘さんが自殺しないように見張っていたほうがいいなんて、言えないし・・・。)
おそらくシェリンはスサーナの気性をよくわかっているだろうから、そばを離れようとはしないと思うが・・・。
私達は医師会に行く前に東翼の宿泊所に顔を出すことにした。妻が今日もイノージェンに手伝ってほしいと言っていたからだ。それに、イノージェンが現れたことはいずれ人の口の端に上る。ライラの母親が王宮に現れたことが『敵』に知られれば、また新たな魔の手が伸びる可能性もある。
「イノージェンは私のほうで手伝ってもらうことにすれば問題ないけど、あなたのほうはどうするの?」
「今日はオシニスさんのところに顔を出すよ。」
「でも昨日はあんまり乗り気じゃなかったって言ってたけど、大丈夫?」
「乗り気じゃなくても乗ってもらうさ。ここまで来て聞きたくないからなんて言われたって、こっちも困るよ。」
「それもそうよね。オシニスさんが及び腰になってたら、いつまでもこの間のお茶会の話が出来ないものね。」
「そういうこと。それに、実を言うとね、私ももう勢いで全部話しちゃいたいかな、なんてね・・・・。」
本当は、それが一番なんじゃないかと自分でも思う。今を逃したら話せなくなってしまいそうで怖いのは、私の方かも知れない。
「おや先生、おはようございます。ライラ博士達ならもう出掛けましたよ。先生が見えたら、剣士団長室に行っているからと伝えてくれと。」
東翼の宿泊所の管理人は、笑顔でそう答えた。
「剣士団長室か・・・。」
『ライラ博士達』と言うことは、イルサもイノージェンも一緒なのだろう。管理人に礼を言い、私達もそっちに向かうことにした。
「今度は中から怒鳴り声が聞こえてこないといいわね。」
妻が冗談めかして言ったが、まったくその通りだ。団長室に行くたびにスサーナの声が聞こえてくるのは実に困る。だが、今回はさすがにそういうことはなかった。なかったが・・・
「これ何かしら。」
団長室の扉の前に、荷物を載せるような手押し車が置かれている。しかもかなり大きい。
「何か荷物でも運び込んだんじゃないかな。だとすると来客中かもしれないな。」
「でもライラ達はここにいるんでしょ?入りましょうよ。」
「そうだね。」
扉を叩くと中から開けてくれたのはイルサだった。
「あら先生、おばさん、おはようございます。母さんもライラもここにいるわよ。」
「クロービスか?入ってくれていいぞ。」
中からオシニスさんの声が聞こえ、私達は団長室に入った。入ってすぐの部屋にはオシニスさんの執務用机があり、いつもならそこに大量の書類が積み重なっているのだが、今日は書類のみならず、大量のファイルが置かれている。
「うわぁ、なんですかこれは。」
「ああ、これは文書館から持ってきてもらった古い記録さ。」
「文書館から?あそこの文書は持ち出せるんですか?」
「あそこは単に古い本をしまっておく場所じゃないぞ。この国で起きたことの全ての記録を保管しておく場所でもある。そういう記録は別に持ち出し禁止ではないよ。もちろん許可は必要だがな。お前に調べてやるなんて言っておいてなかなか顔を出せないから、今朝持ってきてもらったんだよ。」
「そうだったんですか・・・。」
なるほど、先ほどの手押し車はこれを運んできたものか。それにしても膨大な記録だ。この中からおかみさんの記録を探し出すなんて、どのくらいかかるか見当もつかない。
「エヴァンズ管理官、ありがとう。助かったよ。」
オシニスさんが部屋の奥に声をかけた。エヴァンズ?パティのお父さんは今でも管理官をしているのだろうか。
「飛んでもない。このくらいのことならいつでも構いませんよ。残りは奥にしまっておきましたから。」
女性の声・・・。手をぱたぱたと叩きながら出てきたのは・・・
「・・・エミー?」
「クロービス、久しぶりね。ウィローさんもね。」
そこに立っていたのは、紛れもなくエミーだ。文書管理官の制服を着ている。
「・・・一度会いたいと頼んではおいたけど、こんなに早く会えるとは思っていなかったわ。」
エミーは最後に会った時のような異様なオーラはもちろんまとっていない。それどころかエミーを取り巻く『気』はとても明るく穏やかだ。
「君が今の文書管理官なのか・・・。」
「そうよ。父さんの後を継いだの。別に世襲制ってわけじゃないんだけどね。司書の仕事もいいけど、あの場所の管理はとてもやりがいのある仕事だから、一生懸命勉強したのよ。」
エミーは最初に会った時のような笑顔を私と妻に向けた。
「オシニスさん、今日ここで会えるとは思っていなかったんですけど、この間お願いしていたこと、今、いいですか?」
「構わないよ。ライラ、イルサ、お袋さんと一緒に外してくれるか。」
「わかりました。」
「あ、ライラ、イルサ、もしもこのあと用事がなければ、君達の母さんをアスランに会わせてあげてほしいんだけど、病室まで案内してくれるかい?」
「あ、そうよね。それなら私が案内するわ。ライラ、あなたはどうするの?やることはたくさんあるって言ってたわよね。」
「僕も行くよ。せっかく母さんが来てるんだから、僕も一緒にアスランとセーラに会うべきだと思うしね。」
「それじゃ一緒に行きましょう。団長さん、管理官、失礼します。」
「イルサだったわね、さっきの話は、後何年かあなたが司書として実績を積めば大丈夫だと思うわ。本格的に考えたいなら、ぜひがんばってね。」
「はい、ありがとうございます。」
「イノージェン、今日もお手伝いをお願いしたいから、後でアスランの病室に行くわ。」
妻がイノージェンに声をかけた。
「わかった。もしも来ないようなら昨日の部屋に行ってるわよ。」
「よろしくね。」
「それじゃその時は僕が医師会に連れて行くよ。迷子になられると困るからね。」
「あら、そんなに方向音痴じゃないわよ、失礼ね。」
イノージェンはふくれっ面になって、ブツブツ言いながらライラとイルサのあとをついていった。
「さて、クロービス、ウィロー、座ってくれ。エヴァンズ管理官のところにはずっと前から顔を出すって言っていたのになかなか行けなかったから、事情を簡単に説明したんだよ。そしたら、ぜひお前達と話をしたいから、その時に立会人になってくれと頼まれていたんだ。」
「そうですか・・・。エミー、元気そうで良かったよ。あんな別れ方をしてしまったから、ずっと気になっていたんだ。」
「あの後ね・・・父が手配してくれた馬車が来て、私達は城下町に戻ったの。町の中は物騒だからって、ずっと家に籠もっていたわ。あのころ、私は何もする気力がなかった。何もかも、あなたが手に入らないなら全てのものが価値のないもののように思えて、毎日をぼんやり過ごしていたの。でも、王宮に剣士団が突入して、同じ頃にあれほど町中でささやかれていた聖戦の噂が消えてから、父が口をきいてくれて、王宮の図書室で見習い司書として働かせてもらえることになったのよ。」
エミーが少し鼻をすすった。