「ハース鉱山で・・・?」
思わず聞き返した私の隣で、ガチャンと音がした。驚いて振り向くと、その音は妻が手に持ったカップをテーブルに置いた音だった。
「あ・・・あら、ごめんなさい・・・。私ったら乱暴に置いたりして・・・。」
妻の顔は少しだけ青ざめている。カップから手を離してうつむいたまま、肩が小刻みに震えていた。だがフローラには、妻がなぜこれほど動揺しているのか判るはずはなく、怪訝そうに妻を見ながら言葉を続けた。
「はい・・・。姉の父は・・・鉱山に行ったまま、消息を絶ったそうです・・・。そしてそれは・・・ハース鉱山でナイト輝石が発見されて、王国中が歓喜していた頃のことだそうなんです・・・。」
「・・・君はその日記を全部読んだのか・・・?」
「いえ・・・。全部は読めませんでした・・・。いつ姉が戻ってくるか判らなかったし、私も姉がいない間店番をしなくてはなりませんでしたから・・・。」
「あの・・・父さん、ちょっとだけ奥で休んできていいかな・・・?何だか疲れちゃって・・・。」
姉が出かけた今しか、母の荷物を調べるチャンスはない。フローラは店の隣の部屋で休んでいる父親に声を掛けた。
「ああ・・。かまわんよ。お前にも苦労かけるな・・・。毎日働きづめだ・・・。少しなら父さんも店番できるから、ゆっくり休んでこいよ。」
「ありがとう・・・。」
心から心配してくれる父に嘘をつくのはつらい。心の中で父に手を合わせ、フローラは急いで奥へと入っていった。そこには姉の部屋がある。姉はさっきどこかへ出かけたばかりだ。しばらくは戻らないはずだ。フローラは母の荷物が入っていると思われるチェストを開けた。思った通り、そこには見覚えのある母の遺品が入っていた。かき回したりすれば盗み見たのがばれてしまう。フローラは、はやる心を抑えながら、慎重に荷物を一つずつ見ていった。そして見つけたのは・・・何通かの手紙の束と、母がよく書いていた日記の束だった。
(これに何が書いてあるのだろう・・・。)
小さい頃、母が手許でちょこちょこと何か書いているのはよく見ていた。たまに覗き込むと、いつもその中には数字がたくさん書いてあった。母は微笑んで
「これはね・・・毎日の売り上げと仕入れの金額よ・・・。なかなか難しいわね、商売って言うのは・・・。」
優しく頭をなでながらそう教えてくれた。これは全部のページが数字だけなのだろうか・・・。フローラは最初から最後までページをめくってみたが、その一冊はすべて収支の明細だけだった。フローラはとりあえずノートの束を横に置いて、手紙の束から一番上にあった一通を取り出した。そこに書いてあったのは・・・。
(『愛する妻と娘へ』・・・これは、きっと姉さんの本当の父さんからの手紙だわ・・・。でもこの文面は一体どういうことなのかしら・・・。生きては会えないなんて・・・。)
愛する家族に別れを告げなければならない悲しみ・・・。短い文だったが、だからこそ、その心が痛いほどに伝わってくるような手紙だった。
(もしかして、姉さんの本当の父さんは・・・何かよくないことに関わっていたの・・・?それで命を狙われていて・・・。そしてその仇を討つために姉さんはどこかに出かけている・・・。ではどこに行ってるのかしら・・・。)
フローラはそこまで考えて、ふとため息をついた。あまりにも突飛な話だ。まるで、最近町で人気が出ていると言われる、冒険小説の中の一節みたいだ・・・。そんなことが自分の身近に起きるなんて・・・。
他に何かないのだろうか・・・。フローラはもう一度手紙の束を手に取った。そしてもう一通引き抜いて見ようとしたが、なぜか他の手紙は、すべて封がされていた。一度読んで、もう一度封をしたらしかった。
(何で封なんてしたのかしら・・・。)
まさか・・・自分がこの手紙を盗み見るかも知れないから・・・!?いいえ・・・きっとそれは考えすぎだ・・・。自分が今、姉に内緒でこんなことをしているから、それでそんなことを考えてしまうんだ・・・。フローラは自分にそう言い聞かせ、先ほど引き抜いた手紙を丁寧に戻すと、手紙の束を諦めて母の日記をもう一度手に取った。だが日記の中は、どれもこれも他愛ない日常の出来事ばかりだった。でなければ収支明細か・・・。
(私の考え過ぎだったのかしら・・・。)
いまわの際の母のうわごと・・・・。泣きながら取りすがっていた姉の言葉・・・。そして数日前に現れた気味の悪い客・・・。すべては何と言うこともないただの偶然・・・。そして自分の聞き違い・・・。そう思っては見たものの、フローラの心のどこかで『それは違う』という声がする。フローラは諦めきれずに日記を一冊ずつ手に取り、最初からめくっていった。そして突然その手が止まった。
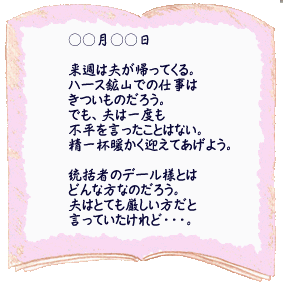 |
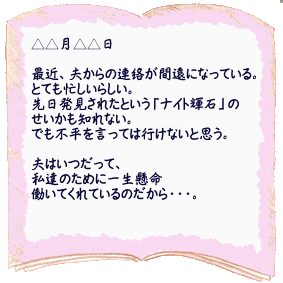 |
(ハース鉱山・・・?それじゃ姉さんと母さんは・・・昔南大陸にいたの・・・?)
もっと詳しく書いてあるところはないものかと、そのあとのページも何ページかめくってみたが、その他は、ほとんどが収支明細や姉に関することだった。今日こんなことを言っていたとか、こんな仕草をしていたとか、母の姉に対する愛情が伝わって来るようだった。やはりあの時の母の言葉に関する手掛かりは得られなかった。もうあまり時間がない。もうすぐ姉が帰ってくる。それに、店番を病床の父に任せてきてしまった。早く戻らなくては・・・。フローラは、これが最後と心に決めて、一冊の日記を取りあげた。この中を見て何も判らなければ、すべては自分の思い過ごしだと言い聞かせてこの場所を離れるつもりだった。焦って手が震え、ページの最初ではなく中程を開いてしまった。そしてそこに書かれていた文章を読んで、フローラは凍りついた・・・。
|
|
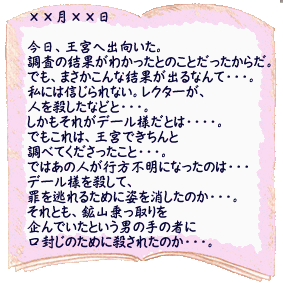 |
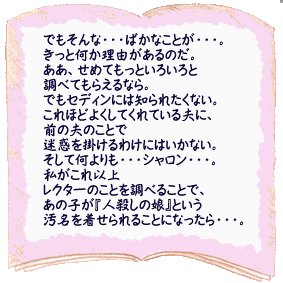 |
そこまで読んだ時、店のほうから父の呼ぶ声が聞こえた。もう行かなければ。フローラは震える手で慎重に母の荷物を戻すと、チェストの抽斗を閉めた・・・。
「シャロンの父親は・・・レクターというのか・・・・。」
あまりにも思いがけない話に、私はしばし呆然としていた。その私の隣で、妻がうめくように小さくつぶやいた。
「・・・どう・・・して・・・。」
膝の上で握りしめた手が、小刻みに震えている。
「どうして・・・そんな話が今頃・・・!」
そこまで言った時、妻の瞳からは涙がこぼれだした。カインは、多分初めて見る母親の涙に驚いている。
「母さん・・・?」
妻はハッとしたように涙を拭ったが、一度出始めた涙は、そう簡単には止まらない。妻はそのまま顔を覆い、立ち上がると部屋を飛び出した。翻ったスカートの裾がカップに当たり、床に転がり落ちて砕け散る。
「母さん・・!!」
カインは呆然と、妻の走り去った扉の先を見つめている。フローラは続けようとした言葉を呑み込み、怯えたような瞳で、やはり扉の先を見つめていた。
「カイン、フローラ、続きはちょっと待ってくれ!」
私はそう言い残し、妻のあとを追った。妻は私達の部屋に飛び込むと、私に背を向けたまま肩で息をしながら、まだつぶやき続けている。
「どうしてよ・・・。どうして・・・今になって・・・。」
何と声をかけてやればいいのか、うまい言葉が見つからず、私は黙って妻の肩に手をかけた。振り向いた妻の瞳は涙で濡れ、ぼんやりと私を見上げているが、その瞳には何も映ってはいないようだった。
「ねぇ・・・どうして・・・?やっと忘れたのよ・・・。憎みたくなかったから・・・。なのに・・・どうして今になって・・・思い出させるのよ・・・。」
そのまましばらく、妻は肩を震わせていた。『どうして今になって・・・。』私は昨夜の自分を思いだしていた。・・・昨夜からずっと私が問いかけ続けている言葉・・・。そして多分・・・誰も答えてはくれない・・・。
「昨日・・・あなたもこんな風につらかったの・・・?」
私は少し迷ったが、それでも黙ったまま小さく頷いた。
「そう・・・。そうよね・・・。きっとつらかったのね・・・。やっと忘れたのに・・・必死の思いで振り切ったのに・・・。どうして今になって・・・!」
妻はまた同じ言葉を繰り返し、私に寄りかかると、そのまま黙り込んだ。
「どうして・・・なんだろうね・・・。」
私も妻の肩を抱いたまま、同じ言葉を繰り返した。どうしてなのだろう・・・。3ヶ月前に私か奇妙な夢を見て、昨日は不気味な声を聞いた。そして私は、やっとの思いで振り切ってきたはずの、私の人生の中で最も忌まわしい出来事を、無理やり思い出させられた・・・。そして今日、妻はもう一つの忘れたい出来事までも、思い出すことになってしまった・・・。これは偶然なのだろうか・・・。それともこれから・・・また何かが起こるのだろうか・・・。
「・・・ごめんなさい・・・。取り乱してしまったわね・・・。」
妻は少しだけ顔をあげて小さく深呼吸した。
「仕方ないよ・・・。まさか・・・今になってあんな話を聞くことになるとは思わなかった・・・。しかもあの男が・・・シャロンの父親だったなんて・・・。」
「・・・シャロンのことはよく憶えているわ。城下町にいた間、たまにセディンさんの店に寄ったりすると、いつもにこにこしてお茶を運んできてくれたわよね・・・。かわいい子だったわ・・・。とても賢そうな瞳をしていて・・・。」
「うん・・・。あの子はとても賢い子だよ・・・。きっと・・・きれいな娘に成長しているんだろうな・・・。」
「でもどうして!寄りによってあの子がレクターの娘だなんて・・・。あの男の手先の・・・娘だなんて・・・。」
「でもデールさんを殺したのが本当にレクターかどうかなんて・・・解らないじゃないか。」
「でも鉱山で聞いたわ!あなただって聞いていたじゃないの!ナイト輝石が発見された頃から、父さんにまとわりついていた鉱夫がいたって!」
「それは憶えてるよ。その男が、時々姿を消したり、持ち場でもないところでうろうろしていたり、怪しい行動ばかりしていたって言うことも・・・ちゃんと憶えているよ。忘れるはずがないじゃないか・・・。」
「それじゃどうしてかばうの!?その男が・・・シャロンの父親かも知れないから!?」
「そんなことじゃないよ・・・。ウィロー、落ち着いてよ!だってみんな・・・推測の域を出ない話ばかりじゃないか!!」
「それじゃ!誰が父さんを殺したのよ!?」
妻はすっかり取り乱している。無理もないことではあるが・・・今はとにかく落ち着かせなければならない。
「君の父さんを殺した男は、もう死んだじゃないか!!私達の目の前で!!」
「だって・・・!!あの男じゃないわ!手を下したのは自分じゃないって・・・!!」
「それじゃ君は・・・一体どうしたいんだ・・・!?」
妻は肩をびくりと震わせ、言葉を失った唇を血が出そうなほどに噛みしめている。
「・・・仮にシャロンの父親が本当に君の父さんを殺したとしよう。そしたら君はデールさんの仇でも討つつもりなのか・・・?そしてシャロンの父親が既に亡くなっていたら?そしたら君はシャロンを仇として狙うつもりか?」
「私は・・・・。」
「仇の何のと言っていたら、いつまでも憎しみがなくならない・・・。あの時君が言った言葉だよ。・・・忘れちゃった?」
昨夜妻が私にそうしてくれたように、今日は私が妻の肩に手をかけて、子供に言い聞かせるように一言一言力を込めて話した。妻はしばらく黙っていたが、やがて小さく頷いた。
「・・・憶えているわ・・・。憶えているわよ・・・。忘れるはずがない・・・。でもね・・・悲しいの・・・。もうとっくに振り切ったと思っていたのに・・・。悲しくて仕方ないのよ・・・。」
妻の瞳からまた涙が流れ落ちる。
「それは仕方ないよ・・・。大事な人を失った痛みなんて・・・何十年過ぎたって消えるものじゃないと思うよ・・・。」
そう言う私の心も、きりきりと痛んでいた。もう20年以上も前の、ハース鉱山での出来事・・・。あの時はカインがいた・・・。私と肩を並べて、一緒に戦っていた・・・。そのカインを・・・私はこの手で・・殺した・・・。
背筋がぞくりとし、背中を冷たいものが流れていった。まぶたの裏のカインの姿が、再び鮮明さを増していくようだった。妻の肩を抱く腕が震え始める。
「ごめんなさい・・・。つらいのはあなたも同じなのよね・・・。私ったら・・・なんてばかなのかしら・・・。実際に手を下したのが誰であれ、もう父さんは戻ってこないんだもの・・・。私がここで憎しみを断ち切らなければって・・・そう思っていたはずなのに・・・。いつの間に・・・こんなに弱気になっていたのかしら・・・。」
「このことだけは・・・私は助けてやれないんだ。こうして・・・君が落ち着くまでそばにいてあげることしか・・・。」
「そんなことないわよ。あなたはいつだって私を助けてくれたわ・・・。あなたがいたから、父さんに会えた。そしてあなたがいたから・・・ここまで生きて来れた・・・。それに・・・みんな昔のことよ・・・。あれからもう・・・20年以上も過ぎているんだわ・・・。」
妻はそこまで言うと、今度は顔をあげて私をまっすぐに見つめた。
「ありがとう・・・。もう大丈夫よ。とにかく今は、フローラのことよね。」
「そうだね。少し冷静に考えてみよう。ハース鉱山で私達が聞いた話・・・。レクターという男がデールさんにまとわりついていたらしい。そしてその男が不審な行動を取っていた。その後デールさんと共に行方不明になった。それがナイト輝石が発見された頃と言うことだったね。」
「そうね・・・。そして私達が鉱山に行って、父さんの遺体を見つけた。つまりその男は父さんを狙う刺客で、父さんを騙して信用させておいて、他の鉱夫達に気づかれないように・・・密かに父さんを殺した・・・。」
妻が身震いする。ハース鉱山の地下室にうち捨てられていた、妻の父親の遺体・・・。その時の光景を思い出した瞬間、私はあることに気づいた。
「ウィロー、聞いていい・・・?」
「なに?」
「ハース城の地下で君の父さんの遺体を見つけた時・・・もう一つ遺体があったの憶えてる?」
「・・・憶えているわ。」
妻の声が暗くなる。
「ごめん・・・。嫌なことだと思うけど・・今思い出したんだよ。君の父さんの遺体に折り重なるようにして死んでいたあの遺体・・・。もしかしてあれが・・・。」
「シャロンのお父さんの遺体だったかも知れないってこと?」
「うん・・・。根拠はないんだけど・・・何となく・・・。」
「そうね・・・。もしかしたら、そうなのかも知れない・・・。あの遺体は・・・父さんの体の上に倒れていた・・・。父さんを殺した後に自分も殺されたという事なのかしら・・・。」
「それとも・・・かばおうとしていたのか・・・。」
私の言葉に妻はぎょっとして顔をあげた。
「クロービス・・・?本気で言ってるの!?」
「・・・あの状況からなら、そう言うことも考えられると言うことだよ。本当のところはわからないんだから、可能性としてゼロではないかも知れない・・・。」
妻はしばらく私の顔を凝視していたが、やがて視線を落とし、ため息をついた。
「・・・そうね・・・。少なくとも、父さんがその人に騙されていたわけでないと言うことになるのなら・・・いいんだけど・・・。」
妻の父親は、元々は若くして大臣の座に就いたほどの切れ者だ。それほどの人物が、そう易々と騙されるとは思えない。それにしてもあの遺体は・・・。本当にシャロンの父親のものなのだろうか。だとしても、確かめる術は何もない・・・。
「あの地下室の遺体は・・・あの後どうなったのかな・・・。モンスター達に踏み荒らされたりしてないといいけど・・・。」
「そうね・・・。父さんをあそこに置いてきてしまった・・・。あのあと・・・どうなったのかしら・・・。」
二人ともため息をついて黙り込んでしまった。ハース城の地下室に横たわる白骨死体の山・・・。その他半分腐乱した死体・・・。あれほどの凄惨な光景を見たのは、あの時とそれから・・・もう一度・・・。もう二度と・・・見たくない光景だ・・・。
「でも・・・レクターのことはあくまでも鉱夫達の推測に過ぎないんだ。どうして王宮ではそんな不確かな話をおかみさんにしたんだろう・・・。」
「そうよね・・・。」
妻も首を傾げている。
「もう少し・・・詳しく話を聞いてあげよう・・・。でも君がつらいなら・・・私が一人で聞くよ。」
「いいえ・・。もう大丈夫・・・。ごめんなさい、心配かけて・・・。」
「カインは多分もっと心配しているよ。今まで君のこんな姿を見たことなんてないはずだからね。」
「そうよね・・・。」
妻は私から体を離し、大きく深呼吸した。
「行こうか。」
「うん・・・。」
私達が戻ると、青ざめた顔のカインとフローラが黙ったまま座っていた。
「母さん・・・。」
カインが心配そうに妻を見つめている。いつも元気で、泣き顔一つ見せたことがない母親の取り乱した様を見て、カインは戸惑いを隠せないでいるらしい。見ると足下に飛び散ったカップの破片はきれいに取り除かれ、こぼれたお茶も拭いてあった。そして新しいカップにお茶がそそがれている。
「お前が掃除したのか?」
ちょっと意外ではあったが私は息子に尋ねた。
「僕とフローラできれいにしたよ。」
「そうか・・・。ありがとう。」
ため息をついてソファに座る妻と私を、二人とも不安そうに見つめている。
「すまなかったね・・・。フローラ、シャロンの父さんがレクターという名前なのは・・・間違いないのかい?」
「はい・・・。手紙の文末にその名前が書いてあって・・・それで母の日記を読んで、とても驚いたんです・・・。」
「君が読めたのは・・・そこまでだったんだね?」
「はい・・・。そのあと店に戻ってすぐに姉が帰ってきましたし・・・父に無理をさせるわけに行きませんでしたから、そのあと母の日記を見るチャンスはありませんでした。」
どうやらシャロンの父親は、間違いなくレクターという鉱夫らしい・・・。ため息をついて黙り込んでしまった妻と私の顔を交互に見て、フローラは戸惑っている。そもそも、なぜ私達がこれほどまでに衝撃を受けているのか、それさえフローラには判らないだろう。説明してやりたいが、それはかえってフローラを絶望の淵に落としかねない話だ・・・。フローラはどうしていいか判らず、すがるような瞳で隣に座っているカインを見た。だが、やはりカインも沈痛な面持ちで黙り込んでいる。カインにとって祖父に当たる人達のことは、きちんと伝えてある。妻の父親も私の父も、カインが生まれた時には既にこの世にいなかったので、せめてどんな人だったかだけでも知っていてほしかったからだ。フローラの今の話は、カインにとっても計り知れないほどの衝撃だったに違いない・・・。
「・・・カイン・・・?ねぇ・・・どうしたの・・・?どうして黙っているの・・・?」
フローラは不安そうにカインの肩に手をかけた。。カインはしばらくフローラを見つめていたが、いきなりその肩を思いきり抱きしめた。そしてちいさな声で、誰に言うともなくつぶやいている。
「君は君だよ・・・。そんな昔のことなんて・・・何も関係ないんだ・・・。」
カインの胸の痛みが伝わってくる・・・。
「カイン・・・!?ねぇ・・・どうしたって言うの・・・!?」
フローラはわけが判らず、カインの腕の中で震えている。このまま黙っているわけにはいかない・・・。
「フローラ・・・よく聞いてくれ・・・。」
「父さん待って!!まだ言わないで!!」
フローラを抱きしめたまま、カインが今にも泣き出しそうに叫んだ。
「今でなければいつ言うんだ!?後になるほどフローラが傷つくことになるんだよ!!」
「だって・・・!」
こらえきれずにカインが涙をこぼした。フローラはカインの腕を振りほどき、正面から私の眼を見つめた。
「教えてください。どうして皆さんがこれほどまでに動揺されているのか・・・教えてください!!」
「・・・ハース鉱山で殺されたという統括者は・・・私の妻の父親なんだよ。」
フローラは瞳を大きく見開き、真っ青になってふらりと立ち上がると後ずさった。
「・・・そんな・・・。姉さんの本当の父さんが殺したのは・・・あなたの・・・。」
「フローラ・・・。」
カインが立ち上がりフローラの腕をつかんだ。
「ほら・・やっぱり・・私はここに来るべきじゃなかった・・・。私がばかなんだわ・・・。私さえここに来なければ・・・。」
カインはフローラの腕を引き寄せ、肩をそっと抱き寄せると、なだめるように耳元で囁いた。
「そんなこと関係ないよ・・・。君は君なんだ・・・。それに・・・みんな昔のことじゃないか・・・。君も僕も・・・生まれるずっと前のことなんだ・・・。そんなことで・・・どうして君がこれほど苦しまなくちゃならないんだ・・・。おかしいよ、そんなの・・・。」
「でも・・・!私はもうここにはいられないわ!!」
フローラは取り乱し、カインの腕から逃れようともがいている。私はそっとカインの後ろに歩み寄り、耳元に話しかけた。
(カイン・・・。食堂にいるよ。落ち着くまでそばにいてあげなさい・・・。)
カインは背中を向けたまま小さく頷いた。妻と私はそっと部屋を出て、隣の食堂の椅子に腰掛けると、二人ともしばらくの間、ただ黙って座っていた。
「しかし・・・判らないな・・・。本当に・・・シャロンの父親がデールさんを・・・。」
「でも鉱夫の人達の話とは一致するわよね・・・。」
「それはそうだけど・・・フローラが読んだ日記の文面からは、おかみさんがどれほど旦那さんを信じていたのか伝わってくるよ・・・。本当に・・・そうなんだろうか・・・。」
「そうね・・・。それに・・・調査なんて誰がしたのかしら・・・。そしていつしたのか、その日記の文だけでは判らないわね・・・。」
「そうだね・・・。それが判ればもう少し調べようもあるのかも知れないけど・・・。」
「でもおかみさんがシャロンのことを考えて諦めたのなら・・・今さらよけいなことをするべきではないとも思うし・・・。」
「うん・・・。へたなことをしてシャロンが世間の矢面に立たされるようなことになったら・・・おかみさんに顔向けが出来ないし、セディンさんにも迷惑がかかるし・・・。」
「でも・・・このままにはしておきたくないわ・・・。」
「やっぱり知りたい・・・?」
「そりゃ・・・判るものなら知りたいわ・・・。でも、私のことより、フローラは今そのことであれほど悩んでいるのよ・・・。きっと・・・シャロンの父さんが人殺しかも知れないって思って・・・そのことでカインの将来に傷がつくのを恐れたのよ・・・。だから・・・あれほどまでにカインを拒絶しようとしてるんだわ・・・。」
「そうか・・・そうかも知れないね・・・。」
「私はそう思うの・・・。だから私のことはいいのよ。今さらどうにもならないことなんだし・・・でもせめて、フローラのことだけは何とかしてあげたいわ・・・。あの子は・・・とてもいい子よ・・・。」
「うん・・・。私もそう思うよ・・・。せめてフローラの不安だけは取り除いてあげたい・・・。そのあとあの二人がうまく行くかどうかは・・・また別の問題だけどね。お互いの気持ち次第というところかな・・・。」
「そうねぇ・・・カインがまた先走ってフローラを振り回したりしなければねぇ・・・。」
「なるほどね、確かにそうだな・・・。」
そこにカインが顔を出した。
「カイン、フローラは・・・落ち着いたのかい?」
「もう大丈夫だよ・・・。」
少し不安そうではあったがカインは頷いて見せた。フローラはソファに座り、涙を拭いながら一生懸命深呼吸をしている。私達も部屋に入りソファに腰掛けた。
「驚かせて・・・悪かったね・・・。」
フローラはまだ赤い瞳のまま、ゆっくりと首を横に振った。
「いえ・・・。かえって教えていただいてよかったです・・・。私・・・何も知らずにいて・・・。」
「少し話を戻そう・・・。フローラ、つらいかも知れないけど、さっきの話をもう少し詳しく聞かせてくれないか?」
「・・・はい・・・。」
「その日記の文を読む限り・・・君の母さんは元の旦那さんのことで、何か王宮に頼み事をしていたみたいだね。」
「そうなんだと思います・・・。」
「そうか・・・。しかし・・・妙な話だな・・・。だいたい調査なんて誰がしたんだろう・・・。あの時のことは・・・ハース帰りの鉱夫達以外では・・・私達しか判らなかったはずのことじゃないか・・・。」
「父さん・・・私達がって・・・。父さんはハース鉱山に行ったことがあるの!?」
思わず口走ってしまってから気づいた。このことを息子に話したことはない。というより・・・昔のことなど、私はカインに話して聞かせたことがほとんどなかった。せがまれて妻との馴れ初めを簡単に話して聞かせたことがあるくらいだ。私達がなぜハース鉱山へと向かわなければならなかったのか・・・。そのことを今言うべきなのかどうか・・・。そう簡単に話していいことでないのは確かなのだが・・・。でもここまで話が出てしまっては、ある程度のことまでは話す以外にないかも知れない。
「・・・あるよ・・・。もう・・・20年以上も前の話だけどね。」
「もしかして・・・父さんと母さんが知り合った頃のこと?」
「そう言うことになるね。」
「父さんが南大陸に行ったのって・・・ハース鉱山に行くのが目的だったわけ?」
「・・・まあね。」
「それって、剣士団の仕事でって言ってたよね。そこで母さんと知り合ったって・・・。」
「・・・そうだね・・・。」
「何の仕事だったの?」
「・・・それは言うわけにはいかないな・・・。昔のこととは言え、王国剣士としての任務の内容なんて、いくらお前にでも、軽々しく話せることではないんだ。」
「あ、そうか・・・。ごめん。そうだよね。解ったよ。」
カインが素直に引き下がってくれて、私は少しほっとした。
「ねぇ、父さん。昔、父さんと母さんが教えてくれたのは・・・母さんの父さんがずっと昔王宮で御前会議の大臣していたことと、そのあとハース鉱山の統括者として就任して、そこで亡くなったってことだけだったよね・・・。」
「そうだね・・・。」
「昔・・・父さんと母さんがおじいちゃん達のことをいろいろ話してくれるの、聞くのがすごく楽しかったんだ。何度も聞いているうちに、会ったこともないはずのおじいちゃん達がすごく身近に感じられて・・・。だから正直言うと、さっきのフローラの話はショックだったよ。シャロンがおじいちゃんを殺したかも知れない人の娘だなんて聞いてさ・・・。」
「カイン・・・。」
フローラの瞳からまた涙が落ちる。
「ごめん、フローラ・・・。君を責めてるんじゃないよ。でも嘘はつけない。今の僕の正直な気持ちなんだ・・・。」
「仕方ないわ・・・。でも私は姉が大好きなの。今までずっと私を守ってくれた姉だもの、本当の父さんがどんな人であっても、私は姉が大好きよ。だから、今度は私が姉を守りたいの。何かよくないことに巻き込まれているのだとしたら、何とか助けてあげたい・・・。でもそれは私の問題なのよ・・・。あなたは今、せっかく王国剣士になれて、何もかもこれからだわ・・・。万一姉の父さんのことが公になれば、私だって何を言われるか判らない。こんなことにあなたを巻き込むわけにはいかないの。だから・・・ごめんなさい。あなたとはもうおつきあいしない方がいいのよ・・・。」
「待ってよ、フローラ!そんなに結論を急がなくたっていいじゃないか!」
つらそうに下を向くフローラの肩を揺さぶりながら、カインは私に視線を移した。
「父さん・・・。ハース城に行ったことがあるって言うなら、何か判ることはないの!?任務のことは聞かないよ。僕は剣士団に入ってまだ3ヶ月だけど、自分の任務を人にべらべら喋っちゃいけないってことくらいわかるから。でも、そのこと以外なら、教えてくれるよね!?本当の本当に、シャロンの父さんはおじいちゃんを殺したの!?それは確かなの!?」
カインは必死だ。
「すこし落ち着きなさい。順を追って説明するから。」
「はい・・・。」
カインはフローラから手を離し、私達に向き直った。
「シャロンの本当のお父さんらしいレクターという男が、もしかしたらデールさんを殺したかも知れない。これは私達もハース鉱山で聞いたよ。」
「やっぱり・・・そうなんですね・・・・。」
フローラは肩を落とした。
「・・・でもそれは、はっきりしていないんだよ。私達が聞いた話は、デールさんにまとわりついていた鉱夫がいたらしいことと、その男が時々持ち場でもないところでうろうろしていたとか、時々姿を消したりすることがあったとか、その程度のことなんだ。実際に殺人の現場を目撃した者がいるわけでもないし・・・。もっとも、あの頃ハース鉱山にいた鉱夫達の間では、その男がきっとデールさんを殺したんだろうと、言われていた。あの時、鉱山を乗っ取ろうとしていた男の手先になって、デールさんを騙して近づいたんじゃないかとね。でもそれはあくまでも鉱夫達の間で囁かれていた噂にすぎないんだ。なのにどうして王宮では、そんな不確かな情報をおかみさんに伝えたのか・・・。そして、そもそもおかみさんは、一体何を王宮に頼んでいたのか・・・。」
「もしかしたら、ハース鉱山で本当に亡くなったのかどうか調べてもらおうと思ったのかな。その短い文面の手紙だけでは、生きてるんだか死んだんだかわからないからって。」
「うーん・・・確かにその可能性はあるけど・・・。それだけのことなら、わざわざ誰かを殺したの何のと言うことまで調べる必要はなかっただろうし。それに・・・。誰がどこでいつ死んだかなんて・・・多分あの状態では調べようがないよ・・・。」
「その言い方だと、父さんはその現場に居合わせたわけ?」
「・・まあね・・・。現場と言っても・・・死体置き場を通っただけだけど・・・。」
「死体置き場か・・・。そんな場所があったって事自体・・・当時のハース鉱山はすごいことになっていたってことだよね。」
「そうだね・・・。あんな場所は・・・もう二度と行きたくないよ。」
「そうなると・・・フローラの母さんが一体何を王宮に頼んだのか・・・それが判らないことには、どうしようもないってことか・・・。」
「でも・・・黙って日記を読んだことを姉に言うわけにもいかないし・・・どうやったら判るのか・・・。」
フローラはすっかり困惑している。
「それにもう一つ疑問があるよ・・・。」
「疑問って?」
私の言葉にカインが首を傾げる。
「フローラが立ち聞きした話だよ。最後の言葉は、確かにシャロンに仇を討たせてやると言っていたんだろう?」
「あ・・・そうか・・・。それって話が逆だよね・・・。」
「そうだよ・・・。シャロンの父さんが本当にデールさんを殺したというのなら、仇と狙われるべきはその本人のはずだ。そしてその人を仇と狙う可能性があるのは、母さんか、カナの村にいる母さんの母さん、つまりお前のおばあちゃんか、その二人しかいないはずだよ。でも二人ともそんなことは考えていないんだ。その言葉の謎が解けなければ、仮におかみさんが王宮に何を頼んでいたか判ったところで、結局は何も判らないのと同じだよ。」
フローラは眼を閉じて、力無くため息をついた。自分でも、もうどうしていいか判らないようだ。そんなフローラを気遣うように、カインがフローラの肩を抱き寄せ、ちいさな声でつぶやいた。
「何か・・・方法はないのかな・・・。このままでは・・・判らないことだらけだよ・・・。」
「・・・判らなくてはいけないのかな・・・。」
「父さん・・・。判らなくちゃ、フローラはずっと悩まなくちゃならないじゃないか・・・。」
「・・・そんなことでフローラが悩まなくちゃならない道理はないじゃないか・・・?シャロンの行動がおかしいのは確かに不安だけど、デールさんが殺されたのはもう20年以上前のことなんだよ。もうずっと・・・昔の話じゃないか・・・。」
フローラは黙って下を向いている。この娘が一人でいくら悩んでみたところで、実際の問題は何一つ解決しない。このままでは、この娘の姉を思いやるやさしい心が、どんどん自分自身を追いつめていってしまう。それに・・・昔のことなんて・・・私自身も話したくない。子供達に話して聞かせたいようなことではない・・・。
「それはそうだけど・・・でも・・・ほっとけないよ!フローラは多分・・・悩むなって言っても悩んじゃうよ。それにシャロンが心配じゃないか・・・。」
カインは半べそ顔で私を見ている。息子のこんな顔を見るのはつらい・・・。
「判ったよ。とにかく、話を整理してみよう・・・。」
私は先ほどフローラから聞いた話と、自分が今話して聞かせたことをつなぎ合わせ、慎重に口を開いた。