「なるほどね・・・。それで父さんは北大陸に戻らずに、母さんと行動を共にすることにしたわけか・・・。」
「そういうことだよ。あの時の母さんの頑固なことと言ったら・・・。カナの村長が10人くらいでかかっても説得なんて出来っこなかっただろうな。」
「ちょっとクロービス、それは言い過ぎよ!そんなに頑固じゃなかったわよ!」
妻が慌てて口を挟んだ。
「はっはっは!それじゃ父さんに説得なんて出来るはずないよね。父さんてさ、母さんにはめっぽう弱いもんなぁ。」
カインはおかしそうに大笑いした。
「え・・・?そ、そうかな・・・そんな風に見えるのか・・・?」
「見えるよ。でも尻に敷かれてるって感じはしないんだけどね。」
「どこで憶えてくるんだ、そんな言葉・・・。」
そう言ったもののだいたい想像はつく。私が子供の頃もそうだった。この島の中でいろんな勉強を教えてくれていたのは当時の長老だったが、長老達が絶対に教えてくれないような悪い言葉やいたずら、それに女の子のことなど、その手の話を私達に教えてくれたのはいつだってダンさんやドリスさんだ。その構図は今だって変わっていない。
「でも・・・ナイト輝石の廃液って言うのは・・・そんなに毒性が強いのか・・・。ライラの奴・・・それほど危険な仕事をしてるんだな・・・。」
カインが急に真顔になってつぶやいた。
「知ってたのか。ライラが王国に出ていって何をしていたのか。」
「うん・・・。剣士団に入ってすぐくらいかな・・・。王宮のロビーで会ったんだよ。フロリア様への定時報告だって言ってた。その時・・・いろいろと話を聞いたんだ。」
「そうか・・・。」
「父さんと母さんにも謝ってたよ。」
「謝るって・・・なにを?」
カインは答える前にフローラをちらりと見た。フローラは不安そうにカインに視線を返している。
「ねぇ、父さん母さん、この間・・・フローラがダンさん達の話を聞いちゃったこと、父さん達もわかってるよね?」
「わかってるよ。ドリスさんが一生懸命謝ってたよ。」
「あ・・・あの・・・私あの時、間違えて診療室の廊下に出てしまったんです。それで、うろうろしている時に立ち入ったことまで聞いてしまって・・・すみませんでした。」
フローラが頭を下げる。
「気にしなくていいよ。君が悪いわけじゃない。それにもう終わったことなんだし・・・。」
私は妻の顔をちらりと見た。私にとっては終わったことでも、妻にとってはどうなのか。男にはどう頑張っても理解出来ない思いがあるのではないだろうか・・・。
「そうね。もう終わった事よ。偶然聞いてしまっただけなんだもの、気にすることはないわ。」
妻はいつもの笑顔をフローラに向けた。私が気をもんでも仕方ないのかも知れない。
「カイン、ライラの話って、そのことだったの?」
フローラからカインに移された妻の視線には不安が滲んでいる。確かにつらい出来事ではあったが、ライラには何の責任もない。あの優しい若者は、自分が憶えてもいないことで今までずっと負い目を感じて生きてきたのだろうか・・・。
「それだけじゃないけどね。僕はライラがハース鉱山にいるなんて、その時まで全然知らなかったんだ。父さん達は知ってたの?」
「知らなかったよ。ライラが島を出ていく時ライザーさん達に、いい仕事でも見つかったのって聞いたんだけど、何か自分のやりたいことがあるらしいからってしか言わなかったんだ。」
「・・・ライザーおじさんは知っているんだね、ハース鉱山で何が起きたのか。」
「知っているよ。北大陸に戻った時にひととおりの話はしたからね。」
「そうか・・・。」
カインが妙に沈み込んだような顔をした。
「どうしたんだ・・・?」
「うん・・・。正直言うとね、僕は父さん達がハース鉱山に行ったことも知らなかったのに、ライラがちゃんとわかってたのが・・・悔しかったんだよ・・・。ライラは・・・僕なんかよりずっといろんなことをわかってて、ちゃんと考えているんだなって思って・・・。」
話せなかったのは・・・ただ単に話したくなかったからだ。思い出したくなかったからだ。それに・・・この王国のためにも口に出すべきではないことだったからだ。でも何を言っても、今のカインにとっては言い訳でしかないような気がする。
「・・・ライラは元気そうだったか?」
「うん。もう少しで夢の実現に向けて一歩を踏み出せるって言ってた。それで、それはみんな父さんと母さんのおかげだって。もしもあの時助けてもらわなかったら、今こんなに夢中になれるほどの仕事に出会うこともなかったから、すごく感謝してるって。」
「そうか・・・。」
「でもそのために、もしかしたら僕にとって兄さんか姉さんがいたはずだったかも知れないのに、って・・・申し訳ないって言ってたよ。」
「そんなこと・・・ライラが気にすることはないのにね・・・。」
妻が遠い目をしてつぶやいた。カインはそんな妻を気遣うような眼で見ながら言葉を続けた。
「でも前にサンドラさんに言われたことがあるんだ。」
「なんて?」
「確かにあのことは不幸な出来事だったかも知れないけど、でもただ単に、僕が生まれてくるのが何ヶ月か遅くなっただけなんじゃないかって。」
「・・・なるほどね。そういう言い方もあるか・・・。」
そうは言ってみたが、それでもあの時失った命はカインのものではあり得ないし、そう思ってしまったら、あの命の行き場がなくなってしまう。でも私は何も言わなかった。カインがそれで納得しているのなら、今はそれでいい。いつかカインが父親になった時には、あの時の私と妻の気持ちを少しでもわかってくれるだろうと思う。
「ライラが言ってたよ。せっかく救われた命なんだから、絶対に大事にするよって。そのためにがんばって剣を憶えたんだってさ。ライラがそんなことまで考えて剣の稽古をしていたって聞いて、びっくりしたよ・・・。」
「お前だって王国剣士になりたくてずっと稽古してたじゃないか。」
「うん・・・。でも・・・僕がライラと初めて王宮で会った時、僕はまだやっと城下町の中の警備を許されたばかりの時だったんだ。なのにライラはもっと遙か前に一人で南大陸へ行って、今は向こうとこっちを何度も歩いているんだよ・・・。剣士団の中でも結構有名みたいだよ、『学者剣士』なんて呼ばれてるんだってさ。」
「学者剣士とはまた・・・なかなかの称号だな・・・。誰から聞いたんだ?」
「アスランのやつさ。僕達が王宮のロビーで話してた時にちょうど来たんだ。ライラと会うのは初めてだったけど、ハース鉱山に剣の腕が立つ研究者がいるってことは聞いてたんだって。」
「なるほどね・・・。」
以前、一度だけライザーさんに頼まれてライラの相手をしたことがある。ライラが島を出るずいぶんと前のことだ。その時、この若者がこのまま稽古を続けていけば、そう遠くない将来、父親にも匹敵するほどの腕を身につけられるだろうと思った。その私の目に狂いはなかったらしい。ではカインはどうなのだろう。他人のことならば冷静に判断できるのだが、自分の息子となると『親の欲目』を差し引かなければならないような気がして、どうしても厳しい目で見てしまう。ライザーさんがカインの相手をしてくれた時、もう少しいろいろと聞いておけばよかったかな、ふとそんなことを考えた。
「で、ライラは他になんて言っていたんだ?」
「・・・この仕事を必ず成功させて、それから島に帰るんだって笑ってたよ。ライラの父さんと母さんに、自分が島から出ることに賛成してよかったって心から思ってもらえるように、無事な姿を一日も早く見せてあげたいって。定時報告は毎月あるみたいなんだけど、今月はまだ来ていなかったっけ・・・。祭りに合わせて来るのかな・・・。今度はちゃんとフローラを紹介したいんだけどな・・・。」
「何だ、まだしてなかったのか。」
「うん。最初にライラと会った時は、まだやっとお茶に誘えるようになったくらいだったし。次の時は僕のほうが忙しくて、王宮のロビーでちょっと立ち話しただけだったんだ。」
「・・・ライラからナイト輝石の試験採掘の話を聞いたのはいつなんだ・・・?」
「それは先月来た時だから・・・あ、でもまだ一ヶ月までは過ぎていないかな。そのころ団長からも同じ話を聞いたんだ。今回は初めてだからかなり小規模だってことと、廃液がきちんと浄化されるかどうかを確認するために、精錬施設に大きな貯水槽をいくつか設置したんだって。」
「その話をした時、オシニスさんはどんな顔してた?」
「うれしそうだったよ。あの時は、ナイト輝石の採掘再開がうれしいんだなと思ってたけど、今思うと自分の相方だった人の息子がそんなすごいことをしようとしてるっていうのがうれしかったんだね、きっと。」
「それはそうだろうな・・・。ライラはライザーさんにそっくりだから、オシニスさんも一目見てすぐにわかったと思うよ。きっとずっと応援していたんだろうな。もっとも、あの人はそんなこと口に出さないけどね。」
「ランドさんもうれしそうだったんだけど、やっぱりライザーおじさんが昔の自分の仲間だからだね。」
「ランドさんとオシニスさんとライザーさんは、みんな仲がよかったんだよ。そうだなぁ・・・ライザーさんがもし今も剣士団にいたら、オシニスさんとランドさんと3人で、お前達の相手をしてもらえたのになあ。」
「じょ・・・冗談じゃないよ!この間おじさん一人に全然歯が立たなかったのに、その上団長とランドさんまで出てこられたら・・・。」
カインは本当に飛び上がりそうなほどに驚いて、慌てて大声を出した。オシニスさんとランドさんの腕はいやと言うほど知っているだろうから、焦るのも無理はない。
「別にお前一人で相手をしろって言うんじゃないよ。アスランがいるじゃないか。父さん達だって、2人だからあの3人を相手にしても何とかなったんだよ。それぞれ一人ずつなんて言われたらどうしようかと思ったけど。」
「そ・・・そりゃそうだけどさぁ・・・。」
「一人では無理なことも、二人なら何とかなるさ。コンビってのはそう言うもんだよ。もちろん、お互いの信頼関係がなければ無理だけどね。」
「信頼関係か・・・。」
カインはまた少し暗い顔をした。アスランの母親のことを聞いてしまってから、多分休暇に入る前までちゃんと話せてないのだろう。黙っている私の顔を少しの間上目遣いに見ていたが、やがてハッとしたように顔をあげ、
「そういえば・・・。」
言ってからなぜかすぐに「しまった」というような顔をした。どうしたのだろう。
「ん?」
「ライラと初めて会った時ね、城下町の喫茶店に入ったんだよ。」
「へぇ、喫茶店か・・・。どこの?」
「うーんとね・・・フローラの店のあるところから一本東隣の通りを奥に入って、そこから少し小さい路地に入ったところなんだけど・・・。」
「ああ・・・あのあたりはけっこうしゃれた店があったけど、今はどうなんだ?」
「昔からそうだったのか。今も女の子が好きそうな店がたくさんあるよ。でもライラとその通りに行った時は、まだ城下町の中もよく知らなかったけどね。」
「そうか・・・。でもそんなところに喫茶店なんてあったかな・・・。」
「父さんが向こうにいた頃には、多分なかったと思うよ。」
「出来たのは最近なのか?」
「もう10年以上にはなるって言ってたなあ・・・。」
「へぇ・・・それじゃ、祭りに行った時にでも覗いてみようかな。なんて言う店なんだ?」
「セーラズカフェ。店のママさんがセーラさんて言うからだってさ。」
「女の人一人でやってる店なの?」
妻が興味深そうに身を乗り出した。
「違うよ。あれ・・・?」
「どうしたの?」
カインが途中で話すのをやめ、首を傾げたので、妻は不思議そうにカインの顔を覗き込んだ。
「他に男の人がいたんだけど・・・そう言えば・・・あの二人は夫婦なのかな・・・。聞いてこなかった・・・。」
「単にそのセーラさんが経営者で、その男の人は従業員だったんじゃないの?」
「でも、コーヒーを実際に煎れているのはザハムさんだったんだよ。」
「ザハムさん?」
カインの口から出たその名前にドキリとした。ライザーさんたちの会話を盗み聞きしてしまった時のことを、私は思いだしただけで一言も言わなかったはずだ。いや、単なる偶然の一致かもしれない。でもそんなにどこにでもあるという名前じゃない・・・。
「そう、すごく落ち着いてて・・・腕っぷしが強そうで・・・その人の煎れたコーヒーがすごくおいしかったんだ。」
「腕っぷしって・・・何それ?」
妻はますます首を傾げている。
「あ・・・あのね・・・。」
カインは言っていいものかどうか、何となく迷っているらしい。そのザハムという人物が私の知っている人物ならば、確かにカインが言い淀むわけがわかるような気がした。
「あのさ、母さんとフローラは・・・もしかしたらあんまりいい気持ちしないかも知れないんだけど・・・。」
「・・・どういう意味・・・?」
「あのね、セーラママって言うのはね、昔、城下町の歓楽街で仕事をしていたんだって。」
カインは一気に言った。言い終えて小さく深呼吸している。
「歓楽街って・・・あそこには酒場もたくさんあるけど、そう言う場所・・・?」
妻がカインに尋ねた。カインは黙って首を横に振った。妻はそれを見て「やっぱり」と言った顔で小さく頷いた。
「なるほどね・・・。いい気持ちしないなんて思わないわよ・・・。ああいう仕事を女として恥ずべき行為だ、なんて言いきる人もいるけど、それぞれ事情があるんだから他人がとやかく言うようなことじゃないと思うわ。」
「私もそんなこと思わないわよ・・・。そりゃ確かに・・・自分がそういう境遇になりたくないって思うけど・・・あそこで働く人達だって、そうなりたくてなったわけじゃないんだろうし・・・。」
妻とフローラの言葉を聞いて、カインは少しほっとした表情を見せた。先ほどのカインの『しまった』顔の意味がわかった。今日の稽古を終えた後、カインは妻とフローラに聞かれたくなくて、わざわざ外でアスランの母親の話を盗み聞きしてしまったことを私にうち明けたのだ。歓楽街の話題など、女性の、しかも母親と恋人の前でなんて話したくなかったのだろう。なのに今うっかり口を滑らせ、似たような話を彼女たちの前でする羽目になってしまったことを後悔していたらしい。
「そっか・・・。王宮の女の子達は、けっこうあそこで働く女の人達に厳しいんだよね。「あんな仕事しているなんて」とか、「あそこまで堕落したくない」とか・・・。」
「堕落とはまたひどい言い方ね。そんなことを言う人達が王国の中枢で働いていることのほうが恥ずかしいわよ。」
妻の思いがけない厳しい言葉に、カインは少し驚いたようだった。
「で、カイン、男性であるあなたの目には、あそこで働く女性達はどう映るの?」
少し怒っているらしい妻に尋問のような口調で質問されて、カインは少し肩をすくめた。これはカインの小さい頃からの癖だ。妻がカインを叱る時、いつも今のような口調で話す。そしてカインはいつもこんな風に肩をすくめて、妻を上目遣いに見るのだった。
「僕は・・・そういう女の人達に会ったことはないけど・・・母さんが言ったみたいに、いろいろ事情があってあそこにいるっていうのは聞いたことがあるから、かえって大変だろうなって思うよ・・・。それだけだけど・・・。」
「いいじゃないか。カインはまだ18なんだし、この島から出るまでそういう仕事をしている人達のことなんてよく知らなかっただろうから、ここであんまり立派なことを言われるとかえって嘘くさいよ。」
口ごもるカインが気の毒になって、思わず助け船を出した。
「それもそうね・・・。カイン、ごめんね、ついムキになっちゃったわ・・・。」
妻が肩をすくめてみせた。
「いや、いいけど・・・それで、そのザハムさんて言う人は、そこのママさんが働いていた店の用心棒をしていた人なんだってさ。」
妻の態度がカインには解せないらしく、言葉を続けながら首を傾げている。
「・・・用心棒・・・?」
首を傾げかけた妻は、次の瞬間顔をこわばらせて私に視線を向けた。でもそれは本当に一瞬のことで、すぐにいつもの笑顔に戻った。カインがそれに気づいたかどうかはわからない。
「用心棒とはまた・・・ずいぶん畑違いの仕事をしていたのね。」
「そうだよね・・・。僕も最初に聞いた時は、すごくびっくりしたけど・・・。」
「でも今は喫茶店のマスターで、そのセーラさんはママさんなんだから、それでいいじゃないか。それより、ライラの話の続きを聞かせてくれないか。」
「あ、うん・・・。そのあとは・・・他にお客さんがいなかったからセーラママ達が奥で僕達の食事を作り始めて・・・あ、そうだ、途中でマスターがコーヒーサーバーを割っちゃったりして・・・その後話したことは・・・いろいろだよ。昔話とか・・・。」
「コーヒーサーバーを・・・?商売道具を割るなんて、おかしなマスターさんね。」
妻がクスリと笑った。
「そうだよね・・・。あのときは確か・・・南大陸に行くためにライザーおじさんに剣を習ってたのかって、ライラに聞いてた時だったような気がするなぁ・・・。カウンターの中でパリーンと音がして・・・。」
カインは首を傾げて頭をとんとん叩きながら思い出そうとしている。
「それじゃ、城下町での楽しみが一つ増えたな。お前の仕事ぶりの見学と、それからその喫茶店だ。」
「・・・ほんとに仕事してるとこにくるの?」
カインは話を途中でやめ、恨めしげな視線を私に向けた。
「そりゃそうだよ。せっかくの職場見学だからね。」
とっさに話を逸らしてしまった。商売道具を割ってしまうほど、きっとそのマスターは動揺したに違いない。あんなにそっくりな顔立ちでも、20年近く前に一度や二度出会っただけの人物と、今目の前にいる人間に血縁関係があるかどうかなんてふつうは考えない。ライザーさんとそのマスターが顔見知りであろうことは、私しか知らないことだ。でもいつまでもこの話を続けていれば、勘のいい妻は何かがおかしいと気づき始めるかもしれない。
「はぁ〜・・・。仕方ないか。それじゃ、そろそろさっきの続きを話してよ。父さんはつらいかもしれないけど、僕はここまで聞いたんだからどうしても最後まで聞きたい。でも父さんが話せるところまででいいよ。」
「話すと約束したところまでは話すよ・・・。」
正直なところ本当に約束したところまで話せるものなのか、自信はない。でもせめて、あの時起きた出来事を包み隠さず話そうとは思う。ライラを思いとどまらせるために、ライザーさんはおそらくかなり詳しくハース鉱山での出来事を話しているに違いない。にもかかわらず、ライラは自分の信念を貫き通し、夢に向かって着実に歩みを進めている。カインもフローラも、もう小さな子供ではないのだ。どんな重荷を背負うことになっても、必ず自分の力で道を切り開いていくだろう。
扉の先には、細長い通路が奥まで続いている。人の気配はないが、壁に松明がともされているところを見ると、まったく使われていないと言うわけでもなさそうだ。注意深く一歩ずつ進んでいく。
「・・・どうやらハース城の中に入ったみたいだね・・・。」
「・・・そうね。父さんはどこにいるのかしら・・・。ねぇクロービス、父さん・・私に会ったら、最初に何て言うと思う?ふふふ、楽しみだな・・どんな顔するんだろう。」
城の中に入れたことで気がゆるんだのか、ウィローの頭の中は、父親と再会した時に何を話そうかと、そんなことでいっぱいらしい。19年ぶりの親子の再会・・・。それが幸せなものであるように、私は心の中で必死で祈っていた。やがて現れた階段を上がりきったところにまた扉がある。通路が奥に向かって延びているところを見ると、この扉の向こうはどうやら何かの部屋らしい。扉の上の方に張ってあるプレートにはおそらくこの部屋が何の部屋なのか書かれていたのだろうが、今ではすり切れたように文字が消え、よく見えない。
「ここは・・・何の部屋なのかしら・・・。」
「とりあえず誰もいないようなら入ってみよう。少し離れてて。」
私は用心して剣を抜くと、扉にそっと近づきパッと開けた。中には誰もいない。扉の正面の壁際に、机と肘掛けのついた立派な椅子がおかれている。部屋の中央にはどっしりとした風合いを持つテーブルと揃いの椅子が5脚。ここはどうやら身分の高い人の部屋らしかった。もしかしたら・・・ここがデールさんの部屋かも知れない。この立派な家具調度品の数々は、統括者の部屋にこそふさわしいものだ。だが、その立派な部屋の中にあって、同じように立派ではあるのになぜか不釣り合いなものが一つだけあった。それは部屋の片隅に置かれているピアノだ。どうしてこんなところにおいてあるのだろう。
「ねぇクロービス、ここってもしかして・・・統括者の部屋なのかしら・・・。父さんの・・・。」
「そんな感じはするんだけど・・・でもここはずっと使われてないみたいだよ。部屋を別な場所に移したのかな・・・。」
備品をそのままにして部屋の場所だけ替えるほうが不自然だが、そうとしか説明のしようがない。
「ピアノがあるね・・・。」
「うん・・・。何でこんなところにあるんだろう。」
「・・・父さんが・・・練習していたのかもしれないわ。」
「練習・・・?」
デールさんはピアノが趣味だったのだろうか。ウィローは私の問いには答えず、まっすぐにピアノの前に歩み寄り、そっとふたを開けた。
「鍵盤はきれいだわ・・・。よく手入れされているみたい。ねぇクロービス、ちょっとだけ・・・弾いてみていい?」
「へえ・・・君もピアノ弾けるんだね。」
「あら、あなたも弾けるの?」
「弾けるよ。父に教わったからね。」
「そう・・・。私は母さんからよ。ねぇ、弾いても大丈夫かな・・・?」
「ちょっと待ってて。」
私はそっと扉の外を窺った。人の気配は相変わらずない。扉は厚く頑丈で、ぴたりと閉めれば余程大きな音でもたてない限り、外に聞こえる心配はなさそうだった。
「大丈夫みたいだけど・・・。あんまり大きな音は出さないでね。」
言いながら私は、用心深く扉をぴたりと閉めて中から鍵をかけた。これなら万が一見つかっても、とりあえず不意打ちを食らうことはない。
「ありがとう・・・。」
私は部屋の中央に置かれているテーブルの椅子に腰掛けた。ウィローがピアノを弾けることに驚いたが、弾き始めたその曲を聞いて、私はもっと驚いた。心臓が飛び出すかと思うほどだった。弾きながら、ウィローが私に語りかけてくる。
「ねぇクロービス・・・。」
「ん・・・?」
「私ね・・・本当言うと・・・父さんのこと、顔も憶えてないのよ・・・。」
「・・・・・・・・・。」
「あなたとカインは・・・きっと気づいていたわよね・・・。父さんは、19年前にハース鉱山に行ってしまってから、一度も帰ってこなかったんだもの・・・。へへ、笑っちゃうでしょ・・・?あれだけ父さん父さんて言っておきながら、父さんがどんな人かも知らないのよ、私・・・。」
ウィローが小さく鼻をすする音が聞こえた。
「鉱山で父さんと一緒に仕事をしていた人達は、誰も父さんのことをよく言わないけど・・・。でもね、私にはわかるの。父さんがすごく優しい人だってこと。理由は・・そうね・・・私が、そう信じて今まで生きてきたから・・・かな・・・。」
そこでウィローは言葉を切り、振り向いて少し寂しげな笑顔を見せた。
「この曲はね、父さんが私にくれたの。誰が作ったものなのかはわからないけど、ずっとずっと昔、優しい思いやりのある子になるようにって、父さんが私にプレゼントしてくれたのよ。曲の名前はね・・・」
「『Lost Memory』だね。」
「どうして知っているの!?」
ウィローの手が止まり、曲がとぎれた。私は自分の荷物の一番奥に大事にしまってあった楽譜を取りだして、譜面台の上にのせた。
「これは・・・。私が持っているのと同じ楽譜だわ・・・。どうしてこれをあなたが持っているの・・・・?」
「父が亡くなってから、家の中にあったピアノの上に置かれていたんだ。なぜ父がこの曲を私に遺したのか・・・それは解らないんだけど・・・。でも今君がこの曲を弾き始めたのを聞いて、すごくびっくりしたよ。」
「そう・・・。あなたも・・・この曲を・・・。」
ウィローは譜面代に載せられた楽譜をしげしげと見つめている。私は立ち上がりウィローの隣に歩み寄った。
「もう一度・・・一緒に弾いてみない?」
「あなたと・・・一緒に・・・?」
ウィローが私を見上げた。ナイト輝石のような深い藍色の瞳が私をとらえる。
「そう、一緒に・・・。」
ウィローが微笑み、うなずいた。
「そうね、一緒に弾いてみましょう。」
「それじゃ私が左手で弾くから、君は右手のほうで弾いてよ。」
そして私達は、もう一度最初から『Lost Memory』を弾き始めた。私はウィローの肩に右手をかけ、ウィローは私の背中に左手を回し、そして私の左手とウィローの右手が、鍵盤の上を滑りながら一つの曲を奏でていく。
「この曲を作ったのは・・・一体誰なのかしらね・・・。」
「君も知らないんだね。」
「ええ・・・。この曲はね、私が産まれた時に父さんが誰かからもらったらしいの・・・。小さな頃・・・父さんが不器用な手で一生懸命弾いてくれたこと、おぼろげだけど憶えているわ・・・。母さんが言ってた・・・。父さんはピアノなんて全然弾けないのに、この曲だけは一生懸命練習して、でもなかなかうまく弾けなくて、なのに絶対に母さんに教わろうとしなかったんだって。いつもなら、わからないことがあれば相手が誰でも頭を下げて教えてもらう父さんが、どうしてあんなに意地を張っていたのか不思議に思ったそうよ・・・。でもそれもみんな聞いた話・・・。私は父さんのいない日々しか知らないわ・・・。家族揃って幸せに暮らす人々を見て、恨めしく思うこともあったわ。そんな時にはね、いつもこの曲を弾くの・・・。そうすると不思議なの・・・。忘れてしまっていた子供の頃の想い出が、次々と浮かんできて・・・いつのまにか・・・何に対しても純粋だった子供の頃の気持ちに戻っているの・・・。そして誰かを恨めしく思う気持ちなんて、すっかり吹き飛んでしまうのよ・・・。」
私はこの曲を初めて弾いた時のことを思い出していた。父がいなくなって、がらんとした家の中で見つけた一枚の楽譜。訳がわからないまま弾き始めた時のあの不思議な感覚・・・。
「この曲を聞くと・・・みんなそう言うよ。私自身もそうだったし・・・この曲を昔剣士団の先輩達に弾いて聞かせたことがあったんだ。その時も・・・そんなことを言っていたよ・・・。不思議な曲だよね・・・。」
「そうね・・・。私は・・・この曲を聞くたび、いつも父さんのことを思い出すの。父さんが私を愛してくれなかったことは、どう強がっても否定は出来ないわ・・・。だけど私は、やっぱり父さんのことが好き・・・。だって私の父さんなんだもの、大好きよ・・・。」
私の背中に回されたウィローの腕に力がこもった。このまま時が止まってしまえばいいのに・・・。そんなことを強く願うほど、充実した時間だった。だがやがて曲には終わりが来る。最後の音の響きがついに消え、部屋の中に静寂が戻っても、二人ともしばらく動かなかった。
「やだ・・・涙が出ちゃったわ。泣いてる場合じゃないわよね。」
見るとウィローは、流れる涙を必死でごしごしとこすっている。実を言うと、私自身も目の縁に涙がたまっていた。この曲はいつも、胸の奥にしまい込まれた懐かしいものを呼び覚ます。
「・・・そろそろここを出なくちゃならないね。」
私はウィローの肩をなだめるようにぽんぽんと叩きながら声をかけた。私を見上げたウィローはまだ少し赤い目をしていたが、それでも力強く頷いた。
「そうね、行きましょう。」
私は楽譜を荷物にしまい込み、ウィローは鍵盤を丁寧に拭いて、ピアノのふたを閉めてカバーをかけ直した。そしてどちらからともなくお互いを見つめ合い微笑んだ。
「不思議だわ・・・。あなたと私はついこの間知り合ったばかりなのに・・・同じ楽譜をそれぞれの父さんから託されていて・・・。あなたのお父さんと私の父さんは会ったことがあるのかしら・・・。」
「どうなんだろう・・・。君と違って私の楽譜は、ただそこに置いてあっただけだから・・・。何の説明もされたわけじゃないし・・・。今に至るまで、何も解らないんだ・・・。でも・・・この曲を以前聞いたことがあるんだよ。王宮で・・・。」
「王宮!?」
「そう。フロリア様のお住まいのある塔の中でね。」
「フロリア様が弾いてたの?」
「そこまでは解らないよ。でもこの曲を聞いた剣士団の先輩達が、やっぱり言っていたよ、前にもそこで聞いたことがあるって。」
「そう・・・。どういうことなのかしら・・・。」
ウィローはしばらく考えていたがハッとして叫んだ。
「ねぇ!父さんは・・・私の父さんは昔王宮にいたのよ・・・!」
「王宮に!?君の父さんが!?」
「そうよ・・・。父さんは、昔エルバール王国の大臣だったの。だから私は・・・カナじゃなくて、エルバールの城下町で生まれたって・・・母さんが昔教えてくれたわ。」
「大臣て・・・御前会議の?」
「そこまではよくわからないけど・・・大臣て言うのは、御前会議の人たちのことなの?」
「そうだよ。王宮で大臣といえば、御前会議のメンバーだけだと思う・・・。そうか・・・君の父さんが・・・御前会議の大臣・・・。」
あまりにも意外なこの話に、私はすっかり驚いてしまった。ではもしも、ウィローの父親がハース鉱山に来ずに大臣の職にとどまっていたら、ウィローは私など手の届かない存在であったかも知れない・・・。
「どうしたの?そんなにびっくりしたの!?」
「あ、う・・うん・・・。君が大臣のお嬢様だったなんて思わなくてさ・・・。」
「いやぁね。そんなの昔の話よ。だいたいその頃のことなんて私何にも憶えてないわ。」
ウィローは私の顔を覗き込んでくすりと笑った。
「そうだね・・・。ごめん。あんまりびっくりしたもんだから・・・。でも君の父さんはともかく、私の父は王宮になんて縁がないはずだよ。」
「そう・・・。不思議ね・・・。」
「うん・・・。そろそろ行こう。この先どのくらいかかるのかわからないし。一ヶ所にあんまり長くいないほうがいいよ。」
「そうね。」
私達はそっと部屋を出ると、奥へと延びた通路を慎重に進んでいった。やがて階段が現れる。上の階にも人の気配が感じられない。だが・・・異様な臭気が立ちこめている。
「なにかしら・・・。この匂い・・・。」
「上の階から匂って来るみたいだけど・・・異様な匂いだな・・・。ウィロー、大丈夫?」
「大丈夫よ。毒はないみたいだし・・・。」
「・・・行こう。」
階段を上がると、そこには扉はなかった。真っ暗で何も見えなかったが、壁などがある気配もない。もしかしたらここは、一つの大きなフロアになっているのかも知れない。荷物からランプを取り出し火をつける。パッと明るくなった部屋の中で私達が見たものは・・・累々と横たわる白骨死体だった。
「・・・・!!」
ウィローは叫び出しそうになったが、やっとの事で声を出さずにこらえた。私にしがみつき、がたがたと震えている。一体何人分の死体があるのか・・・5人や10人できかないことは確かだった。
「こ・・・これ・・・。」
ウィローがやっとの事で声を出した。歯の根が合わないほどに震えているので、なかなかうまく言葉にならない。
「こ・・・鉱・・・山で・・亡くなった人達なの・・・?」
「たぶん・・・ね・・・。」
そういう私もこんなにたくさんの死体の山など初めて見る。私まで動揺していることがウィローに知れたらよけい不安にさせるかもしれない。でもどうしても、声の震えを止めることが出来ない。
「そんな・・・。」
ウィローの声が涙声になる。
「ひどい・・・。埋葬もされてないなんて・・・。こんなに・・・こんなにたくさんの人達が・・・。」
あまりにも凄惨な光景に、私達はしばらくの間どうしていいかわからず立ちすくんでいた。だが、この死体の山を埋葬してやれるだけの時間はない。
「・・・とにかく進もう・・・。ゆっくりでいいよ。」
私達は歩き出した。ウィローは私に寄りかかるようにしがみついたまま、やっとの事で歩いている。ランプで足許を照らしながら、せめて死体を踏んだりしないように慎重に歩を進め、フロアの奥にあった扉の近くまで辿り着いた時には、このフロアにあがってからかなりの時間が過ぎていた。
「ここにも・・・死体があるわ・・・。」
扉の手前に、折り重なるようにして二つの死体が転がっていた。ウィローはもうたくさんだというように、頭を左右に振っている。私は黙ってウィローの肩を叩きながら、死体をのぞき込んだ。二人のうち、下になっているほうの一人は他の死体よりも身なりがいい。私はその二つの死体の前にしゃがみ込んだ。死体の手に手紙らしきものが握りしめられていたのを見つけたからだ。
「ク、クロービス・・・どうしたの?」
ウィローが怯えたように私の隣にしゃがみ込み、私にしっかりとしがみついた。
「この二人・・・何となくお互いをかばい合っているように見えてね。どっちも男性みたいだけど・・・下の方の人が手紙を持っているんだ。ちょっと見せてもらおう。」
私は下になっている白骨の手から手紙を取り出した。既に骨だけになった指の間から、手紙はするりと抜けた。多分・・・死体が腐乱する過程で、一度この手紙は水分を含んだのだろう。紙はバリバリになっていたし、インクもあちこち滲んでいた。そして最後のほうはかなり文字が乱れている。それでも何とか読むことは出来そうだ。私はランプに手紙をかざし、私の隣で震えながら覗き込むウィローと共にその手紙を読み始めた。
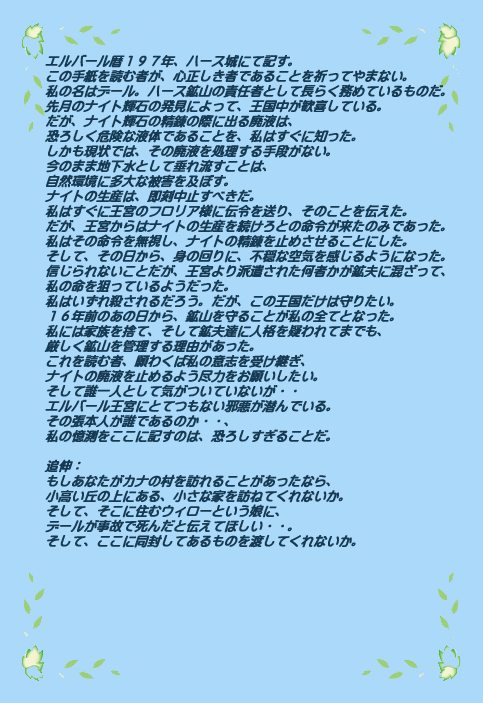
読めるのはここまでだった。そのあとに書いてある文字は、ランプの光だけでは判読しがたいほどに乱れていて、とても読むことが出来なかった。封筒の奥に何か入っている。取り出してみると、美しい純白の石がはめられた指輪だった。私の隣で、ウィローは呆然としたまま手紙を見つめ続けている。
「この人が・・・デールさんだったんだね・・・。」
ウィローはゆっくりと頷いた。